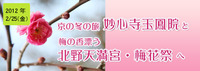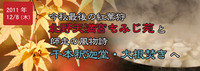2013年04月21日
4/14 白峯神宮の奉納蹴鞠見学と雨宝院の遅咲き桜を訪ねて
4月14日(日)のらくたび京都さんぽは、
白峯神宮の春の例祭で奉納される、貴族のたしなみ蹴鞠を見学し、
西陣の路地を通りぬけながら、雨宝院などの遅咲き桜を楽しみました。

出発は、地下鉄今出川駅。まずは妙顕寺を目指します。
烏丸通から上立売通、室町通に囲まれた一角には
かつて室町幕府の花の御所があったと、
先生より解説して頂きます。何気ない街中にも歴史が隠されていますね。

妙顕寺には、まだ遅咲きのしだれ桜が残っていてくれました。
今回は、17日連続の「とっておきの桜さんぽ」の一企画で、
遅咲き桜もあちこちで咲いていました。

西陣には日蓮宗の本山がいくつもありますが、
中でも妙顕寺は、京都に日蓮宗を布教した日像上人が
京都で初めて開いたお寺です。

続いて、同じ日蓮宗の妙覚寺へ。
聚楽第の遺構とも伝わる門前では、八重桜が咲き誇っていました。

妙覚寺は、戦国時代に織田信長の宿所としても使われ、
もし信長が打たれた時に妙覚寺にいれば
「妙覚寺の変」になったかもなど、
本能寺の変に関わる興味深いお話が山村先生から語られます。

堀川通に面した水火天満宮も、しだれ桜が美しい神社。
道真を大宰府に左遷した醍醐天皇によって創建された
由緒ある天満宮です。

堀川通を渡って、櫟谷(いちいだに)七野神社へ。
神社は、賀茂社に奉仕する斎王の御所である賀茂斎院の跡地です。
葵祭に際しては、斎王代も参拝に来られるのだとか。

西陣を散策して、いよいよ今回の桜のメイン、雨宝院へとやってきました。
境内は遅咲き桜が所狭しと咲いていて、空が見えないほどです。

弘法大師によって創建されたという雨宝院には、
平安時代初期の十一面観音像が伝わります。私たちも拝観を行いました。
穏やかな表情をされた立派な仏様で、すぐ近くで拝ませて頂きました。

境内は桜が見事で、足元を見れば雪のように花弁が積もっています。

黄緑色の花を咲かせる御衣黄(ぎょいこう)桜も、知られています。

続いて、西陣の細い路地を抜けながら、
蹴鞠が奉納される白峯神宮へと向かいました。

、
4月14日は、白峯神宮の淳仁天皇大祭です。
白峯神宮の境内は蹴鞠の飛鳥井家の邸宅跡で、
蹴鞠道の神である精大明神も祀られているため、
祭事では蹴鞠が奉納されます。

取れそうもない玉を拾ってしまうなど
見事な足技を見せて頂きました。
ちょうど「黄桜」も満開で、
珍しい薄黄緑色の花を咲かせていました。

再び界隈の散策へ。
こちらは本阿弥光悦の京屋敷跡。
鷹峯のイメージが強いですが、代々の屋敷が街中にありました。

続いて、狩野元信の屋敷跡。
狩野派2代めの人物です。

さらに武者小路千家の前へ。
落ちついた佇まいをされていました。

新町通にある霊光殿天満宮。
鳥居には「天下無敵 必勝利運」と書かれた額が。
この神社のご神徳で蒙古を撃退できたとして、
時の天皇から授かった言葉だそうです。

最後は福長神社。
ご祭神は元は宮中に祀られていた井戸の神で、
現在も住宅街の中で大切に祀られていました。

この後、地下鉄今出川駅に戻って、解散となりました。
今回は遅咲き桜も見られ、蹴鞠の妙技を堪能でき、
点在している史跡や歴史を秘めたお社へも足を運ぶなど、
密度の濃い散策だったのではないかと思います。
ご参加頂きまして、ありがとうございました。
(霊光殿天満宮に、牡丹が咲いていました。)

ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
白峯神宮の春の例祭で奉納される、貴族のたしなみ蹴鞠を見学し、
西陣の路地を通りぬけながら、雨宝院などの遅咲き桜を楽しみました。
出発は、地下鉄今出川駅。まずは妙顕寺を目指します。
烏丸通から上立売通、室町通に囲まれた一角には
かつて室町幕府の花の御所があったと、
先生より解説して頂きます。何気ない街中にも歴史が隠されていますね。
妙顕寺には、まだ遅咲きのしだれ桜が残っていてくれました。
今回は、17日連続の「とっておきの桜さんぽ」の一企画で、
遅咲き桜もあちこちで咲いていました。
西陣には日蓮宗の本山がいくつもありますが、
中でも妙顕寺は、京都に日蓮宗を布教した日像上人が
京都で初めて開いたお寺です。
続いて、同じ日蓮宗の妙覚寺へ。
聚楽第の遺構とも伝わる門前では、八重桜が咲き誇っていました。
妙覚寺は、戦国時代に織田信長の宿所としても使われ、
もし信長が打たれた時に妙覚寺にいれば
「妙覚寺の変」になったかもなど、
本能寺の変に関わる興味深いお話が山村先生から語られます。
堀川通に面した水火天満宮も、しだれ桜が美しい神社。
道真を大宰府に左遷した醍醐天皇によって創建された
由緒ある天満宮です。
堀川通を渡って、櫟谷(いちいだに)七野神社へ。
神社は、賀茂社に奉仕する斎王の御所である賀茂斎院の跡地です。
葵祭に際しては、斎王代も参拝に来られるのだとか。
西陣を散策して、いよいよ今回の桜のメイン、雨宝院へとやってきました。
境内は遅咲き桜が所狭しと咲いていて、空が見えないほどです。
弘法大師によって創建されたという雨宝院には、
平安時代初期の十一面観音像が伝わります。私たちも拝観を行いました。
穏やかな表情をされた立派な仏様で、すぐ近くで拝ませて頂きました。
境内は桜が見事で、足元を見れば雪のように花弁が積もっています。
黄緑色の花を咲かせる御衣黄(ぎょいこう)桜も、知られています。
続いて、西陣の細い路地を抜けながら、
蹴鞠が奉納される白峯神宮へと向かいました。
、
4月14日は、白峯神宮の淳仁天皇大祭です。
白峯神宮の境内は蹴鞠の飛鳥井家の邸宅跡で、
蹴鞠道の神である精大明神も祀られているため、
祭事では蹴鞠が奉納されます。
取れそうもない玉を拾ってしまうなど
見事な足技を見せて頂きました。
ちょうど「黄桜」も満開で、
珍しい薄黄緑色の花を咲かせていました。
再び界隈の散策へ。
こちらは本阿弥光悦の京屋敷跡。
鷹峯のイメージが強いですが、代々の屋敷が街中にありました。
続いて、狩野元信の屋敷跡。
狩野派2代めの人物です。
さらに武者小路千家の前へ。
落ちついた佇まいをされていました。
新町通にある霊光殿天満宮。
鳥居には「天下無敵 必勝利運」と書かれた額が。
この神社のご神徳で蒙古を撃退できたとして、
時の天皇から授かった言葉だそうです。
最後は福長神社。
ご祭神は元は宮中に祀られていた井戸の神で、
現在も住宅街の中で大切に祀られていました。
この後、地下鉄今出川駅に戻って、解散となりました。
今回は遅咲き桜も見られ、蹴鞠の妙技を堪能でき、
点在している史跡や歴史を秘めたお社へも足を運ぶなど、
密度の濃い散策だったのではないかと思います。
ご参加頂きまして、ありがとうございました。
(霊光殿天満宮に、牡丹が咲いていました。)
ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
11月10日 報恩寺「鳴虎図」と聚楽第の足跡めぐり
8月12日 金閣寺と上七軒ビアガーデン
2月25日(土) 妙心寺玉鳳院と梅の香漂う北野天満宮へ
12月8日(木)北野天満宮・もみじ苑と千本釈迦堂・大根焚き
西陣の町家文化財 冨田屋で過ごす夏の茶話会
京都三奇祭やすらい祭見学と西陣の隠れ桜めぐり
8月12日 金閣寺と上七軒ビアガーデン
2月25日(土) 妙心寺玉鳳院と梅の香漂う北野天満宮へ
12月8日(木)北野天満宮・もみじ苑と千本釈迦堂・大根焚き
西陣の町家文化財 冨田屋で過ごす夏の茶話会
京都三奇祭やすらい祭見学と西陣の隠れ桜めぐり