2013年04月21日
4/14 白峯神宮の奉納蹴鞠見学と雨宝院の遅咲き桜を訪ねて
4月14日(日)のらくたび京都さんぽは、
白峯神宮の春の例祭で奉納される、貴族のたしなみ蹴鞠を見学し、
西陣の路地を通りぬけながら、雨宝院などの遅咲き桜を楽しみました。

出発は、地下鉄今出川駅。まずは妙顕寺を目指します。
烏丸通から上立売通、室町通に囲まれた一角には
かつて室町幕府の花の御所があったと、
先生より解説して頂きます。何気ない街中にも歴史が隠されていますね。

妙顕寺には、まだ遅咲きのしだれ桜が残っていてくれました。
今回は、17日連続の「とっておきの桜さんぽ」の一企画で、
遅咲き桜もあちこちで咲いていました。

西陣には日蓮宗の本山がいくつもありますが、
中でも妙顕寺は、京都に日蓮宗を布教した日像上人が
京都で初めて開いたお寺です。

続いて、同じ日蓮宗の妙覚寺へ。
聚楽第の遺構とも伝わる門前では、八重桜が咲き誇っていました。

妙覚寺は、戦国時代に織田信長の宿所としても使われ、
もし信長が打たれた時に妙覚寺にいれば
「妙覚寺の変」になったかもなど、
本能寺の変に関わる興味深いお話が山村先生から語られます。

堀川通に面した水火天満宮も、しだれ桜が美しい神社。
道真を大宰府に左遷した醍醐天皇によって創建された
由緒ある天満宮です。

堀川通を渡って、櫟谷(いちいだに)七野神社へ。
神社は、賀茂社に奉仕する斎王の御所である賀茂斎院の跡地です。
葵祭に際しては、斎王代も参拝に来られるのだとか。

西陣を散策して、いよいよ今回の桜のメイン、雨宝院へとやってきました。
境内は遅咲き桜が所狭しと咲いていて、空が見えないほどです。

弘法大師によって創建されたという雨宝院には、
平安時代初期の十一面観音像が伝わります。私たちも拝観を行いました。
穏やかな表情をされた立派な仏様で、すぐ近くで拝ませて頂きました。

境内は桜が見事で、足元を見れば雪のように花弁が積もっています。

黄緑色の花を咲かせる御衣黄(ぎょいこう)桜も、知られています。

続いて、西陣の細い路地を抜けながら、
蹴鞠が奉納される白峯神宮へと向かいました。

、
4月14日は、白峯神宮の淳仁天皇大祭です。
白峯神宮の境内は蹴鞠の飛鳥井家の邸宅跡で、
蹴鞠道の神である精大明神も祀られているため、
祭事では蹴鞠が奉納されます。

取れそうもない玉を拾ってしまうなど
見事な足技を見せて頂きました。
ちょうど「黄桜」も満開で、
珍しい薄黄緑色の花を咲かせていました。

再び界隈の散策へ。
こちらは本阿弥光悦の京屋敷跡。
鷹峯のイメージが強いですが、代々の屋敷が街中にありました。

続いて、狩野元信の屋敷跡。
狩野派2代めの人物です。

さらに武者小路千家の前へ。
落ちついた佇まいをされていました。

新町通にある霊光殿天満宮。
鳥居には「天下無敵 必勝利運」と書かれた額が。
この神社のご神徳で蒙古を撃退できたとして、
時の天皇から授かった言葉だそうです。

最後は福長神社。
ご祭神は元は宮中に祀られていた井戸の神で、
現在も住宅街の中で大切に祀られていました。

この後、地下鉄今出川駅に戻って、解散となりました。
今回は遅咲き桜も見られ、蹴鞠の妙技を堪能でき、
点在している史跡や歴史を秘めたお社へも足を運ぶなど、
密度の濃い散策だったのではないかと思います。
ご参加頂きまして、ありがとうございました。
(霊光殿天満宮に、牡丹が咲いていました。)

ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
白峯神宮の春の例祭で奉納される、貴族のたしなみ蹴鞠を見学し、
西陣の路地を通りぬけながら、雨宝院などの遅咲き桜を楽しみました。
出発は、地下鉄今出川駅。まずは妙顕寺を目指します。
烏丸通から上立売通、室町通に囲まれた一角には
かつて室町幕府の花の御所があったと、
先生より解説して頂きます。何気ない街中にも歴史が隠されていますね。
妙顕寺には、まだ遅咲きのしだれ桜が残っていてくれました。
今回は、17日連続の「とっておきの桜さんぽ」の一企画で、
遅咲き桜もあちこちで咲いていました。
西陣には日蓮宗の本山がいくつもありますが、
中でも妙顕寺は、京都に日蓮宗を布教した日像上人が
京都で初めて開いたお寺です。
続いて、同じ日蓮宗の妙覚寺へ。
聚楽第の遺構とも伝わる門前では、八重桜が咲き誇っていました。
妙覚寺は、戦国時代に織田信長の宿所としても使われ、
もし信長が打たれた時に妙覚寺にいれば
「妙覚寺の変」になったかもなど、
本能寺の変に関わる興味深いお話が山村先生から語られます。
堀川通に面した水火天満宮も、しだれ桜が美しい神社。
道真を大宰府に左遷した醍醐天皇によって創建された
由緒ある天満宮です。
堀川通を渡って、櫟谷(いちいだに)七野神社へ。
神社は、賀茂社に奉仕する斎王の御所である賀茂斎院の跡地です。
葵祭に際しては、斎王代も参拝に来られるのだとか。
西陣を散策して、いよいよ今回の桜のメイン、雨宝院へとやってきました。
境内は遅咲き桜が所狭しと咲いていて、空が見えないほどです。
弘法大師によって創建されたという雨宝院には、
平安時代初期の十一面観音像が伝わります。私たちも拝観を行いました。
穏やかな表情をされた立派な仏様で、すぐ近くで拝ませて頂きました。
境内は桜が見事で、足元を見れば雪のように花弁が積もっています。
黄緑色の花を咲かせる御衣黄(ぎょいこう)桜も、知られています。
続いて、西陣の細い路地を抜けながら、
蹴鞠が奉納される白峯神宮へと向かいました。
、
4月14日は、白峯神宮の淳仁天皇大祭です。
白峯神宮の境内は蹴鞠の飛鳥井家の邸宅跡で、
蹴鞠道の神である精大明神も祀られているため、
祭事では蹴鞠が奉納されます。
取れそうもない玉を拾ってしまうなど
見事な足技を見せて頂きました。
ちょうど「黄桜」も満開で、
珍しい薄黄緑色の花を咲かせていました。
再び界隈の散策へ。
こちらは本阿弥光悦の京屋敷跡。
鷹峯のイメージが強いですが、代々の屋敷が街中にありました。
続いて、狩野元信の屋敷跡。
狩野派2代めの人物です。
さらに武者小路千家の前へ。
落ちついた佇まいをされていました。
新町通にある霊光殿天満宮。
鳥居には「天下無敵 必勝利運」と書かれた額が。
この神社のご神徳で蒙古を撃退できたとして、
時の天皇から授かった言葉だそうです。
最後は福長神社。
ご祭神は元は宮中に祀られていた井戸の神で、
現在も住宅街の中で大切に祀られていました。
この後、地下鉄今出川駅に戻って、解散となりました。
今回は遅咲き桜も見られ、蹴鞠の妙技を堪能でき、
点在している史跡や歴史を秘めたお社へも足を運ぶなど、
密度の濃い散策だったのではないかと思います。
ご参加頂きまして、ありがとうございました。
(霊光殿天満宮に、牡丹が咲いていました。)
ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
2012年11月18日
11月10日 報恩寺「鳴虎図」と聚楽第の足跡めぐり
11月10日(土)のらくたび京都さんぽは、
秀吉伝説が伝わる特別公開の鳴虎図を報恩寺で見学し、
同じく特別公開の浄福寺も訪れながら、
秀吉ゆかりの聚楽第の足跡をたどりました。

出発は地下鉄の鞍馬口駅。
まずは妙覚寺へと向かいました。
門前の桜も綺麗な妙覚寺の表門は、
聚楽第の裏門を移築したものともいわれています。

くぐり戸が二つあるのが特徴ですよ。

妙覚寺からは小川通を南へ。本法寺の前にはかつて流れていた
「小川(こかわ)」跡にかかっていた橋も残されています。

一帯は綺麗な井戸水も手に入りやすかったため、
表千家・裏千家の茶室もあります。

そして「鳴虎図」が特別公開されている報恩寺へ!
12年に1度、寅(とら)年の正月三が日にしか公開されない絵が見られるのです。
鳴虎図は非常に繊細なタッチで描かれていました。
秀吉がこの絵を所望して聚楽第に持ち帰りましたが、
夜に吠えて眠れず、寺に返したといわれています。

報恩寺は「撞かずの鐘」でも知られています。
現在は大みそかの夜に撞かれていて、幻の音色を聞くことが出来ます。

堀川通ではイチョウも黄色く色づいていました。
イチョウの下は公園になっていて、
もうじき黄金色の絨毯になりますね。

こちらは山名宗全の邸宅跡。
応仁の乱で東軍の細川勝元と対峙した西軍の本拠地で、
それゆえ一帯が「西陣」と呼ばれています。

幾多の大火をくぐりぬけ、焼けずの寺で知られる本隆寺では、
いけばな展が行われていました。しばし見学させて頂きました。

さて、今出川通を南へ渡って、
いよいよ聚楽第の範囲へと入って来ました。
この道が北の端だそうですよ。

そして特別公開の浄福寺へ到着です。
鮮やかな赤門が印象的です。

浄福寺の本堂は最古の違法建築といわれています。
江戸時代には建物の大きさを三間、すなわち約5.4mまでに
規制する三間梁規制がありました。
しかし、法要などのために多くの人が入れる場所が必要だった浄福寺は、
外観は別棟のようにして中はこっそりつなげて広くしたそうです。

方丈の天井に張られた龍の絵は、
真下で手を叩くと「び~ん」と響く鳴き龍です。
他にも、住職による絵解きもあって、楽しませていただきました。

さて、浄福寺を後にして、再び聚楽第の跡をたどります。
こちらは濠跡が見つかった付近で、石碑が立っています。

さらには聚楽第にあったという梅雨の井へ。
現在は住宅地の中に隠れるようにあります。

そして聚楽第の濠跡に立つとされる松林寺。
境内は辺りよりも土地が低なっています。

今回は聚楽第推定地の南端・丸太町通で解散となりました。
聚楽第跡は今は住宅地ですが、僅かながら痕跡が残されていて、
何気ない風景でも先生の解説があると「なるほど」と思えます。

報恩寺と浄福寺の非公開文化財も
素晴らしいものばかり。個人的には報恩寺の小さな千体地蔵尊に感動しました。
今回も多くの方にご参加いただきまして、ありがとうございました。

ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
秀吉伝説が伝わる特別公開の鳴虎図を報恩寺で見学し、
同じく特別公開の浄福寺も訪れながら、
秀吉ゆかりの聚楽第の足跡をたどりました。
出発は地下鉄の鞍馬口駅。
まずは妙覚寺へと向かいました。
門前の桜も綺麗な妙覚寺の表門は、
聚楽第の裏門を移築したものともいわれています。
くぐり戸が二つあるのが特徴ですよ。
妙覚寺からは小川通を南へ。本法寺の前にはかつて流れていた
「小川(こかわ)」跡にかかっていた橋も残されています。
一帯は綺麗な井戸水も手に入りやすかったため、
表千家・裏千家の茶室もあります。
そして「鳴虎図」が特別公開されている報恩寺へ!
12年に1度、寅(とら)年の正月三が日にしか公開されない絵が見られるのです。
鳴虎図は非常に繊細なタッチで描かれていました。
秀吉がこの絵を所望して聚楽第に持ち帰りましたが、
夜に吠えて眠れず、寺に返したといわれています。
報恩寺は「撞かずの鐘」でも知られています。
現在は大みそかの夜に撞かれていて、幻の音色を聞くことが出来ます。
堀川通ではイチョウも黄色く色づいていました。
イチョウの下は公園になっていて、
もうじき黄金色の絨毯になりますね。
こちらは山名宗全の邸宅跡。
応仁の乱で東軍の細川勝元と対峙した西軍の本拠地で、
それゆえ一帯が「西陣」と呼ばれています。
幾多の大火をくぐりぬけ、焼けずの寺で知られる本隆寺では、
いけばな展が行われていました。しばし見学させて頂きました。
さて、今出川通を南へ渡って、
いよいよ聚楽第の範囲へと入って来ました。
この道が北の端だそうですよ。
そして特別公開の浄福寺へ到着です。
鮮やかな赤門が印象的です。
浄福寺の本堂は最古の違法建築といわれています。
江戸時代には建物の大きさを三間、すなわち約5.4mまでに
規制する三間梁規制がありました。
しかし、法要などのために多くの人が入れる場所が必要だった浄福寺は、
外観は別棟のようにして中はこっそりつなげて広くしたそうです。
方丈の天井に張られた龍の絵は、
真下で手を叩くと「び~ん」と響く鳴き龍です。
他にも、住職による絵解きもあって、楽しませていただきました。
さて、浄福寺を後にして、再び聚楽第の跡をたどります。
こちらは濠跡が見つかった付近で、石碑が立っています。
さらには聚楽第にあったという梅雨の井へ。
現在は住宅地の中に隠れるようにあります。
そして聚楽第の濠跡に立つとされる松林寺。
境内は辺りよりも土地が低なっています。
今回は聚楽第推定地の南端・丸太町通で解散となりました。
聚楽第跡は今は住宅地ですが、僅かながら痕跡が残されていて、
何気ない風景でも先生の解説があると「なるほど」と思えます。
報恩寺と浄福寺の非公開文化財も
素晴らしいものばかり。個人的には報恩寺の小さな千体地蔵尊に感動しました。
今回も多くの方にご参加いただきまして、ありがとうございました。
ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
2012年08月19日
8月12日 金閣寺と上七軒ビアガーデン
8月12日(日)のらくたび京都さんぽは、らくたび初の金閣寺拝観と、
芸舞妓さんがおもてなしをしてくれる上七軒ビアガーデンでの夜の宴を催しました。

集合は金閣寺。夕方でしたが、まだまだ大勢の観光客で賑わっていました。
らくたびの京都さんぽでは初めての金閣寺の散策です。

象徴でもある金閣(舎利殿)は、この日も西日に輝いて迎えてくれました。
多くの観光客がいる中でも、若村先生の解説はよく聞こえます!

かつては金閣から池泉庭園を眺めた金閣寺。鏡湖池には、
日本列島をかたどったとされる葦原島などがあります。
目の前の島も、解説があると亀の形に見えてきますよ!


金閣寺はお庭も見事。金閣寺垣は、特有の背の低い垣根です。

境内には龍門瀑と呼ばれる滝もあります。
鯉の滝登りにちなんだ石もあり、夏の夕方に清涼な空間を作り出していました。

金閣寺の境内は、元は西園寺家の山荘。
その跡地ともいわれる安民沢には、弁天様の使いである白蛇の塚があります。

お茶室の夕佳亭(せっかてい)は、江戸初期の茶人・金森宗和好みのお茶室。
南天の床柱が有名で、三角や四角の窓などの意匠もユニークです。
「夕日に佳い」との名前にもぴったりの時間帯でした。

金閣寺でたっぷりと学んだあとは、ビアガーデンを目指しながら周辺のお社を散策です。
こちらは、通称「わら天神」の名で知られる敷地神社。安産祈願の信仰を集め、
授与される藁の護符に節があれば男の子、なければ女の子が生まれるのだとか。

桜の名所で知られる平野神社は緑がいっぱいの神社となっていました。
平安遷都時に長岡京から遷された古社で、
御祭神も今を生きる力をくださる「今木神」などユニークです。


かつて京都の街を囲んだお土居の堀の役割も果たした紙屋川を越えると、洛中に。
北野天満宮へは北門から入って行きました。なかなか北門から入ることはありませんね!

後ろの赤いお社は地主(じぬし)神社。祀られているのは天神地祇(てんじんちぎ)で、
菅原道真が祀られる以前から、天の神である天神をお祀りしていた神社です。
北野天満宮の参道は現在の本殿へと真っすぐは続いておらず、実はこのお社へと続く道でした。

こちらは絵馬所。京都で最も古い絵馬堂として多数の絵馬が飾られています。
あの新撰組が「誠」の文字のモチーフにしたともされる絵馬もありますよ。

北野天満宮を抜けると、いよいよお待ちかねの上七軒ビアガーデンです!
暑さの中を歩いてきて、ちょうど喉も乾いてきたころ合いです(笑)

皆様でかんぱ~い!!

らくたびのテーブルには、舞妓の市まりさんがずっと付いてくれました。

舞妓さんが箸袋で折り紙を作ってくれて、こぞって箸袋を渡すほどの人気に!

若村先生や舞妓さんや皆様から貴重なお話をたくさん聞きながら、
夏の宴は大いに盛り上がっていきました。

今回は、金閣寺を詳しく分かりやすい解説を聞きながらじっくりと散策し、
道中の神社も楽しみながら上七軒ビアガーデンに向かいました。
普段お話しする機会の少ない舞妓さんからも
貴重なお話やおもてなしの心を感じることができた散策でした。
雨に降られることなく、昨年のリベンジも果たせましたね。
ご参加頂きまして、ありがとうございました!

ご案内 / らくたび代表・若村 亮
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
芸舞妓さんがおもてなしをしてくれる上七軒ビアガーデンでの夜の宴を催しました。
集合は金閣寺。夕方でしたが、まだまだ大勢の観光客で賑わっていました。
らくたびの京都さんぽでは初めての金閣寺の散策です。
象徴でもある金閣(舎利殿)は、この日も西日に輝いて迎えてくれました。
多くの観光客がいる中でも、若村先生の解説はよく聞こえます!
かつては金閣から池泉庭園を眺めた金閣寺。鏡湖池には、
日本列島をかたどったとされる葦原島などがあります。
目の前の島も、解説があると亀の形に見えてきますよ!
金閣寺はお庭も見事。金閣寺垣は、特有の背の低い垣根です。
境内には龍門瀑と呼ばれる滝もあります。
鯉の滝登りにちなんだ石もあり、夏の夕方に清涼な空間を作り出していました。
金閣寺の境内は、元は西園寺家の山荘。
その跡地ともいわれる安民沢には、弁天様の使いである白蛇の塚があります。
お茶室の夕佳亭(せっかてい)は、江戸初期の茶人・金森宗和好みのお茶室。
南天の床柱が有名で、三角や四角の窓などの意匠もユニークです。
「夕日に佳い」との名前にもぴったりの時間帯でした。
金閣寺でたっぷりと学んだあとは、ビアガーデンを目指しながら周辺のお社を散策です。
こちらは、通称「わら天神」の名で知られる敷地神社。安産祈願の信仰を集め、
授与される藁の護符に節があれば男の子、なければ女の子が生まれるのだとか。
桜の名所で知られる平野神社は緑がいっぱいの神社となっていました。
平安遷都時に長岡京から遷された古社で、
御祭神も今を生きる力をくださる「今木神」などユニークです。
かつて京都の街を囲んだお土居の堀の役割も果たした紙屋川を越えると、洛中に。
北野天満宮へは北門から入って行きました。なかなか北門から入ることはありませんね!
後ろの赤いお社は地主(じぬし)神社。祀られているのは天神地祇(てんじんちぎ)で、
菅原道真が祀られる以前から、天の神である天神をお祀りしていた神社です。
北野天満宮の参道は現在の本殿へと真っすぐは続いておらず、実はこのお社へと続く道でした。
こちらは絵馬所。京都で最も古い絵馬堂として多数の絵馬が飾られています。
あの新撰組が「誠」の文字のモチーフにしたともされる絵馬もありますよ。
北野天満宮を抜けると、いよいよお待ちかねの上七軒ビアガーデンです!
暑さの中を歩いてきて、ちょうど喉も乾いてきたころ合いです(笑)
皆様でかんぱ~い!!
らくたびのテーブルには、舞妓の市まりさんがずっと付いてくれました。
舞妓さんが箸袋で折り紙を作ってくれて、こぞって箸袋を渡すほどの人気に!
若村先生や舞妓さんや皆様から貴重なお話をたくさん聞きながら、
夏の宴は大いに盛り上がっていきました。
今回は、金閣寺を詳しく分かりやすい解説を聞きながらじっくりと散策し、
道中の神社も楽しみながら上七軒ビアガーデンに向かいました。
普段お話しする機会の少ない舞妓さんからも
貴重なお話やおもてなしの心を感じることができた散策でした。
雨に降られることなく、昨年のリベンジも果たせましたね。
ご参加頂きまして、ありがとうございました!
ご案内 / らくたび代表・若村 亮
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
2012年03月06日
2月25日(土) 妙心寺玉鳳院と梅の香漂う北野天満宮へ

小雨降る午後、花園駅に集合し
「 雨きつくならへんかったらいいねぇ〜
 」などと言いながら
」などと言いながら妙心寺へと向かいました。
平安時代、双ヶ丘の麓には四季折々の美しい花が咲き誇ったことから
『 花園 』 と呼ばれた。
その地に室町初期には花園天皇が離宮を営み、のちに禅寺に改められた
ことが妙心寺の始まりです。現在は、臨済宗妙心寺派の大本山で、
広大な敷地に46の塔頭寺院が立ち並んでいます。
山村先生の後ろに見えるのは浴室・明智風呂
光秀の叔父である密宗和尚が光秀の菩提を弔うために建立したとされる。

今回は『 京の冬の旅 』( 〜3/18 )で特別公開されている、妙心寺にとって
最も由緒ある塔頭・玉鳳院を拝観しました。
残念ながら撮影禁止ですが、花園法皇を祀る開山堂「 微笑庵 」や、
狩野派の襖絵、豊臣秀吉の子鶴松の霊屋などをたっぷりと拝見しました。

そして広大な境内にある塔頭寺院の説明をそれぞれ受けながら通り抜け、
東へと進み、地蔵院へと向かいました。
浄土宗・地蔵院( 洛陽三十三所観音霊場の第三十番札所 )
神亀三年 ( 726 )行基が、聖武天皇の勅願により創建したのが始まりである
というほどの歴史をもつ古刹です。こちらは通称 「 椿寺 」と呼ばれている。

写真の椿は「 五色八重散り椿 」といい豊臣秀吉が北野大茶会の縁により
献木したと伝えられています。
現在は二代目で樹齢約100年!、毎年3月下旬〜4月中旬が見頃です。
花びらが一片づつ散るのが特徴で、側に咲く満開の枝垂桜と散椿との
競演がみごとなので、その季節にぜひお越しくださいね

らくたびご一行様は、「 妖怪ストリート 」と呼ばれる一条通を東へと進みます!
こんな妖怪や、

あんな妖怪が次々に登場します。

妖怪を見てワイワイ
 と言いながら、大将軍八神社へ到着!
と言いながら、大将軍八神社へ到着!大将軍八神社( だいしょうぐんはちじんじゃ )
桓武天皇が平安遷都の際、王城鎮護( 西の方位を守護するため )に
創建された神社です。この神社には素盞鳴尊( スサノオノミコト ) と
その御子( ミコ )八神、暦神八神、そして聖武天皇、桓武天皇と
多くの神様が祀られる ありがた〜い神社です。
方徳殿( 宝物殿 )では貴重なご神像 80体を拝見することができます。

そしていよいよこの後、北野天満宮へ。
まずは天神市で賑わう境内の側にある東向観音寺( ひがしむきかんのんじ )をご参拝。
神仏習合時代の創建で、明治になり神仏分離令がなされた後も神社の
境内の中にお寺がるあるという神宮寺( じんぐうじ )として現存するのは
この東向観音寺のみだとか。
ご本尊は菅原道真自作という十一面観音菩薩です。
( 洛陽三十三所観音霊場の第三十一番札所 )

こちらの境内には、京都学ではかかせない京都三珍鳥居のひとつ
伴氏社にお祀りされている道真公のお母様のお墓があります。

そしてこちらは、土蜘蛛塚と呼ばれる石灯籠。京の町には怨霊めいた
伝承がたくさんあり、その中のひとつがこの土蜘蛛塚です。

平安時代の武将・源頼光が熱病にかかったが、
夜中に目覚めると枕元に怪しい僧の姿が・・・。
斬りつけた血の跡を四天王が追うと巨大な土蜘蛛が!
これを退治し河原に晒すと、頼光の熱病が治ったという。
このようなコ〜ワいお話が残る『 塚 』は、強いパワーがあるので興味本位で
写真を撮らないようにしましょう

さあ、最後は天満宮さんのご参拝です!
この日は、京都に春の訪れを告げる北野天満宮の梅花祭が
行われていたことから、境内はとっても賑わっていました。

楼門には、あまりにも有名な道真公の歌が詠まれていました。

みなさんが見上げておられるのは・・・そう! 三光門です。
豊富な彫刻の中にある【 日・月・星 】を探しておられるんですね〜。
みなさん、楽しそう〜


境内には約1500本という梅があり、この日は 3分咲きほどでした。
それでも梅の花の芳しい甘〜い香りが立ちこめ、もうすぐそこまで
春がやってきているなぁ
 、と感じることができました。
、と感じることができました。
参加者の皆さま、ほんとうにお疲れ様でした!
北野天満宮・梅宮大社・御苑、城南宮に、隨心院と。
京都の梅の見頃はまだまだこれからです!
お気に入りの梅の名所を訪れてみてくださいね

ご案内 : らくたび代表 山村 純也
写真 : らくたび会員 五島 千恵様
文&写真 : らくたびレポーター 奥村
2011年12月12日
12月8日(木)北野天満宮・もみじ苑と千本釈迦堂・大根焚き

12月8日(木)の京都さんぽは、今秋のフィナーレを飾る紅葉狩りと
京の冬の風物詩・大根焚きを訪れました。
冷たい小雨が降る中、嵐電・北野白梅町を出発。
最初に向かったのは、
≪平野神社≫
もともとは奈良の都にあったのですが、平安京遷都とともに
お引っ越しをされたという由緒あるお社。
春は400本、50品種の桜が咲く京都随一の桜の名所です。
御神木からパワーをいただき、また寒桜や見事な小金色に色づいた
イチョウ、橘の実・・・など秋ならではの平野神社に出会うことができました。
続いては・・・
≪北野天満宮≫
すでにお正月の準備が進められていました。
こちらは学問の神様・菅原道真をお祀りしているので、もちろん皆さんで、
「学問成就」を祈願しました(笑)
また、この北野天満宮には豊臣秀吉が、鴨川の氾濫と東からの
侵略に備えて築いた土塁「御土居(おどい)」が残っており、
その周辺は「もみじ苑」として近年人気の紅葉スポットとなっています。
舞台から見ると、紅葉一色!!
本殿を角度を変えて、紅葉とともに見ることもできます。
階段を下りると「御土居」がよく見えます。
この日の御土居は「散り紅葉御土居」でした(笑)
「御土居って聞いたことはあったけど、見たのは初めて!」
「こんな土塁が22.5㎞も続いていたんですか!」
「洛中洛外の区切りがわかった」
皆さん、御土居を楽しまれたご様子。
しっとりと雨に濡れた紅葉が一層輝いていました。
このもみじ苑の入苑料には、お茶とお菓子が付いていて、ちょっと一服。
嬉しいですね。
秋のフィナーレを見事に飾ったあとは、冬の風物詩へ!
≪千本釈迦堂≫
大根焚きは鎌倉時代、慈禅上人が大根の切り口に梵字を書いて、魔よけとして
人びとにふるまったことに始まる伝統行事。毎年12月7日、8日の2日間
行われ、1万人が訪れるそう。
5000本の大根が大きなお鍋で焚かれます。
私たちはラッキーなことに、国宝に指定されている本堂内でいただくことが
できました。
ホッカホカの大根を、ふぅーふぅーとさましながら、いただきます。
じっくりと焚きこまれていて、おいしい~♪

「無病息災」のご利益があるということですが、食べ終わった後には
早くも身体がポカポカしてきました。これで冬も元気に過ごせそうです。
おかめさんも参拝者の様子を笑顔で見守っておられました。
小雨の降る中の散策となりましたが、皆さん、ワイワイと賑やかに
楽しく散策することができました。
さて、いよいよ、京都に本格的な冬が到来!
寒さに負けずに、冬も京都を楽しみましょうね~♪
ご案内・文・写真/らくたび 森
受付・添乗/富田
2009年08月29日
西陣の町家文化財 冨田屋で過ごす夏の茶話会

国の登録有形文化財の指定を受けた町家冨田屋さんを訪ね、
夏のしつらえ等についてお話を聞いた後、お抹茶をいただく
と言うのが本日の主要な内容です。
集合場所の西陣織会館へバスで向かっていると、心配していたとおり
雨が本降りになって来ました。どうやら夕立のようです。
もう少し余裕を見て西陣織会館に到着していれば、
内部の見学も出来たのですが、今回は残念ながら諦めることにしました。
夏のしつらえ等についてお話を聞いた後、お抹茶をいただく
と言うのが本日の主要な内容です。
集合場所の西陣織会館へバスで向かっていると、心配していたとおり
雨が本降りになって来ました。どうやら夕立のようです。
もう少し余裕を見て西陣織会館に到着していれば、
内部の見学も出来たのですが、今回は残念ながら諦めることにしました。

西陣 は、応仁の乱で山名宗全が率いた西軍の本陣跡地に広がった
絹織物の産地です。
また、ここには、 村雲御所跡 の碑が立てられています。
これは、豊臣秀次の生母・瑞龍院日秀尼が秀次の菩提を弔うため、
村雲の地に創建されたお寺ですが、堀川通の拡張工事が始まる昭和37年、
滋賀県近江八幡に移築されました。
西陣の中心をなす今出川大宮は古く 「千両ヶ辻」 と呼ばれ、
1日に千両に値する生糸が動いたといわれるほど賑わったそうです。
ここから堀川通を少し下ルと安倍晴明を祭神とする 晴明神社 があります。
境内には、晴明の念力で湧き出て、飲むと悪病難病が治ると伝えられている
晴明井があります。最近の占いブームの影響か若い女性の姿が
多く見受けられます。また最近では特に修学旅行生に大人気の
スポットのひとつだそうです。
今日の散歩の安全を祈願して、さあ出発です。
絹織物の産地です。
また、ここには、 村雲御所跡 の碑が立てられています。
これは、豊臣秀次の生母・瑞龍院日秀尼が秀次の菩提を弔うため、
村雲の地に創建されたお寺ですが、堀川通の拡張工事が始まる昭和37年、
滋賀県近江八幡に移築されました。
西陣の中心をなす今出川大宮は古く 「千両ヶ辻」 と呼ばれ、
1日に千両に値する生糸が動いたといわれるほど賑わったそうです。
ここから堀川通を少し下ルと安倍晴明を祭神とする 晴明神社 があります。
境内には、晴明の念力で湧き出て、飲むと悪病難病が治ると伝えられている
晴明井があります。最近の占いブームの影響か若い女性の姿が
多く見受けられます。また最近では特に修学旅行生に大人気の
スポットのひとつだそうです。
今日の散歩の安全を祈願して、さあ出発です。

晴明神社を出て、西の方角に進むと数分で 冨田屋 さんに到着します。
冨田屋さんは、元々伏見で両替商を営んでいました。
その後西陣産地問屋システムを立ち上げ、明治18年に
現在の商家を建てられたそうです。
玄関の外観は見るからに「京の町家」という雰囲気です。
らくたび会員の安達さんにお迎えをいただき、早速案内していただきました。
この建物は、1999年に国登録有形文化財指定、
2007年に京都市景観重要建造物に指定というすごいものです。
我々素人にもそのすごさが伝わってきます。
冨田屋さんは、元々伏見で両替商を営んでいました。
その後西陣産地問屋システムを立ち上げ、明治18年に
現在の商家を建てられたそうです。
玄関の外観は見るからに「京の町家」という雰囲気です。
らくたび会員の安達さんにお迎えをいただき、早速案内していただきました。
この建物は、1999年に国登録有形文化財指定、
2007年に京都市景観重要建造物に指定というすごいものです。
我々素人にもそのすごさが伝わってきます。

座敷に案内していただくと、「アンティーク着物展」が開催されており、
冨田屋さん代々のお嬢様や奥様の着物が展示されていました。
中には今ではもう再現不可能なものもあるとか。
大変貴重なものを拝見することが出来ました。
離れ座敷に通じる廊下には、切れ目のない約10mの赤松の廊下があり、
歴史と重厚さを感じさせられます。離れ座敷に通されると、
ふすまは「すだれ」に、畳には「あじろ」が引かれ、
見た目にも夏の雰囲気が伝わって涼しく感じられます。
昭和10年に増築された離れのうち、とくに茶室は
武者小路千家官休庵九代家元・千宗守氏より
「楽寿」の名を頂いたそうです。
冨田屋さん代々のお嬢様や奥様の着物が展示されていました。
中には今ではもう再現不可能なものもあるとか。
大変貴重なものを拝見することが出来ました。
離れ座敷に通じる廊下には、切れ目のない約10mの赤松の廊下があり、
歴史と重厚さを感じさせられます。離れ座敷に通されると、
ふすまは「すだれ」に、畳には「あじろ」が引かれ、
見た目にも夏の雰囲気が伝わって涼しく感じられます。
昭和10年に増築された離れのうち、とくに茶室は
武者小路千家官休庵九代家元・千宗守氏より
「楽寿」の名を頂いたそうです。

今まで抹茶を頂く機会はあっても、このように本格的な茶室での経験は
全く初めてのことで、不安と興味津々の入り混じった心境です。
高さ・幅が60cm少しの小さな出入口であるにじりぐちから茶室に入ります。
正座をして一礼、そのまま、両拳をついて膝で進むような動作で
体を滑らせて茶室に入ります。
まさに「にじって入る」そのもので、普段テレビなどでよく見る光景です。
これは、地位・身分の高い人にも頭を下げさせる、という目的で
作られたもので、武士は刀を差したままでは
入りにくくなっているのだそうです。
今回、最も心配していた正座については、安達さんからの
「足を崩してどうぞ!!」の一言にホッと胸を撫で下ろしました。
お茶を頂く前にお菓子が出されます。感動したのは、
菓子鉢から懐紙に菓子を移すお箸の作法です。安達さんから、
懇切丁寧にお箸の持ち方、使い方について教えていただきました。
毎日使っているお箸ですが、その使い方によって、
物凄く上品に且つ無駄の無い仕草があることを気づかせていただきました。
食物を豪快に口に運ぶのも悪くはないでしょうが、
こういう仕草、所作も大切だなあと反省させられました。
安達さん、お箸に限らずこのようなマナーなど改めて教えてくださいね。
全く初めてのことで、不安と興味津々の入り混じった心境です。
高さ・幅が60cm少しの小さな出入口であるにじりぐちから茶室に入ります。
正座をして一礼、そのまま、両拳をついて膝で進むような動作で
体を滑らせて茶室に入ります。
まさに「にじって入る」そのもので、普段テレビなどでよく見る光景です。
これは、地位・身分の高い人にも頭を下げさせる、という目的で
作られたもので、武士は刀を差したままでは
入りにくくなっているのだそうです。
今回、最も心配していた正座については、安達さんからの
「足を崩してどうぞ!!」の一言にホッと胸を撫で下ろしました。
お茶を頂く前にお菓子が出されます。感動したのは、
菓子鉢から懐紙に菓子を移すお箸の作法です。安達さんから、
懇切丁寧にお箸の持ち方、使い方について教えていただきました。
毎日使っているお箸ですが、その使い方によって、
物凄く上品に且つ無駄の無い仕草があることを気づかせていただきました。
食物を豪快に口に運ぶのも悪くはないでしょうが、
こういう仕草、所作も大切だなあと反省させられました。
安達さん、お箸に限らずこのようなマナーなど改めて教えてくださいね。

冨田屋さんを後にして、堀川通を渡り現在の一条戻り橋を東に進みます。
油小路通を下ルと楽家家元・楽美術館があります。
楽焼は、千利休の指導の元で、聚楽第建造の土を使って焼いたもので、
豊臣秀吉から聚楽第の一文字「楽」を印章に賜ったことが
始まりとされる説が広く知られています。
楽焼は、あの柔らかい釉薬の手触りにホッとした温もりを感じることが出来、
大好きな焼物のひとつです。
油小路通を下ルと楽家家元・楽美術館があります。
楽焼は、千利休の指導の元で、聚楽第建造の土を使って焼いたもので、
豊臣秀吉から聚楽第の一文字「楽」を印章に賜ったことが
始まりとされる説が広く知られています。
楽焼は、あの柔らかい釉薬の手触りにホッとした温もりを感じることが出来、
大好きな焼物のひとつです。

雨のぱらつく蒸し暑い日でありましたが、ご参加の皆さん、安達さん、
らくたびスタッフの皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。
らくたびスタッフの皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。
文・写真/らくたび会員 鴨田一美様
2009年04月12日
京都三奇祭やすらい祭見学と西陣の隠れ桜めぐり

咲き誇る京都の桜が見頃を迎えたこの日、京都さんぽが開催されました。
今回は京都三奇祭のひとつやすらい祭と西陣の桜散策がメインです。
北大路通りに面した大徳寺南門に集合した一行は
さっそくやすらい祭が行われている 玄武神社 へと向かいます。
今回は京都三奇祭のひとつやすらい祭と西陣の桜散策がメインです。
北大路通りに面した大徳寺南門に集合した一行は
さっそくやすらい祭が行われている 玄武神社 へと向かいます。

やすらい祭は今宮神社が有名ですが今回訪れた玄武神社、川上大神宮でも
実施されています。平安時代、花の散る頃になると疫病が流行り
人々を苦しめました。飛散する花とともに疫病が流行ると信じた人々が
疫病を鎮め無病息災を祈願したことに始まったのがやすらい祭です。
境内には無病息災のご利益があるとされる 風流傘 がありました。
やすらい踊りが始まる前にちゃんと入ってきましたよ。
これで病気になることはないでしょう。
実施されています。平安時代、花の散る頃になると疫病が流行り
人々を苦しめました。飛散する花とともに疫病が流行ると信じた人々が
疫病を鎮め無病息災を祈願したことに始まったのがやすらい祭です。
境内には無病息災のご利益があるとされる 風流傘 がありました。
やすらい踊りが始まる前にちゃんと入ってきましたよ。
これで病気になることはないでしょう。

やすらい祭を見学後はいよいよ西陣の桜散策へと向かいます。
最初に立ち寄ったのが 水火天満宮 です。境内にある2本の紅枝垂れ桜が
満開でした。観光客は少なめなのでゆっくりと眺めることができます。
さらに境内には登天石と呼ばれている石があります。
非業の死を遂げた菅原道真ゆかりの石で、道真の死後都で起こる雷雨を
鎮めるために師である法正坊尊意僧正が宮中に向かう途中、
鴨川が急に溢れ出し数珠をひと揉みすると川が2つに分かれ
この石が現れたそうです。石の上には道真がいて、やがて天に
登っていったそうです。その後は雷雨がおさまり、僧正が持ち帰り
供養して 「登天石」 と名付けられました。
最初に立ち寄ったのが 水火天満宮 です。境内にある2本の紅枝垂れ桜が
満開でした。観光客は少なめなのでゆっくりと眺めることができます。
さらに境内には登天石と呼ばれている石があります。
非業の死を遂げた菅原道真ゆかりの石で、道真の死後都で起こる雷雨を
鎮めるために師である法正坊尊意僧正が宮中に向かう途中、
鴨川が急に溢れ出し数珠をひと揉みすると川が2つに分かれ
この石が現れたそうです。石の上には道真がいて、やがて天に
登っていったそうです。その後は雷雨がおさまり、僧正が持ち帰り
供養して 「登天石」 と名付けられました。

続いては日蓮宗の寺院である 妙覚寺 と 妙顕寺 です。
妙覚寺にも見事な紅枝垂れ桜があります。時より吹く風で桜が散っていくのが
とても風情がありますね……
妙覚寺の山門は聚楽第の裏門を移築したといわれており、
梁の上には兵を伏せておく空間があるのが特徴です。
妙顕寺は京都で初めて建立された寺院で関西法華宗の根本をなす寺院です。
この妙顕寺の満開の桜をバックに参加者全員で記念撮影です!!
妙覚寺にも見事な紅枝垂れ桜があります。時より吹く風で桜が散っていくのが
とても風情がありますね……
妙覚寺の山門は聚楽第の裏門を移築したといわれており、
梁の上には兵を伏せておく空間があるのが特徴です。
妙顕寺は京都で初めて建立された寺院で関西法華宗の根本をなす寺院です。
この妙顕寺の満開の桜をバックに参加者全員で記念撮影です!!

次なる目的地の雨宝院へ向かう途中小川通りにある茶道の家元、
表千家・裏千家 に立ち寄ります。
立ち寄るといっても中へ入ることは勿論できません。
山村さんの説明によれば表千家の裏にあるため裏千家と名付けられたとか。
さらに、裏千家の茶室今日庵は宗旦が清巌和尚という人物の
「懈怠比丘不期明日」(懈怠の比丘明日を期せず)の意に感じて命名したそうです。
長谷川等伯ゆかり本法寺を通り抜け雨宝院を目指します。
表千家・裏千家 に立ち寄ります。
立ち寄るといっても中へ入ることは勿論できません。
山村さんの説明によれば表千家の裏にあるため裏千家と名付けられたとか。
さらに、裏千家の茶室今日庵は宗旦が清巌和尚という人物の
「懈怠比丘不期明日」(懈怠の比丘明日を期せず)の意に感じて命名したそうです。
長谷川等伯ゆかり本法寺を通り抜け雨宝院を目指します。

雨宝院 の本尊は大聖歓喜天で、別名を西陣聖天とも呼ばれ
親しまれています。さらに本堂前にある桜は歓喜桜と呼ばれており、
御室桜と同じ種類で八重桜です。開花時には御室桜同様根元から花をつけます。
親しまれています。さらに本堂前にある桜は歓喜桜と呼ばれており、
御室桜と同じ種類で八重桜です。開花時には御室桜同様根元から花をつけます。

最終目的地の 平野神社 に到着です。
平野神社は言わずと知れた京都随一の桜の名所です。
境内には50種類、400本もの桜があり比較的長い期間桜を楽しむことができます。
16時過ぎに平野神社に到着しましたが、この時間でも多くの花見客で
賑わっていましたね。
本日の京都さんぽは平野神社で解散です。解散後、参加者の皆様は
カメラ片手に賑やかな境内を楽しまれていました。
晴天(汗ばむ程の陽気……)に恵まれた今回の京都さんぽ。
非常に満足できた桜散策となりました。
平野神社は言わずと知れた京都随一の桜の名所です。
境内には50種類、400本もの桜があり比較的長い期間桜を楽しむことができます。
16時過ぎに平野神社に到着しましたが、この時間でも多くの花見客で
賑わっていましたね。
本日の京都さんぽは平野神社で解散です。解散後、参加者の皆様は
カメラ片手に賑やかな境内を楽しまれていました。
晴天(汗ばむ程の陽気……)に恵まれた今回の京都さんぽ。
非常に満足できた桜散策となりました。
文/らくたび会員 森田和宏様 写真/らくたび会員 奥村成美様
2009年01月12日
冨田屋の白みそ雑煮と北野天満宮新春初詣
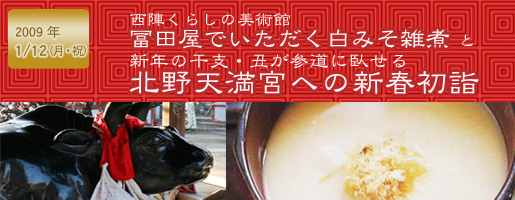
今日はお正月の松の内ということもあり、おせち料理と白みそ雑煮をいただく
という季節感たっぷりの京都さんぽです。
そんなテーマだったので、綺麗な「おべべ(着物)」姿の方も
多く参加されてました。
京都のお正月らしく華やかなご一行さんでのスタートとなりました(笑)
という季節感たっぷりの京都さんぽです。
そんなテーマだったので、綺麗な「おべべ(着物)」姿の方も
多く参加されてました。
京都のお正月らしく華やかなご一行さんでのスタートとなりました(笑)

今出川駅を出発し、武者小路通りを西へと進みます。
この辺りは史跡や石碑が多く立ち並んでいるエリアです。
まずは、三千家のひとつ武者小路千家の由緒あるお茶室 官休庵 に到着。
もちろん中に入ることはできませんので、記念撮影のみとなりました。
そして、民家の路地を通り抜けて行きます。
この路地を 狩野図子 といいます。文字通り狩野派の絵師が
代々邸宅としてきたお屋敷があった場所なんです。
今でも 狩野元信邸宅跡 の石碑が立っています。
なんでもない路地にも名称があるところが、さすが京都です。
この辺りは史跡や石碑が多く立ち並んでいるエリアです。
まずは、三千家のひとつ武者小路千家の由緒あるお茶室 官休庵 に到着。
もちろん中に入ることはできませんので、記念撮影のみとなりました。
そして、民家の路地を通り抜けて行きます。
この路地を 狩野図子 といいます。文字通り狩野派の絵師が
代々邸宅としてきたお屋敷があった場所なんです。
今でも 狩野元信邸宅跡 の石碑が立っています。
なんでもない路地にも名称があるところが、さすが京都です。

一行は今出川通りに出て 白峯神宮 に到着しました。境内にある地主社に祀られている
精大明神は蹴鞠の神様とされています。
「蹴鞠の碑」という石碑があり、球技上達の「撫で鞠」として有名で
多くの方がこの鞠を撫でるために参拝します。
今では球技全般・スポーツの神様として厚く信仰されています。
次に堀川通りを渡り、 晴明神社 に向かいます。平安時代の大陰陽師・
安倍晴明を祭神とした神社で、この辺りの氏神さんでもあります。
参拝をすませて、さあ!冨田屋さんまではもう少しです。
精大明神は蹴鞠の神様とされています。
「蹴鞠の碑」という石碑があり、球技上達の「撫で鞠」として有名で
多くの方がこの鞠を撫でるために参拝します。
今では球技全般・スポーツの神様として厚く信仰されています。
次に堀川通りを渡り、 晴明神社 に向かいます。平安時代の大陰陽師・
安倍晴明を祭神とした神社で、この辺りの氏神さんでもあります。
参拝をすませて、さあ!冨田屋さんまではもう少しです。

大宮通りを北へ向かうと、西陣くらしの美術館・ 冨田屋 さんの建物が見えてきました。
広く延びる壁からその建物の大きさが伺えます。
立派な染め暖簾をくぐると、お正月の赤と白の餅花が出迎えてくれました。
ここから京町家の正月の始まりです。
まず上がらせていただいたお部屋には、立派な屏風が飾られています。
これは、お正月のみ飾られるという土佐光起の作品だとか・・・・・・すごい!
奥の間の床の間には、お正月の掛け軸と、鏡餅が供えられています。
本来1月11日が鏡開きですが、日延べして私たちをお迎えくださいました。
こちらには今は珍しくなった年神さんである歳徳神(としとくじん)
という神様をお祀りします。
組み立て式の特別な神棚を部屋の天井からぶらさげ、そこに神様をお迎えします。
この神棚は360度回転式で、歳徳神さんがおみえになる恵方に向かって
お参りできるようにくるりと回すことができるそうです。
今年の恵方は東北東なのでその方向に回してあります。
節分までこのままお祀りして、節分が終わるとバラバラに解体し、
大切にお蔵に片付けるそうです。
広く延びる壁からその建物の大きさが伺えます。
立派な染め暖簾をくぐると、お正月の赤と白の餅花が出迎えてくれました。
ここから京町家の正月の始まりです。
まず上がらせていただいたお部屋には、立派な屏風が飾られています。
これは、お正月のみ飾られるという土佐光起の作品だとか・・・・・・すごい!
奥の間の床の間には、お正月の掛け軸と、鏡餅が供えられています。
本来1月11日が鏡開きですが、日延べして私たちをお迎えくださいました。
こちらには今は珍しくなった年神さんである歳徳神(としとくじん)
という神様をお祀りします。
組み立て式の特別な神棚を部屋の天井からぶらさげ、そこに神様をお迎えします。
この神棚は360度回転式で、歳徳神さんがおみえになる恵方に向かって
お参りできるようにくるりと回すことができるそうです。
今年の恵方は東北東なのでその方向に回してあります。
節分までこのままお祀りして、節分が終わるとバラバラに解体し、
大切にお蔵に片付けるそうです。

そして冨田屋13代目・田中峰子さんのお話が始まりました。
西陣の古くから伝わる町家での1年の過ごし方、習わし、
大切にしたい決まり事を1年を通してお話いただきました。
師走から始まり、正月のしつらい・七草粥・小豆粥、2月の節分。
3月には雛祭り。冨田屋さんには代々の100体以上のお雛さんがあり、
それがずらーっと並ぶそうです。
その雛祭りの時には、ひちぎり餅 をいただきます。
春、4月になると平野神社でお花見を。
5月には大将さんを飾り端午の節句。
6月になると夏越の祓い。
7月の七夕さんは、西陣という地ならではで 「織り姫さん」にちなみ
笹飾りも盛大に。
そして、夏、千本閻魔堂でお精霊迎えをし、大文字の送り火。
子供達のお楽しみ地蔵盆。
9月になると1年で最も大切な節句・重陽の節句。
いのこもち をいただき、お火焚きさんで手紙を焼く。
そして、また師走がやってくる。
なんだか聞いていると風情がありとても贅沢な1年の過ごし方
と思いますが、昔の人はこのような時間をあたり前のように
過ごしていたんでしょうね。
今の時代に生きる私たちの方が余程贅沢なはずなのに、
なんとも羨ましく感じました。
西陣の古くから伝わる町家での1年の過ごし方、習わし、
大切にしたい決まり事を1年を通してお話いただきました。
師走から始まり、正月のしつらい・七草粥・小豆粥、2月の節分。
3月には雛祭り。冨田屋さんには代々の100体以上のお雛さんがあり、
それがずらーっと並ぶそうです。
その雛祭りの時には、ひちぎり餅 をいただきます。
春、4月になると平野神社でお花見を。
5月には大将さんを飾り端午の節句。
6月になると夏越の祓い。
7月の七夕さんは、西陣という地ならではで 「織り姫さん」にちなみ
笹飾りも盛大に。
そして、夏、千本閻魔堂でお精霊迎えをし、大文字の送り火。
子供達のお楽しみ地蔵盆。
9月になると1年で最も大切な節句・重陽の節句。
いのこもち をいただき、お火焚きさんで手紙を焼く。
そして、また師走がやってくる。
なんだか聞いていると風情がありとても贅沢な1年の過ごし方
と思いますが、昔の人はこのような時間をあたり前のように
過ごしていたんでしょうね。
今の時代に生きる私たちの方が余程贅沢なはずなのに、
なんとも羨ましく感じました。

いよいよ奥座敷に通していただき、お待ちかねのおせち料理と白みそ雑煮です!
おせち料理は、黒豆・たたきごぼう・千枚漬けの3種です。
京都のお雑煮、白味噌のあまいお雑煮です。
大根の白梅と、金時人参の紅梅が可愛らしい。
白味噌の中には、今朝つきたての白い丸餅が入っています。
いつも家で食べる慣れ親しんだ白みそ雑煮ですが、
このお雑煮は格別に美味しかったです。
おせち料理は、黒豆・たたきごぼう・千枚漬けの3種です。
京都のお雑煮、白味噌のあまいお雑煮です。
大根の白梅と、金時人参の紅梅が可愛らしい。
白味噌の中には、今朝つきたての白い丸餅が入っています。
いつも家で食べる慣れ親しんだ白みそ雑煮ですが、
このお雑煮は格別に美味しかったです。

心も身体も温まり、 北野天満宮 に向かいました。
まだお正月飾りが残る上七軒を通り境内へ。ここでは「北野天満宮七不思議」を
丁寧に説明していただきました。やはりひとつひとつ目にしながら
説明していただくと、とてもわかり易いですね。
最後に若村先生ならでは説明をひとつ・・・・・・絵馬所にある「誠」の字。
こちらに掲げられた額の文字を近藤勇が見て、ご存知、新撰組の「誠」の
旗を作ったとか! 一同、へぇ~!!!と大興奮でした(笑)
北野天満宮に行かれることがあれば、絵馬所で「誠」の額を
探してみてくださいね。ヒントは、西の端です。
今日はこのような伝統的なお正月を体験させていただき、
ありがとうございました!京都の冬らしいとても寒い1日でしたが、
天神さんの境内の梅もちらほら咲いており、
少しずつ春はやってきています。春のさんぽも楽しみですね。
まだお正月飾りが残る上七軒を通り境内へ。ここでは「北野天満宮七不思議」を
丁寧に説明していただきました。やはりひとつひとつ目にしながら
説明していただくと、とてもわかり易いですね。
最後に若村先生ならでは説明をひとつ・・・・・・絵馬所にある「誠」の字。
こちらに掲げられた額の文字を近藤勇が見て、ご存知、新撰組の「誠」の
旗を作ったとか! 一同、へぇ~!!!と大興奮でした(笑)
北野天満宮に行かれることがあれば、絵馬所で「誠」の額を
探してみてくださいね。ヒントは、西の端です。
今日はこのような伝統的なお正月を体験させていただき、
ありがとうございました!京都の冬らしいとても寒い1日でしたが、
天神さんの境内の梅もちらほら咲いており、
少しずつ春はやってきています。春のさんぽも楽しみですね。
文/らくたび会員 奥村成美様 写真/らくたび会員 鴨田一美様
2008年12月07日
千本釈迦堂大根焚きと応仁の乱の痕跡を求めて

今回の京都さんぽは 応仁の乱 にスポットを当てての散策です。
まず初めに訪れたのは 上御霊神社 です。
まず初めに訪れたのは 上御霊神社 です。

境内はかつて御霊杜とも呼ばれ、応仁の乱の戦端が開かれたところ
として知られています。そもそも応仁の乱は室町幕府の後継者問題に
端を発しています。そこへ畠山氏の家督問題が重なり全国の守護大名が
東軍・西軍に分かれて戦火が拡大していきました。
として知られています。そもそも応仁の乱は室町幕府の後継者問題に
端を発しています。そこへ畠山氏の家督問題が重なり全国の守護大名が
東軍・西軍に分かれて戦火が拡大していきました。

一行は上御霊神社を後にして寺ノ内通りを西へ歩きます。
次なる目的地 妙顕寺 へ到着です。妙顕寺は法華宗の寺院です。
京都で初めて建立された寺院で関西法華宗の根本をなす寺院とのこと。
尾形光琳・乾山兄弟がこの寺の信徒で境内には2人のお墓もあります。
さらに西へ進み 百々橋跡 へ。
こちらも応仁の乱の激戦が繰り広げられた場所です。
現在橋は解体され下を流れる小川も埋め立てられており
礎石が一基あるだけです。
次なる目的地 妙顕寺 へ到着です。妙顕寺は法華宗の寺院です。
京都で初めて建立された寺院で関西法華宗の根本をなす寺院とのこと。
尾形光琳・乾山兄弟がこの寺の信徒で境内には2人のお墓もあります。
さらに西へ進み 百々橋跡 へ。
こちらも応仁の乱の激戦が繰り広げられた場所です。
現在橋は解体され下を流れる小川も埋め立てられており
礎石が一基あるだけです。

堀川通りを渡り 山名宗全邸跡 をチェックです。
西軍総大将の邸宅跡ですが今は石碑があるだけでとても寂しい感じがします。
訪れる人はまずいないでしょうね。
西軍総大将の邸宅跡ですが今は石碑があるだけでとても寂しい感じがします。
訪れる人はまずいないでしょうね。

千本釈迦堂の前に三上路地にある蜂蜜専門店 dorato (ドラート)
へちょっと寄り道です。若村さんのブログでも紹介されていましたね。
店内には50種類を超える蜂蜜が並んでいます。
試食をさせていただけるので自分のお気に入りの蜂蜜を
見つけることができます。皆さん思い思いの蜂蜜を選んでいました。
いよいよ次は 千本釈迦堂(大報恩寺) へ向かいます。
この日は冬の風物詩である大根焚きが行われています。
へちょっと寄り道です。若村さんのブログでも紹介されていましたね。
店内には50種類を超える蜂蜜が並んでいます。
試食をさせていただけるので自分のお気に入りの蜂蜜を
見つけることができます。皆さん思い思いの蜂蜜を選んでいました。
いよいよ次は 千本釈迦堂(大報恩寺) へ向かいます。
この日は冬の風物詩である大根焚きが行われています。

境内はすでに大勢の人で賑わっていました。
この大報恩寺の本堂は山名宗全が必至で守り抜いたと言われており、
市街地最古の木造建築物として有名です。仏像彫刻も優品が揃っていますし、
おかめ像もあり、非常に見応えのある寺院ではないでしょうか。
引換券を購入し参加者全員で大根焚きをいただきました。
少し大きめの輪切りにされた大根が3つと揚げが入っています。
寒かったせいもあるでしょう。非常に美味しくいただきました。
この大報恩寺の本堂は山名宗全が必至で守り抜いたと言われており、
市街地最古の木造建築物として有名です。仏像彫刻も優品が揃っていますし、
おかめ像もあり、非常に見応えのある寺院ではないでしょうか。
引換券を購入し参加者全員で大根焚きをいただきました。
少し大きめの輪切りにされた大根が3つと揚げが入っています。
寒かったせいもあるでしょう。非常に美味しくいただきました。

暖まったところで次は千本通りを北上し最終目的地船岡山へ向かいます。
途中、千本閻魔堂、上品蓮台寺へ。
千本閻魔堂は引接寺が正式名称で御本尊は閻魔法王様です。
こちらの本堂にはえんまさんのお湯呑碗と呼ばれる湯呑が
お賽銭箱の上に設置されています。
湯呑に見事お賽銭が入れば倍になってかえってくるとか・・・・・・
上品蓮台寺は十二坊とも呼ばれています。
応仁の乱で焼失後再興した際に十二の子院があったことから
十二坊の名前が付けられました。
寺宝としては天平時代の作として貴重な絵因果経を有しています。
途中、千本閻魔堂、上品蓮台寺へ。
千本閻魔堂は引接寺が正式名称で御本尊は閻魔法王様です。
こちらの本堂にはえんまさんのお湯呑碗と呼ばれる湯呑が
お賽銭箱の上に設置されています。
湯呑に見事お賽銭が入れば倍になってかえってくるとか・・・・・・
上品蓮台寺は十二坊とも呼ばれています。
応仁の乱で焼失後再興した際に十二の子院があったことから
十二坊の名前が付けられました。
寺宝としては天平時代の作として貴重な絵因果経を有しています。

そして船岡山へ到着です。この船岡山には応仁の乱の際
西軍がお城を築いた場所です。
そのお城を巡って船岡山合戦が行われたそうです。
今は当時を偲ぶものはありませんが。
到着したころにはだいぶ太陽が傾いていました。そこで参加者全員で
山頂に登り傾く夕陽を沈むまで見ることに。
ため息がでるくらい綺麗な夕陽でした。
西軍がお城を築いた場所です。
そのお城を巡って船岡山合戦が行われたそうです。
今は当時を偲ぶものはありませんが。
到着したころにはだいぶ太陽が傾いていました。そこで参加者全員で
山頂に登り傾く夕陽を沈むまで見ることに。
ため息がでるくらい綺麗な夕陽でした。
文/らくたび会員 森田和宏様 写真/らくたび会員 鴨田一美様
2008年11月03日
源氏物語と秋の非公開文化財を訪ねて

今年は 『源氏物語』 の存在が『紫式部日記』で確認されてから1000年の
節目の年にあたることから、源氏物語にちなんだ様々な企画が
各地で開催されてきました。
そんな千年紀に沸く源氏物語ゆかりの場所を目指して出発です。
節目の年にあたることから、源氏物語にちなんだ様々な企画が
各地で開催されてきました。
そんな千年紀に沸く源氏物語ゆかりの場所を目指して出発です。

大聖寺、 三時知恩寺 はどちらも皇室ゆかりの女性が入寺された
門跡尼寺です。通常は非公開となっておりますので外からの見学となりました。
外観は大寺院とは異なりとても落ち着いた雰囲気を醸し出していました。
特別に公開される時期もあるとのことですので、チャンスがあれば
ぜひ訪れてみたいものです。
門跡尼寺です。通常は非公開となっておりますので外からの見学となりました。
外観は大寺院とは異なりとても落ち着いた雰囲気を醸し出していました。
特別に公開される時期もあるとのことですので、チャンスがあれば
ぜひ訪れてみたいものです。

報恩寺 の梵鐘は「撞かずの鐘」として京都検定テキストにも
紹介されています。西陣の織子さんと丁稚さんの揉め事から、
鐘を撞かなくなってしまった話です。
登場する人物や内容がとても具体的で、今でもその話がここに
生きている面白さがあります。
このように京都にはあちらこちらに伝説が伝わっていますが、
ハッピーエンドで終わるものだけでなく、ちょっと悲しかったり、
不気味だったりする伝説までもが大切に残されています。
物語好きの京都人の気質なのか、先人の教えを生活に取り入れる
智恵なのか・・・・・・?いずれにしても伝説が町歩きを
一層楽しくさせてくれることは間違いないでしょう。
紹介されています。西陣の織子さんと丁稚さんの揉め事から、
鐘を撞かなくなってしまった話です。
登場する人物や内容がとても具体的で、今でもその話がここに
生きている面白さがあります。
このように京都にはあちらこちらに伝説が伝わっていますが、
ハッピーエンドで終わるものだけでなく、ちょっと悲しかったり、
不気味だったりする伝説までもが大切に残されています。
物語好きの京都人の気質なのか、先人の教えを生活に取り入れる
智恵なのか・・・・・・?いずれにしても伝説が町歩きを
一層楽しくさせてくれることは間違いないでしょう。

小川通 は表千家の不審菴、裏千家の今日庵も並ぶ風情のある通りです。
もともとこの通りには小川が流れていたことから“小川通”となりました。
百々橋の礎石があったり、報恩寺や本法寺の門前には川がないのに
橋が架かっていたりすることから川の存在が確認できます。
私事ですが、以前母とこの道を歩いている時に、小川が流れていた話を
したのですが、「ホンマ?」と信用していない(?)様子でした。
ちゃんと橋を見せれば信用してもらえたのでしょうね。
今度試してみようと思いました。
もともとこの通りには小川が流れていたことから“小川通”となりました。
百々橋の礎石があったり、報恩寺や本法寺の門前には川がないのに
橋が架かっていたりすることから川の存在が確認できます。
私事ですが、以前母とこの道を歩いている時に、小川が流れていた話を
したのですが、「ホンマ?」と信用していない(?)様子でした。
ちゃんと橋を見せれば信用してもらえたのでしょうね。
今度試してみようと思いました。

宝鏡寺 は和宮が幼少期を過ごしたお寺であることから、
NHK大河ドラマ「篤姫」の篤姫紀行でも紹介されていたお寺です。
境内には門前にある和傘屋「日吉屋」さんの傘がきれいに並べられていました。
傘を作成する中で「屋外の広い場所で干す」ということが重要な工程である為、
傘屋さんはお寺の門前に店を構え、境内を借りて日干しをされるそうです。
観光用ではありませんので、いつもいつも出会える光景ではありませんが、
出会えたら“ラッキー”と思えるので、講座で教えていただいてからは
この辺りを歩く時は運試し(?)を兼ねて覗いています。
皆さんもぜひお試し下さい。
NHK大河ドラマ「篤姫」の篤姫紀行でも紹介されていたお寺です。
境内には門前にある和傘屋「日吉屋」さんの傘がきれいに並べられていました。
傘を作成する中で「屋外の広い場所で干す」ということが重要な工程である為、
傘屋さんはお寺の門前に店を構え、境内を借りて日干しをされるそうです。
観光用ではありませんので、いつもいつも出会える光景ではありませんが、
出会えたら“ラッキー”と思えるので、講座で教えていただいてからは
この辺りを歩く時は運試し(?)を兼ねて覗いています。
皆さんもぜひお試し下さい。

慈受院 は秋の特別公開中でしたので、中に入って拝観しました。
藤原鎌足の伝記であり日本最古の絵巻でもある「大織冠絵巻」、
足利義輝がお寺に宛てた手紙、後桜町天皇から下賜された屏風、
狩野探幽の掛け軸などなど、さりげなく置かれていましたが、
素晴らしい寺宝を間近で見ることができました。
藤原鎌足の伝記であり日本最古の絵巻でもある「大織冠絵巻」、
足利義輝がお寺に宛てた手紙、後桜町天皇から下賜された屏風、
狩野探幽の掛け軸などなど、さりげなく置かれていましたが、
素晴らしい寺宝を間近で見ることができました。

本法寺、 水火天満宮 を見た後は、いよいよ本日のテーマにちなんで
紫式部 のお墓参りです。紫式部のお墓は島津製作所さんの一角に
小野篁のお墓と並んで立っています。その並び方から一瞬「恋人同士?」
と思いますが、生きた時代が違いますのでそれはありません。
では、なぜ並んで立っているのかと言いますと、紫式部は
「源氏物語という架空のお話を書いた=嘘をついた=地獄行き」と
なっていたところ、閻魔様に仕えていた小野篁が源氏物語の人気振りを
伝え、地獄行きから逃れたという伝説があるからだそうです。
しかし、当の紫式部もフォローした小野篁も、まさか1000年後までブームが
続き、世界20カ国で翻訳がされるとは想像しなかったでしょうね。
また、このお墓の裏辺りから紫野小学校へ続く道は最近「紫式部通」と
名付けられたそうです。定着するのにもう少し時間がかかりそうですが、
京都の道は正面通や不明門通の様に定着さえすれば
その根拠が無くなっても名前は残ります。今後、紫式部通が
どのように発展していくのかを楽しみにしておきましょう。
紫式部 のお墓参りです。紫式部のお墓は島津製作所さんの一角に
小野篁のお墓と並んで立っています。その並び方から一瞬「恋人同士?」
と思いますが、生きた時代が違いますのでそれはありません。
では、なぜ並んで立っているのかと言いますと、紫式部は
「源氏物語という架空のお話を書いた=嘘をついた=地獄行き」と
なっていたところ、閻魔様に仕えていた小野篁が源氏物語の人気振りを
伝え、地獄行きから逃れたという伝説があるからだそうです。
しかし、当の紫式部もフォローした小野篁も、まさか1000年後までブームが
続き、世界20カ国で翻訳がされるとは想像しなかったでしょうね。
また、このお墓の裏辺りから紫野小学校へ続く道は最近「紫式部通」と
名付けられたそうです。定着するのにもう少し時間がかかりそうですが、
京都の道は正面通や不明門通の様に定着さえすれば
その根拠が無くなっても名前は残ります。今後、紫式部通が
どのように発展していくのかを楽しみにしておきましょう。

玄武神社 、 雲林院 を見学後、最後の目的地である 大徳寺 に到着しました。
大徳寺の住所は「紫野」であり、近くには「紫明通」も通っていることから、
ここら辺りと紫式部も何らかの関係があるのかもしれません。
しかし現在はその事実は明らかになっていません。でもそれはそれで
いいのではないかと私は思います。千年紀の今年、様々な行事が
各地で行われる中、新たな写本が確認されたり、違う解釈が
出てきたりしました。新発見を伝える新聞記事を読んでは、
1000年前と今が繋がることにワクワクしたものです。
(京都検定受験者としては非常に困るのですが)
そんなまだまだ秘められているであろう真実の解明は、50年後、
100年後の未来の人達に楽しんでいただけばいいと思うのです。
大徳寺でこの日の京都さんぽは終了し、
あとは希望者で特別公開をしている塔頭の拝観をしました。
この日のコースは西陣から紫野と狭い範囲ながらも見所いっぱいの
楽しいさんぽとなりました。
今年の源氏物語千年紀を記念して、11月1日は「古典の日」と
制定されたそうです。古典を楽しむことが1年限りの一過性のもの
として終わることなく、今後も少しずつその魅力を深めていければ
・・・・・・と思っています。
参加者の皆様、スタッフの皆様、お疲れ様でした!
大徳寺の住所は「紫野」であり、近くには「紫明通」も通っていることから、
ここら辺りと紫式部も何らかの関係があるのかもしれません。
しかし現在はその事実は明らかになっていません。でもそれはそれで
いいのではないかと私は思います。千年紀の今年、様々な行事が
各地で行われる中、新たな写本が確認されたり、違う解釈が
出てきたりしました。新発見を伝える新聞記事を読んでは、
1000年前と今が繋がることにワクワクしたものです。
(京都検定受験者としては非常に困るのですが)
そんなまだまだ秘められているであろう真実の解明は、50年後、
100年後の未来の人達に楽しんでいただけばいいと思うのです。
大徳寺でこの日の京都さんぽは終了し、
あとは希望者で特別公開をしている塔頭の拝観をしました。
この日のコースは西陣から紫野と狭い範囲ながらも見所いっぱいの
楽しいさんぽとなりました。
今年の源氏物語千年紀を記念して、11月1日は「古典の日」と
制定されたそうです。古典を楽しむことが1年限りの一過性のもの
として終わることなく、今後も少しずつその魅力を深めていければ
・・・・・・と思っています。
参加者の皆様、スタッフの皆様、お疲れ様でした!
文/らくたび会員 森明子様 写真/らくたび会員 鴨田一美様
2008年10月04日
秋祭りの先陣 北野天満宮のずいき祭と北野散策

今回の京都さんぽは、秋の実り五穀豊穣に感謝する天神さんの秋祭り
ずいき祭 の還幸祭をメインに北野方面の散策です。
JR山陰本線円町駅にて集合。今日の参加者は20名ほど。
久しぶりにこぢんまりとしたさんぽです。
ずいき祭 の還幸祭をメインに北野方面の散策です。
JR山陰本線円町駅にて集合。今日の参加者は20名ほど。
久しぶりにこぢんまりとしたさんぽです。

駅から数分歩いたところでの最初の説明は紙屋川(かみやがわ)
です。平安京の西堀川にあたり、洛中洛外を分ける川。
当時はこの川のほとりで朝廷御用達の紙を漉いていたため、一般民衆が
この川を使うことは禁じられていました。
「禁川(きんせん)=天皇が使用される紙のみを漉く川」
この説明を受けていると、早速ずいき祭りの神輿巡行に遭遇!
ずいきをはじめ、たくさんのお野菜や乾物で飾り付けられたお神輿さんを
間近で見られて嬉しかったです!
です。平安京の西堀川にあたり、洛中洛外を分ける川。
当時はこの川のほとりで朝廷御用達の紙を漉いていたため、一般民衆が
この川を使うことは禁じられていました。
「禁川(きんせん)=天皇が使用される紙のみを漉く川」
この説明を受けていると、早速ずいき祭りの神輿巡行に遭遇!
ずいきをはじめ、たくさんのお野菜や乾物で飾り付けられたお神輿さんを
間近で見られて嬉しかったです!

その巡行が通り過ぎてから、 法輪寺(達磨寺) に到着。
起き上がり達磨堂には、諸願成就のために奉納された達磨8000体余が
納められています。お堂の中にずらーっと並んだ達磨と、
天井いっぱいに描かれた達磨天井図に圧倒されました。
この法輪寺は、達磨だけではなく、衆聖堂階上にある金色に輝く
「仏涅槃木像」や、先代のご住職が映画関係の方と親交があったことから
六百有余霊(最近でいうと、石原裕次郎さんや、美空ひばりさん)を祀る
貴寧磨殿(キネマ殿) などが安置されています。
そして本堂南庭も素晴らしい! 紅葉の木が庭の真ん中 に植えられており
これからの季節が楽しみですね。
起き上がり達磨堂には、諸願成就のために奉納された達磨8000体余が
納められています。お堂の中にずらーっと並んだ達磨と、
天井いっぱいに描かれた達磨天井図に圧倒されました。
この法輪寺は、達磨だけではなく、衆聖堂階上にある金色に輝く
「仏涅槃木像」や、先代のご住職が映画関係の方と親交があったことから
六百有余霊(最近でいうと、石原裕次郎さんや、美空ひばりさん)を祀る
貴寧磨殿(キネマ殿) などが安置されています。
そして本堂南庭も素晴らしい! 紅葉の木が庭の真ん中 に植えられており
これからの季節が楽しみですね。

菅原道真の乳母・多治比文子(たじひのあやこ)ゆかりの 文子天満宮 に到着。
多治比文子は、邸宅内に道真を祀る祠(ほこら)を建て、その後、道真の神霊は
北野天満宮に祀られました。このような歴史から、文子天満宮は、
北野天満宮の前身神社 として崇められています。
(京都市内には、何箇所かの文子天満宮があるそうです。)
京都市指定有形文化財に指定されている 奥渓(おくたに)家 へ。
こちらの初代は後水尾天皇の中宮東福門院の御典医を勤め、のちに
仁和寺門跡の御典医をも勤めた医家です。
玄関には「蘇命散」 の看板がかかり、御典医と薬販売の格式を伺わせる
貴重な昔の建物です。
多治比文子は、邸宅内に道真を祀る祠(ほこら)を建て、その後、道真の神霊は
北野天満宮に祀られました。このような歴史から、文子天満宮は、
北野天満宮の前身神社 として崇められています。
(京都市内には、何箇所かの文子天満宮があるそうです。)
京都市指定有形文化財に指定されている 奥渓(おくたに)家 へ。
こちらの初代は後水尾天皇の中宮東福門院の御典医を勤め、のちに
仁和寺門跡の御典医をも勤めた医家です。
玄関には「蘇命散」 の看板がかかり、御典医と薬販売の格式を伺わせる
貴重な昔の建物です。

次に訪れたのは、日蓮宗の本山・ 立本寺 。境内には公園もあり、
なんとものどかなお寺です。お寺の歴史や沿革の説明を伺ってから、
道路ひとつ隔てた墓地へ。
ここには、石田三成の家臣である、島左近のお墓があります。
「三成に過ぎたるものが2つあり。島の左近に佐和山の城」
といわれただけあって、その名と人望は天下に高かった。
関ヶ原合戦での堂々とした戦いっぷりは、敵をも恐れさせた!
戦国時代のお話になると、山村先生の口調はヒートアップします!
臨場感たっぷりです!!
そして、こちらには二代目吉野太夫の夫、豪商・灰屋紹益
(はいやしょうえき)のお墓もあります。
紹益の遺言かどうかはわかりませんが、吉野太夫ゆかりの桜の木の下に
紹益のお墓があるというのが、なんともロマンチックな気がしました。
なんとものどかなお寺です。お寺の歴史や沿革の説明を伺ってから、
道路ひとつ隔てた墓地へ。
ここには、石田三成の家臣である、島左近のお墓があります。
「三成に過ぎたるものが2つあり。島の左近に佐和山の城」
といわれただけあって、その名と人望は天下に高かった。
関ヶ原合戦での堂々とした戦いっぷりは、敵をも恐れさせた!
戦国時代のお話になると、山村先生の口調はヒートアップします!
臨場感たっぷりです!!
そして、こちらには二代目吉野太夫の夫、豪商・灰屋紹益
(はいやしょうえき)のお墓もあります。
紹益の遺言かどうかはわかりませんが、吉野太夫ゆかりの桜の木の下に
紹益のお墓があるというのが、なんともロマンチックな気がしました。

更にさんぽは続き、本門仏立宗・宥清寺、北野名物の長五郎餅本舗、
天皇家ゆかりの清和院を経て、 北野天満宮 に到着。
上七軒界隈をずいき祭り行列が巡行するまで時間があるので、
三光門や本殿・権現造の説明をしていただき、みんなで参拝をしました。
そして、この秋11月1日より公開されるもみじ苑辺りで「御土居」の
説明です。「御土居」は豊臣秀吉によって作られた洛中を囲む土塁で、
ヨーロッパで言うと城壁にあたるものです。
こちらの御土居は、先ほどの紙屋川を利用して高く積み上げられたものです。
昨年このもみじ苑に来ましたが、紅葉が素晴らしく綺麗でした。
天神さんの境内ではありますが、ちょっとした森の中にでも居るような、
自然の風情溢れる紅葉狩りが楽しめます!
天皇家ゆかりの清和院を経て、 北野天満宮 に到着。
上七軒界隈をずいき祭り行列が巡行するまで時間があるので、
三光門や本殿・権現造の説明をしていただき、みんなで参拝をしました。
そして、この秋11月1日より公開されるもみじ苑辺りで「御土居」の
説明です。「御土居」は豊臣秀吉によって作られた洛中を囲む土塁で、
ヨーロッパで言うと城壁にあたるものです。
こちらの御土居は、先ほどの紙屋川を利用して高く積み上げられたものです。
昨年このもみじ苑に来ましたが、紅葉が素晴らしく綺麗でした。
天神さんの境内ではありますが、ちょっとした森の中にでも居るような、
自然の風情溢れる紅葉狩りが楽しめます!

さあ、時間になりました。いよいよお祭りの行列がやってきます!
上七軒辺りに行くと、かなりの人です。
それも大きなカメラを提げたカメラマンがいっぱい!
どうも、行列をお迎えされる舞妓さん、芸妓さんがお目当てらしいです。
すごい熱心ですね~。
4日間に渡るずいき祭のなかでも、この還幸祭は特別の意味を持ちます。
単に「巡行を終えた天神様が本社に御帰りになる」というだけでなく、
「おいでまつり」の別名が示すように
「大宰府で御隠れになった菅原道真公の御霊が神様として
初めて北野の地においでになる」という御鎮座の由来を回顧し、
再現するという意味もあるのです。
氏子区域の人々も、還幸祭の行われる4日には親類縁者を招いて
御馳走を作り、晴れ着をきて、行列に供奉したり、沿道から
御輿を拝んだりしたといいます。
年に一度、御鎮座の往時に思いを致し、御神霊を「お迎えする」
ことで氏神としての天神様を改めて意識し、感謝する心が
育まれるのです。(北野天満宮HPより引用)
上七軒辺りに行くと、かなりの人です。
それも大きなカメラを提げたカメラマンがいっぱい!
どうも、行列をお迎えされる舞妓さん、芸妓さんがお目当てらしいです。
すごい熱心ですね~。
4日間に渡るずいき祭のなかでも、この還幸祭は特別の意味を持ちます。
単に「巡行を終えた天神様が本社に御帰りになる」というだけでなく、
「おいでまつり」の別名が示すように
「大宰府で御隠れになった菅原道真公の御霊が神様として
初めて北野の地においでになる」という御鎮座の由来を回顧し、
再現するという意味もあるのです。
氏子区域の人々も、還幸祭の行われる4日には親類縁者を招いて
御馳走を作り、晴れ着をきて、行列に供奉したり、沿道から
御輿を拝んだりしたといいます。
年に一度、御鎮座の往時に思いを致し、御神霊を「お迎えする」
ことで氏神としての天神様を改めて意識し、感謝する心が
育まれるのです。(北野天満宮HPより引用)

見学するだけの私たちからすれば、行列を見てキレイ~、可愛い~
と簡単に思っているお祭りも、その歴史や謂われをちゃんと知ると、
人々(氏子さん達)の努力の賜物なんですね。
京都の三大祭ばかりが大きく取り上げられていますが、
各町で行われている祭り事は皆同様に、それに従事する人々に
とっては大切なことなんです。
あらゆる京都の行事を拝見する際には、今までとは違う目線で
楽しみたいと思いました。
と簡単に思っているお祭りも、その歴史や謂われをちゃんと知ると、
人々(氏子さん達)の努力の賜物なんですね。
京都の三大祭ばかりが大きく取り上げられていますが、
各町で行われている祭り事は皆同様に、それに従事する人々に
とっては大切なことなんです。
あらゆる京都の行事を拝見する際には、今までとは違う目線で
楽しみたいと思いました。
文/らくたび会員 奥村成美様 写真/らくたび会員 鴨田一美様
2008年09月14日
百鬼夜行ゆかりの一条通と平野神社名月祭

今日9月14日は旧暦の8月15日、そう 中秋の名月 です。
私たちの「京都さんぽ」のゴールの平野神社でも「名月祭」と称して、
雅楽、日本舞踊などが催されます。
平野神社へは、平安京の北端であった一条通り沿いに史跡を見つつ
西へ西へと行く事になります。さあ、烏丸今出川から出発です。
一筋南へ下って右折し、武者小路通へ入っていきます。
私たちの「京都さんぽ」のゴールの平野神社でも「名月祭」と称して、
雅楽、日本舞踊などが催されます。
平野神社へは、平安京の北端であった一条通り沿いに史跡を見つつ
西へ西へと行く事になります。さあ、烏丸今出川から出発です。
一筋南へ下って右折し、武者小路通へ入っていきます。

室町通の交差点に 福長神社 があります。
水の神としての信仰が篤く由緒ある神社だったそうですが、今では
本当にひっそりと忘れられた様な感じがします。
多分町内の方が、大切に維持されているのでしょう。
ちょっと西へ進むと 乾向地蔵尊 です。縁起やご利益は解らないのですが、
乾(いぬい)は北西の方角「戌(いぬ)と亥(い)の間の方角」を表しており、
今の御所から見て北西に有るという事が名前の由来の様です。
同じ様に巽(たつみ)も南東を示すという事です。
わが庵は都の巽しかぞ住む…
という歌も有りましたね。
水の神としての信仰が篤く由緒ある神社だったそうですが、今では
本当にひっそりと忘れられた様な感じがします。
多分町内の方が、大切に維持されているのでしょう。
ちょっと西へ進むと 乾向地蔵尊 です。縁起やご利益は解らないのですが、
乾(いぬい)は北西の方角「戌(いぬ)と亥(い)の間の方角」を表しており、
今の御所から見て北西に有るという事が名前の由来の様です。
同じ様に巽(たつみ)も南東を示すという事です。
わが庵は都の巽しかぞ住む…
という歌も有りましたね。

新町通をちょっと上ルと左手が 霊光殿天満宮 。
社名は、菅原道真が大宰府に左遷された際、天から一条の光とともに
天一神・帝釈天が降臨したとの伝説によるそうです。
元誓願寺通りを西に行くと狩野永徳の祖父の 狩野元信邸跡 の石碑です。
狩野家は代々この屋敷に住んだそうです。
社名は、菅原道真が大宰府に左遷された際、天から一条の光とともに
天一神・帝釈天が降臨したとの伝説によるそうです。
元誓願寺通りを西に行くと狩野永徳の祖父の 狩野元信邸跡 の石碑です。
狩野家は代々この屋敷に住んだそうです。

細い路地を下って、武者小路通りに出ました。通りの名から解るように、
ここには三千家の一つである武者小路千家の 官休庵 があります。
千宗旦の次男宗守が開いた茶室で、宗守は武者小路千家を起こす前は
讃岐高松松平家に茶の指南役として仕えており、「官を休んで庵を開く」
という意味から官休庵と称したそうです(へええ・・・その1)
油小路通りを下り千家十職の一つ茶碗師の樂家と 樂美術館 の前を通り、
前面に裸体のレリーフがある超斬新な 旧京都中央電話局西陣分局舎 を
過ぎて北へ右折し一条通りに戻ってきました。
ここには三千家の一つである武者小路千家の 官休庵 があります。
千宗旦の次男宗守が開いた茶室で、宗守は武者小路千家を起こす前は
讃岐高松松平家に茶の指南役として仕えており、「官を休んで庵を開く」
という意味から官休庵と称したそうです(へええ・・・その1)
油小路通りを下り千家十職の一つ茶碗師の樂家と 樂美術館 の前を通り、
前面に裸体のレリーフがある超斬新な 旧京都中央電話局西陣分局舎 を
過ぎて北へ右折し一条通りに戻ってきました。

角に小野小町雙紙洗水遺跡と彫られた石碑があります。
前の南北の道が 小町通り です。ここには、こういう話が残されてます。
この辺りで平安時代の昔、歌会が催されました。常日頃、小野小町を
快く思っていなかった大友黒主は小町を懲らしめてやろうと
一計を図ります。小町が歌を書いた紙の上に加筆し、歌会の席上で
「この歌は万葉集の盗作である」と小町を糾弾したのでした。
ところが、さすがと言おうか、小町は少しも動揺せずに
“これは黒主が加筆したものだから、未だ墨が完全には
乾ききってはいない筈”と考え、歌が書かれている和紙を、
汲んだ井戸の水にそっと浸したのでした。
結果は想像の通り、黒主が加筆した部分は水に溶け出してしまい、
黒主は大変な恥をかかされたのでした。
伝説ですが、もしこういう話であったならば、黒主の策略は
余りにも幼稚ですし、それを皆の前で暴露した小野小町という
女性は、私にはとても恐ろしい女性に思えてしまいます。
この辺りには、宮本武蔵との決闘で有名な吉岡一門の道場が
有ったとか。昔この付近には松が沢山植わっていたそうで、
つまり“一条下り松”がいつのまにか“一乗寺下り松”と変化し、
詩仙堂の近くの一乗寺が決闘の場所となってしまった
という話があります。(へええ・・・その2)
前の南北の道が 小町通り です。ここには、こういう話が残されてます。
この辺りで平安時代の昔、歌会が催されました。常日頃、小野小町を
快く思っていなかった大友黒主は小町を懲らしめてやろうと
一計を図ります。小町が歌を書いた紙の上に加筆し、歌会の席上で
「この歌は万葉集の盗作である」と小町を糾弾したのでした。
ところが、さすがと言おうか、小町は少しも動揺せずに
“これは黒主が加筆したものだから、未だ墨が完全には
乾ききってはいない筈”と考え、歌が書かれている和紙を、
汲んだ井戸の水にそっと浸したのでした。
結果は想像の通り、黒主が加筆した部分は水に溶け出してしまい、
黒主は大変な恥をかかされたのでした。
伝説ですが、もしこういう話であったならば、黒主の策略は
余りにも幼稚ですし、それを皆の前で暴露した小野小町という
女性は、私にはとても恐ろしい女性に思えてしまいます。
この辺りには、宮本武蔵との決闘で有名な吉岡一門の道場が
有ったとか。昔この付近には松が沢山植わっていたそうで、
つまり“一条下り松”がいつのまにか“一乗寺下り松”と変化し、
詩仙堂の近くの一乗寺が決闘の場所となってしまった
という話があります。(へええ・・・その2)

小松帯刀(たてわき)寓居参考地は、大河ドラマ「篤姫」で
有名になった小松帯刀が、この地にあった近衛邸の別邸を借りて
住んでいたのではないかと考えられる事から、石碑が今年(2008年7月)
建てられました。幕末の状況って案外解ってない事が多い様です。
有名になった小松帯刀が、この地にあった近衛邸の別邸を借りて
住んでいたのではないかと考えられる事から、石碑が今年(2008年7月)
建てられました。幕末の状況って案外解ってない事が多い様です。

さていよいよ 一条戻橋 です。何かただならぬ魔界の雰囲気を感じさせる
名前ですね。名前は、平安時代、文章博士の三善清行(きよつら)の
葬送の列がこの橋にさしかかった時、修業先の紀州熊野から
急遽かけつけた息子の浄蔵が棺に取りすがって
「お父さん、生き返ってください」
と必死に祈った所、俄かに空が暗くなりむっくりと父の清行が生き返った
という伝説に由来するそうです。
それ以来、出征する兵隊さんは、必ず生きて日本に、京都に
戻って来れる様にと、この橋を渡って戦地に赴いたそうです。但し、
結婚で嫁ぐ花嫁さんは決してこの橋を渡ってはいけないそうです。
出戻りになっては困りますからね。
いやよく出来た話ですね。私はすごく面白い話と思いますが。
しかし、今私たちが見る橋は、何とお粗末というか橋らしくない
と言うか。昔は下を流れる堀川も十分な川幅があり、一条戻橋も
その名に違わず立派な橋で有ったかと想像力で補って下さい。
名前ですね。名前は、平安時代、文章博士の三善清行(きよつら)の
葬送の列がこの橋にさしかかった時、修業先の紀州熊野から
急遽かけつけた息子の浄蔵が棺に取りすがって
「お父さん、生き返ってください」
と必死に祈った所、俄かに空が暗くなりむっくりと父の清行が生き返った
という伝説に由来するそうです。
それ以来、出征する兵隊さんは、必ず生きて日本に、京都に
戻って来れる様にと、この橋を渡って戦地に赴いたそうです。但し、
結婚で嫁ぐ花嫁さんは決してこの橋を渡ってはいけないそうです。
出戻りになっては困りますからね。
いやよく出来た話ですね。私はすごく面白い話と思いますが。
しかし、今私たちが見る橋は、何とお粗末というか橋らしくない
と言うか。昔は下を流れる堀川も十分な川幅があり、一条戻橋も
その名に違わず立派な橋で有ったかと想像力で補って下さい。

堀川通りを渡ると、 妖怪ストリート までは、一直線です。
大将軍八神社のある大将軍商店街に入りました。ここが近頃話題になっている
妖怪ストリートです。
ここで言う妖怪とは、器物の妖怪である付喪神(つくもがみ)の事です。
商店街の店先にはその店をアピールする様々な姿の妖怪が立っていて
客の目を楽しませてくれます(?)。
大将軍八神社のある大将軍商店街に入りました。ここが近頃話題になっている
妖怪ストリートです。
ここで言う妖怪とは、器物の妖怪である付喪神(つくもがみ)の事です。
商店街の店先にはその店をアピールする様々な姿の妖怪が立っていて
客の目を楽しませてくれます(?)。

そろそろ、平野神社の名月祭が気になってきました。北野天満宮を通って、
平野神社 に着いた頃は、すっかり辺りは暗くなり、舞台では丁度、
日本舞踊が始まる所でした。空には美しい名月がその姿を見せています。
来年の中秋の名月は10月3日の土曜日だそうです。らくたびさん、
来年も又「名月観賞ツアー」の企画をお願いします。
参加の皆さん、お疲れ様でした。
らくたびさんならではの路上散策ツアーでした。
平野神社 に着いた頃は、すっかり辺りは暗くなり、舞台では丁度、
日本舞踊が始まる所でした。空には美しい名月がその姿を見せています。
来年の中秋の名月は10月3日の土曜日だそうです。らくたびさん、
来年も又「名月観賞ツアー」の企画をお願いします。
参加の皆さん、お疲れ様でした。
らくたびさんならではの路上散策ツアーでした。
文/らくたび会員 坂田肇様 写真/らくたび会員 鴨田一美様・坂田肇様
2007年04月08日
古きよき京都を訪ねて 西陣の桜めぐり

京都の桜がピークを迎えた4/8(日)午後1時、烏丸今出川に集合。35名の大人数です。
関東から参加してくださった方も多く、日本髪を結ってこられた着物姿の方や
ABC朝日放送の「ムーブ」のテレビ取材(4/12放映)もあり、
賑やかにスタートしました。
関東から参加してくださった方も多く、日本髪を結ってこられた着物姿の方や
ABC朝日放送の「ムーブ」のテレビ取材(4/12放映)もあり、
賑やかにスタートしました。

まずは少し北にある大聖寺門跡へ。室町幕府第三代将軍足利義満が
花の御所を築いた場所にあり、大聖寺門跡も義満が花の御所内に建てた
岡松殿が起こりだとか。歴史の長いつながりを感じます。
花の御所の石碑を後に、露地のような細い道を通って室町通へ。
この小さな通りが「室町幕府」や「室町時代」の名の由来に
なっているそうです。
さらに西へ行くときれいに改築された町家にたどり着きました。
こちらは町家ギャラリーとして今年の2月にオープンしたBe京都。
多様な作家さんの作品が並んでいます。
オーナーの内山さんが町家について説明してくださいました。
以前は有名な映画女優のお宅だったそうです。
花の御所を築いた場所にあり、大聖寺門跡も義満が花の御所内に建てた
岡松殿が起こりだとか。歴史の長いつながりを感じます。
花の御所の石碑を後に、露地のような細い道を通って室町通へ。
この小さな通りが「室町幕府」や「室町時代」の名の由来に
なっているそうです。
さらに西へ行くときれいに改築された町家にたどり着きました。
こちらは町家ギャラリーとして今年の2月にオープンしたBe京都。
多様な作家さんの作品が並んでいます。
オーナーの内山さんが町家について説明してくださいました。
以前は有名な映画女優のお宅だったそうです。

その横の光照院門跡を見て、さらに細い道を西へ進み、
日蓮宗の中で最初に勅願寺となった妙顕寺に到着です。
あの江戸時代の芸術家、尾形光琳や弟の乾山も
こちらの檀家さんだそうで、となりの寺院にお墓がありました。
境内の桜は満開なのにもかかわらず、観光客はほぼ皆無!
日蓮宗の中で最初に勅願寺となった妙顕寺に到着です。
あの江戸時代の芸術家、尾形光琳や弟の乾山も
こちらの檀家さんだそうで、となりの寺院にお墓がありました。
境内の桜は満開なのにもかかわらず、観光客はほぼ皆無!

さらに西へ行くとすぐ、人形寺として知られる宝鏡寺です。
通常非公開ですが、境内をのぞくと向いの和傘老舗店「日吉屋」の
和傘が干してありました。 いかにも京都らしい絵になる風景です。
通常非公開ですが、境内をのぞくと向いの和傘老舗店「日吉屋」の
和傘が干してありました。 いかにも京都らしい絵になる風景です。

その後、小川通では表千家と裏千家の家元の前を通り、
さらに北側にある妙覚寺へ。表門前の枝垂桜が満開でした。
表門は聚楽第の裏門といわれ、数少ない遺構とされています。
織田信長がかつては本能寺とともに常宿としていたそうで、
もしも、あの運命の日にこちらに泊まっていたら、
「本能寺の変」ではなく「妙覚寺の変」として
歴史に名が残っていたかもしれません。
さらに北側にある妙覚寺へ。表門前の枝垂桜が満開でした。
表門は聚楽第の裏門といわれ、数少ない遺構とされています。
織田信長がかつては本能寺とともに常宿としていたそうで、
もしも、あの運命の日にこちらに泊まっていたら、
「本能寺の変」ではなく「妙覚寺の変」として
歴史に名が残っていたかもしれません。

堀川通に出ると、北側に水火天満宮がありました。
ここは見事な紅枝垂桜が2本、境内の空気が桃色に染まっているかのよう。
あまりの美しさに立ちすくむ感じで見とれている人が多かったです。
境内では菅原道真ゆかりの「登天石」の説明を聞きました。
ここは見事な紅枝垂桜が2本、境内の空気が桃色に染まっているかのよう。
あまりの美しさに立ちすくむ感じで見とれている人が多かったです。
境内では菅原道真ゆかりの「登天石」の説明を聞きました。

その後、堀川通を渡って妙蓮寺へ。こちらの御会式桜は、
お釈迦様の誕生日である4月8日(本日)に満開になるはずなのですが、
ほとんど散っていたのが残念でした。(写真は昨年撮影)
お釈迦様の誕生日である4月8日(本日)に満開になるはずなのですが、
ほとんど散っていたのが残念でした。(写真は昨年撮影)

この辺りから西陣の町家が軒を連ねます。
その町中にひっそりと建っているのが雨宝院。弘法大師ゆかりの小さな寺院には、
折り重なるように歓喜桜や観音桜が咲いていました。
ここではお堂の前にお釈迦様が生まれた時に、甘い雨が降ったという
言い伝えにちなんで、誕生仏に甘茶をかけられるようになっていました。
次に訪れた釘抜地蔵(石像寺)では甘茶の接待まであり、
なんと綿菓子までいただいてしまいました。
みなさん綿菓子を口にして、「何年ぶりだろ~」と
喜んでいらっしゃいました。
その町中にひっそりと建っているのが雨宝院。弘法大師ゆかりの小さな寺院には、
折り重なるように歓喜桜や観音桜が咲いていました。
ここではお堂の前にお釈迦様が生まれた時に、甘い雨が降ったという
言い伝えにちなんで、誕生仏に甘茶をかけられるようになっていました。
次に訪れた釘抜地蔵(石像寺)では甘茶の接待まであり、
なんと綿菓子までいただいてしまいました。
みなさん綿菓子を口にして、「何年ぶりだろ~」と
喜んでいらっしゃいました。

そして千本釈迦堂のお亀さんの悲話が残るお亀桜へ。
大きな柳のような枝ぶりの立派な枝垂れ桜ですが、
少し遅かったようでかなり散っていました。
大きな柳のような枝ぶりの立派な枝垂れ桜ですが、
少し遅かったようでかなり散っていました。

その後、花街の上七軒を通り抜け、北野天満宮にお参りして、
最後は平野神社へ。ここでようやくたくさんの花見客に遭遇しました。
桜の名所といわれるだけあり、約400本の桜はまさに圧巻。
薄桃色の花の雲にすっぽりと覆われた境内にて解散となりました。
かなりの長距離散策、お疲れ様でした。ご参加ありがとうございました!
最後は平野神社へ。ここでようやくたくさんの花見客に遭遇しました。
桜の名所といわれるだけあり、約400本の桜はまさに圧巻。
薄桃色の花の雲にすっぽりと覆われた境内にて解散となりました。
かなりの長距離散策、お疲れ様でした。ご参加ありがとうございました!

