2007年02月10日
「松本酒造」清酒づくり特別見学と伏見散策
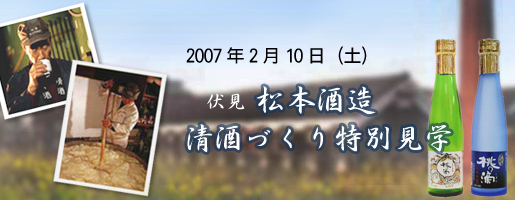
伏見は豊臣秀吉が建てた伏見城を中心に城下町として栄えた町。
今回は近鉄桃山御陵前駅から出発です。
大手筋商店街へ入ってすぐには銀座址の石碑があり、
付近にあった銀座の名残が銀座町という町名に見られます。
ちなみに東京の銀座はその後、つくられたそうです。
今回は近鉄桃山御陵前駅から出発です。
大手筋商店街へ入ってすぐには銀座址の石碑があり、
付近にあった銀座の名残が銀座町という町名に見られます。
ちなみに東京の銀座はその後、つくられたそうです。



しばらく進んで少し北にそれると、風変わりな二層の山門が。
ここは法然上人の25霊場の一つ、源空寺です。
伏見城から移築されたとされる山門の中には、
秀吉の念持仏で出世を導いたという大黒さんを祀っていました。
ここは法然上人の25霊場の一つ、源空寺です。
伏見城から移築されたとされる山門の中には、
秀吉の念持仏で出世を導いたという大黒さんを祀っていました。

商店街を抜け、5分ほど歩くと、時を経て深い黒味を帯びた
木目調の建物が見えてきました。
松本酒造さんです。
門を入って右側、まるで寺院のような重厚な玄関が迎えてくれます。
これは建仁寺にあった織田有楽斎(織田信長の弟で茶人)が使っていた
建物の玄関を移築したものだそうです。
木目調の建物が見えてきました。
松本酒造さんです。
門を入って右側、まるで寺院のような重厚な玄関が迎えてくれます。
これは建仁寺にあった織田有楽斎(織田信長の弟で茶人)が使っていた
建物の玄関を移築したものだそうです。

松本酒造の松本保博さんに迎えられ、
庭園の見える部屋へ通されました。
そこでは松本酒造さんの歴史、建物や庭のこと、お酒づくりのこと
などのお話をおいしいお抹茶とお菓子とともにいただきました。
庭園の見える部屋へ通されました。
そこでは松本酒造さんの歴史、建物や庭のこと、お酒づくりのこと
などのお話をおいしいお抹茶とお菓子とともにいただきました。

特に印象に残ったのは、酒づくりへのこだわり。
酒米選びやつくり方はもちろんですが、
何よりもつくる時の「心構え」を大事にされていることが
伝わってきました。最新の技術と伝統をうまく融合させながらも、
酒文化に誇りをもって取り組んでいける文化的環境を守っていくことが、
その心構えを支える大切な要素だそうです。
それが今日迎えていただいた、「万暁院」
(大正時代から変わらぬ有名な酒造場で、構想から完成まで1万日、
約30年の意)というお客様をもてなす迎賓館として形となって
あらわわれていると実感しました。
酒米選びやつくり方はもちろんですが、
何よりもつくる時の「心構え」を大事にされていることが
伝わってきました。最新の技術と伝統をうまく融合させながらも、
酒文化に誇りをもって取り組んでいける文化的環境を守っていくことが、
その心構えを支える大切な要素だそうです。
それが今日迎えていただいた、「万暁院」
(大正時代から変わらぬ有名な酒造場で、構想から完成まで1万日、
約30年の意)というお客様をもてなす迎賓館として形となって
あらわわれていると実感しました。



その後、できあがった日本酒を絞っているところへ案内してもらいました。
そこでは、絞った直後の酒糟(さけかす)をその場で食べさせてもらい、
絞りたての「桃の滴」をいう銘柄のお酒を試飲させていただきました。
スーッとしたのどこし、すっきりとして心地よい味わい。
少し間を置いてカーッと熱くなり、身体がぽかぽかと温まってきます。
サイコーです!気分良くおかわりまでいただいてしまいました。
そこでは、絞った直後の酒糟(さけかす)をその場で食べさせてもらい、
絞りたての「桃の滴」をいう銘柄のお酒を試飲させていただきました。
スーッとしたのどこし、すっきりとして心地よい味わい。
少し間を置いてカーッと熱くなり、身体がぽかぽかと温まってきます。
サイコーです!気分良くおかわりまでいただいてしまいました。

帰り際、お土産にと酒糟と銘酒「桃の滴」までいただきました!

松本酒造を後にし、門を出てすぐ西側の川べりに立ち寄ります。
ここからの松本酒造の全景は、伏見を代表する風景として知られています。
ここからの松本酒造の全景は、伏見を代表する風景として知られています。

竹田街道まで戻り、日本電車発祥の地の石碑を過ぎると、
油懸け地蔵という旗が見えてきます。
昔大山崎の油商人が、ここにあったお地蔵さんに油を懸けて祈願したところ
商売が大成功したことから信仰が続いているそうです。
お堂の中には油で黒光りしたお地蔵さんがいらっしゃいました。
その横には松尾芭蕉がこのお寺の住職を訪ねた時に残した句がありました。
油懸け地蔵という旗が見えてきます。
昔大山崎の油商人が、ここにあったお地蔵さんに油を懸けて祈願したところ
商売が大成功したことから信仰が続いているそうです。
お堂の中には油で黒光りしたお地蔵さんがいらっしゃいました。
その横には松尾芭蕉がこのお寺の住職を訪ねた時に残した句がありました。
「我衣に伏見の桃の雫せよ」
気付かれましたか?先ほどいただいた松本酒造さんの「桃の滴」の銘は
この句から取ったそうです。
その後は龍馬通商店街から寺田屋、伏見の運河の横を散策しながら
「島の弁天さん」で知られる長建寺、月桂冠大倉記念館の前を通り、
月桂冠の元本店である「伏見夢百衆」の前で解散しました。
松本酒造様、ご参加下さいました会員の皆様、ありがとうございました!
この句から取ったそうです。
その後は龍馬通商店街から寺田屋、伏見の運河の横を散策しながら
「島の弁天さん」で知られる長建寺、月桂冠大倉記念館の前を通り、
月桂冠の元本店である「伏見夢百衆」の前で解散しました。
松本酒造様、ご参加下さいました会員の皆様、ありがとうございました!

