2012年01月30日
1月28日(土) なにわたび!大坂冬の陣へ

らくたび京都さんぽ恒例の遠征シリーズ。京都散策をより深くお楽しみ
いただくために、これまで、「ならたび(奈良)」、「しがたび(滋賀)」、さらには
「江戸たび(東京)」を実施してきました。
そして・・・この冬、ついに実現したのが、 「なにわたび!」 です。
京都さんぽ初の大阪遠征は、 「なにわたび!大坂冬の陣」 と題して、
大坂冬の陣の最大の激戦地であり、戦国武将・真田幸村が「真田丸」を
築いた玉造エリアから、大坂城へと散策しました。
ご案内は・・・ 戦国スペシャリスト・山村 純也 (らくたび代表)

「好きな歴史上の人物は?」の問いに「豊臣秀吉」と答える山村がご紹介
するこの散策。期待が高まります!

ご案内の山村、参加者24名様、らくたびスタッフ若村、森、の総勢27名にて、
大坂冬の陣へ、いざ出陣~!
駅を出てすぐの商店街には、真田幸村をモデルにしたキャラクターが!
交差点名は・・・
参加者のGさんは真田氏と同じく信州のご出身。戦国随一の武将として
歴史に名を刻む地元のヒーローゆかりの地を歩くことを、楽しみにして
くださっていたそうです。嬉しいですね!
【 鎌八幡 】

大坂冬の陣の時、真田幸村が戦勝祈願に神木に鎌を打ち込んだところ、
真田丸で大勝利をおさめることができ、「必勝祈願の木」として評判に
なったそう。また、「鎌」が「切る」に通じることから、現在では「縁切り」の
ご利益で信仰されています。
【 心眼寺 】
真田幸村の菩提を弔うために、江戸時代に創建された浄土宗の寺院。
門の扉には真田家の「六文銭の家紋」が見られます。
【 どんどろ大師 】

正式名称は善福寺。 通称の「どんどろ大師」は、江戸時代、大坂城代の
大名・土井利位 (どい としつら)が弘法大師 に深く信仰を寄せてこちらに
参拝していたことから “ 土井殿の大師 ” (どいどののだいし)がいつしか
「どんどろ大師」 となったそう(大笑)
ここで、らくたび・若村は早くも戦線離脱・・・?
いや、大阪での講義があるため、お仕事へ向かいました。いってらっしゃ~い!
【 三光神社 】
大坂冬の陣の時に、真田幸村が築いた出城 「真田丸」 と跡地と伝えられ、
境内には幸村が掘ったと伝わる 「真田の抜け穴」 や幸村像が立っています。
ここで、山村が幸村の戦いぶりを熱~く熱~く語り、参加者の皆様は熱心に
耳を傾けてくださいました。
【 玉造稲荷 】
大坂城の鎮守社として信仰されたお社。
境内には豊臣秀頼寄進の石の鳥居と秀頼像があります。
【 聖マリア大聖堂 ・ 越中井 】

大坂冬の陣から遡ること14年前、天下分け目の決戦「関ヶ原の戦い」の時、
細川越前守忠興の妻・ガラシャ夫人が西軍・石田三成の人質になることを拒み、
屋敷のあったこの地で最期を遂げました。

ちりぬべき 時知りてこそ 世の中の
花も花なれ 人も人なれ (細川ガラシャ辞世の句)
真田幸村はじめ、戦国武将のゆかりの地を歩き、いよいよ、大坂城へ登城します。
【 大坂城 】

豊臣秀吉によって築城され、子・秀頼の時代の「大坂夏の陣」で焼け落ちた天守閣は
徳川幕府によって再築されますが、その後の落雷で再び焼失。現在の天守閣は
昭和6年に市民の寄付によって完成され、大阪のシンボルとなっています。
エレベーターで8階の展望台まで上がると、地上50mから広大な大阪城公園と
大阪の街を一望。天下人と同じ風景を見ることができました。
また、館内では 「プチ変身」 もできまして、せっかくなので・・・
Aさん(写真左) : 豊臣秀吉 森(写真右) : 真田幸村 に変~身!
【 淀殿 ・ 豊臣秀頼 自刃の地 】
山村から大坂夏の陣における二人の最期についてのご案内がありました。
この後、JR/京阪・京橋駅まで歩き、この日の「なにわたび!」は無事終了と
なりました。参加者の皆さまからは、「戦国ゆかりの地を歩いてきた後に、大阪城
から見る景色は最高でした」、「京都との違いが感じられた」、「大阪市在住なので
地元の魅力がわかった」などのご感想をいただきました。
さらに、「“大坂冬の陣”が開催されたということは、“大坂夏の陣”もありますよね?」
とのご質問があり、山村からは「ぜひ、開催しましょう」と。
参加者の皆さま、6.3㎞のロングさんぽとなりましたが、お疲れさまでした。
次回は、夏の陣でお会いしましょう~!
ご案内:らくたび代表 山村 純也
写真:らくたび会員 鴨田 一美様
受付・添乗・文・写真:らくたびスタッフ 森 明子
2012年01月16日
2012年1月15日(日)着物で神社へ新年参拝
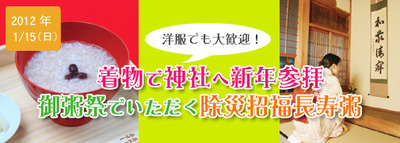
2012年1月15日(日)の京都さんぽは・・・
「着物で神社へ新年参拝
御粥祭でいただく除災招福長寿祈願」 です。
ご案内は らくたび代表 若村 亮 
着物姿でご案内です~♪
京阪・出町柳駅をスタートし、まずは 【 下鴨神社 】 へ
大きな境内図の前で、神社の歴史をご紹介。
平安京以前の原生林の植生を伝える自然林「糺の森(ただすのもり)」の
参道を進むと朱色の鳥居が見えてきました。
「早くお参りに行きたい!」と気持ちは高まりますが、まずは身を清めましょう。
次に「鳥居の正しいくぐり方」のご紹介です。
「鳥居のまん中は神さまの通り道」となりますので、まん中を避けて・・・
「柱に近い端っこを通る」のが正しいくぐり方です。
下鴨神社の御祭神は、
賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと) と 玉依媛命(たまよりひめのみこと)
古来、京都の守護神として、国家国民の安穏と平和を祈願するとともに、
厄除け、交通安全、縁結び、安産、子育ての神さまとして篤く信仰されています。
皆さまにとって2012年がよき年となるように・・・お参りしましょう。
また、干支のお社「言社」には、十二支の生まれの年の守り神さまがお祀り
されていますので、それぞれのお社に参拝。
「私のお社はどこ?」、「丑さんはあっちです」、「あっ、一緒のお社ですね」・・・
大勢でワイワイと参拝すると楽しいですね♪
参拝後は、この日のメインイベント(?) 【 除災難招福長寿粥 】
京都では小豆粥を「あずのおかいさん」といい、1/15(小正月)に食べると
邪気を祓うと言われています。小豆とお餅の入った熱々の御粥をいただきました。
下鴨神社の境内にある 【 河合神社 】 は美人祈願のお社として人気急上昇中!
手鏡をかたどった絵馬にお化粧をして奉納すると、身も心も美しなれるとか。
本殿には愛らしいニコニコ笑顔の絵馬がたくさん奉納されていました。
またこちらは『方丈記』の著者・鴨長明ゆかりの神社でもあります。
河合神社の神官の家に生まれた鴨長明でしたが、事情により神官を継ぐことが
できず、この無常感がのちに『方丈記』を書くにいたったとか。
境内には復元された方丈が公開されています。
「美人祈願の効果はあったかな?」なんて話をしていると、参加者のKさまが
「京都さんぽに参加していると楽しいから“笑顔美人”になっていますよ」と
嬉しいお言葉が!ありがとうございます(*^_^*)
下鴨神社をたっっっ~ぷりと参拝し、次の訪問地へと向かいます。
【 幸神社(さいのかみのやしろ) 】
現在は小さな神社ですが、創建の歴史は非常に古く、御所を護る鬼門(北東)の
神さまとして崇められてきました。現在では、方除け、縁結びのお社として
信仰されています。
「鬼門除けの猿」もちゃんといらっしゃいます。
続いては、現在≪京の冬の旅≫特別公開中の
【 相国寺・大光明寺 】
辰年の守り本尊である普賢菩薩像を拝観。また伊藤若冲筆の襖絵、室町幕府の
9代将軍・足利義尚の自筆などの寺宝などを見学しました。
そして、最後は・・・
【 俵屋吉富 】
御抹茶と季節の和菓子をいただきました。
おいしいお菓子でホッコリし、こちらで京都さんぽは終了となりました。
参加者の皆さまからは、「普段なかなか着物を着る機会がないので
よかったです」と嬉しいお言葉をいただきました。
皆さまのきれいな着物姿を見ていると、私も着てみたくなったりして・・・
日本文化の良さをあらためて感じた京都さんぽとなりました。
ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。
【 おまけ 】
実はこの日は≪第30回全国都道府県対抗女子駅伝≫が開催されており、
解散後、第8区の力走を観戦することができました。
第8区は中学生が3㎞を走ります。
この時点で1位は大阪、2位が京都。
「頑張れ~!」
京都さんぽの参加者さんの出身地、千葉、東京、長野、群馬、兵庫、鹿児島・・・
みんな頑張れ~!
冬の都大路を懸命に駆ける姿に、元気をいただくことができました。
ご案内・写真/らくたび 若村
受付・添乗・文・写真/らくたび 森
2012年01月15日
2012年1月9日(月・祝) 新春! えべっさんめぐり

1月9日(月・祝)
2012年 辰年 最初の「 らくたび京都さんぽ 」が開催されました!
新年最初の京都さんぽは、新春!えべっさんめぐり です。
まずは平安時代から八坂神社に祀られている えべっさん を参拝しました。
蛭子社を参拝し、商売繁昌・開運招福を願い・・・。

大国主社を参拝し、良縁成就・家内安全を願い・・・。

最後に本殿を参拝し、厄除・災難除を願い・・・。

新春吉例「 三社詣 」をお参りして、今年はこれで縁起が良い〜。

お参りし各お社でご朱印をいただき、こんな有り難〜いお札が完成。
自宅に持ち帰り御祀りします

この日の午後、蛭子祭が行われるため八坂さんの境内には 七福神 を
乗せる えびす船 がスタンバっていました。

今日のもうひとつのテーマ、
2012年大河ドラマ「平清盛」にちなむこちらは 忠盛灯籠 です。
清盛の出生にまつわるエピソードが残る史跡ですが、この日は前日の
大河ドラマ初回放映について賛否両論の会話が行き交ってましたよ


賑やかな八坂神社を後に、閑静な円山公園を抜け、2012年大河ドラマ
「平清盛」に合わせて公開されるようになった? 京都祇園堂 へ。
こちらは清盛の母、という説もある祗園女御の御廟があるお堂です。
今まではほぼ閉じられていましたが、今年は常時開放されるようです、
ぜひ一度は訪れてみてくださいね。

祗園閣がそびえる大雲院 〜 月真院 〜 ねねの道 〜圓徳院の境内にある
秀吉の出世守り本尊・三面大黒をご参拝。

大黒天、弁財天、毘沙門天の三面のお顔を持ち、
一 つの仏様を拝むことによって三尊のご利益が得られるということで、
これまた縁起が良い〜


京情緒あふれる石塀小路をぬけ、八坂庚申堂 〜 八坂の塔を経て、
大河ドラマ「平清盛」の舞台・六波羅界隈へと進みます。
夏のお精霊迎えの際に賑わう六道珍皇寺へ。

こちらには小野篁が冥界に通ったと伝わる井戸が今も残り、その井戸を
拝見するために木戸の一部が覗けるようになってまして、
・・・みなさん頑張っておられま〜す


平家ゆかりの六波羅蜜寺では、都七福神のひとつ弁財天を参拝しました。

こちらは平清盛公の供養塔です。
昨年秋には大河ドラマ主役の松山ケンイチさんもご参拝に来られたそうです。

六波羅蜜寺のご本尊は12年に一度「 辰年 」に、そう今年の秋にご開帳されます。
大河ドラマ「平清盛」ゆかりの地として、
そしてご本尊ご開帳と一年を通して賑わうこと間違いなしですね。
さあ、いよいよツアーも終盤です!
新春の商売繁盛を願い 宵えびす で賑わう 祇園の恵美須神社 をご参拝。

福笹に縁起物をたくさんつけて、それぞれの思いを込めてお参りしました!

最後は、お正月飾りで
 華やかな
華やかな 花街・宮川町から帰路へとつきました。
花街・宮川町から帰路へとつきました。
新春らしくおめでたく、ご利益をいっぱいいただいた「 京都さんぽ 」でした。
参加者のみなさん、
これで辰年の龍のごとく、今年の運勢はぐん
 ぐん
ぐん と上昇しますね〜。
と上昇しますね〜。文・写真/らくたび会員 奥村なるみ

