2013年04月07日
4/7 王朝の古式ゆかしい嵯峨野めぐり
4/7(日)の京都さんぽは平安王朝の雅を感じる嵯峨野めぐりへ!
昨日からの暴風雨で、開催すら危ぶまれましたが、なんとか天気も
回復。そして・・・まだまだ美しい桜を楽しむことができました。
≪ とっておきの桜スポット ≫



今は遅咲き桜が見ごろとなっています。少しずつ花の形が異なるので
比べて見るのも楽しいですね。
≪ 広沢池と遍照寺山 ≫

「 嵯峨富士 」とも称される美しい山。広沢池は月の名所としても名高く
多くの和歌にも詠まれています。
いにしえの人は汀に影絶えて 月のみ澄める広沢池 - 源頼政 -
この後、観音島にも足を延ばしました。
≪ 大覚寺 ≫

「 旅行会社のポスターになりそうな写真が撮れました! 」とおっしゃったKさん。
ええ、私もです(笑) 白砂 × 桜 × 唐門が京都らしい~。

今回は大沢池も散策。すると、昨日の暴風で散った桜が池面を染める貴重な
風景に遭遇!ある意味、昨日の嵐に感謝です。
Tさんからは「 大覚寺は何回も来ているけど、池に降りたのは初めて! 」と。
楽しんでいただけたようでよかったです!
大覚寺は嵯峨天皇の離宮「嵯峨院」に始まるお寺。そんな由緒正しき
庭園を京都さんぽが貸切状態でした。
今年は桜の開花が想像以上に早く、正直なところ、私も今日の散策は
桜は期待できないので、お越しくださるお客さまにも申し訳ない・・・と
思っていました。ところが・・・嵐に耐えた桜、桜吹雪、花筏、散り桜と
春の嵐が作ってくれた予想外のシーンを堪能することができました。
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
らくたびでは、まだまだ、桜さんぽやってます。( こちら )
「 らくたびの散策は桜が散っていても十分見どころがある場所に
案内してくれるから楽しいよ 」と言ってくださったMさん!
ありがとうございます!その言葉を励みに4/15までがんばります~(*^_^*)
らくたび 森
昨日からの暴風雨で、開催すら危ぶまれましたが、なんとか天気も
回復。そして・・・まだまだ美しい桜を楽しむことができました。
≪ とっておきの桜スポット ≫
今は遅咲き桜が見ごろとなっています。少しずつ花の形が異なるので
比べて見るのも楽しいですね。
≪ 広沢池と遍照寺山 ≫
「 嵯峨富士 」とも称される美しい山。広沢池は月の名所としても名高く
多くの和歌にも詠まれています。
いにしえの人は汀に影絶えて 月のみ澄める広沢池 - 源頼政 -
この後、観音島にも足を延ばしました。
≪ 大覚寺 ≫
「 旅行会社のポスターになりそうな写真が撮れました! 」とおっしゃったKさん。
ええ、私もです(笑) 白砂 × 桜 × 唐門が京都らしい~。
今回は大沢池も散策。すると、昨日の暴風で散った桜が池面を染める貴重な
風景に遭遇!ある意味、昨日の嵐に感謝です。
Tさんからは「 大覚寺は何回も来ているけど、池に降りたのは初めて! 」と。
楽しんでいただけたようでよかったです!
大覚寺は嵯峨天皇の離宮「嵯峨院」に始まるお寺。そんな由緒正しき
庭園を京都さんぽが貸切状態でした。
今年は桜の開花が想像以上に早く、正直なところ、私も今日の散策は
桜は期待できないので、お越しくださるお客さまにも申し訳ない・・・と
思っていました。ところが・・・嵐に耐えた桜、桜吹雪、花筏、散り桜と
春の嵐が作ってくれた予想外のシーンを堪能することができました。
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
らくたびでは、まだまだ、桜さんぽやってます。( こちら )
「 らくたびの散策は桜が散っていても十分見どころがある場所に
案内してくれるから楽しいよ 」と言ってくださったMさん!
ありがとうございます!その言葉を励みに4/15までがんばります~(*^_^*)
らくたび 森

2012年09月23日
9月15日 大覚寺「源平ゆかりの寺宝」観賞と京料理
9月15日のらくたび京都さんぽは、嵯峨釈迦堂で知られる清凉寺から
初秋の嵯峨野を経て、大覚寺で京の夏の旅「霊宝館」の
源平ゆかりの寺宝展を鑑賞しました。
途中、京料理おきなにて、嵯峨豆腐を用いたおいしい京料理も頂きました。
出発は嵯峨嵐山駅。愛宕山が美しく見えています。

最初はゆっくり歩きながら、清凉寺へ。

嵯峨釈迦堂とも呼ばれる清凉寺では、釈迦37歳の像を写した
生身(しょうしん)の釈迦如来像を、間近で拝観させていただきました。
釈迦像の中からは五臓六腑の模型も見つかっており、
本当に生き写しであることが想像できますね。
若村先生に展示品を丁寧に説明して頂けました。

お堂をじっくりと回った後は、境内もゆっくりと散策します。
こちらは豊臣秀頼公の首塚。清凉寺は秀頼によって復興されており、
昭和55年に大阪城の三の丸跡の発掘で見つかった頭蓋骨が
秀頼のものではないかとして、こちらに首塚が作られました。

一切経蔵では、輪蔵(りんぞう)を回すことで、
一切経を読んだのと同じ功徳を授かれるとされます。
参加者の皆様もゆっくりと回されていましたよ!

さて、じっくりと清凉寺を散策した後は、お待ちかねの豆腐料理♪
「京料理おきな」さんは、嵯峨豆腐「森嘉」さんの向かいにあって、
ミシュランガイドでは☆も獲得されています。

次々と運ばれるお豆腐料理に舌鼓を打ちます♪



皆さんと歓談しながら和やかに頂きました。
とてもおいしかったです。

お腹を満たした後は、大覚寺へ向けて嵯峨野を散策!

稲の穂も実りだし、遠くには鳥居形も見えます。
9月も半ばを迎えながら残暑が厳しい一日でしたが、
初秋の雰囲気も感じることが出来ました。

大覚寺は、格式高い門跡寺院。
大玄関では後宇多法皇が使用した輿が置かれ、
雅な雰囲気で迎えてくれます。

こちらは宸殿(しんでん)の蔀(しとみ)戸に付けられた金具。
蝉の形をしていて面白いですね。一つ一つ蝉の種類も違うそうですよ。
蝉は逃げる時に鳴き声を出すので、
侵入者を検知する防犯の願いが込められています。

参加者の皆様も興味津々で見上げています。

さて、霊宝館では源平ゆかりの寺宝展が行われています。
ちょうど中で観賞している間に・・・

外は一時的に大雨になっていました!心経殿も雨にかすみます。
心経殿の中には歴代天皇直筆の写経が収められ、
天皇の命により封印がされて信仰の対象ともなっている建物。
60年に1回の開扉と開封で、次回は平成30年に開かれますよ。

雨上がりの大覚寺は苔の緑が生き生きとしていました。

今回は大覚寺前で解散です。
ちょうど雨に降られる前に嵯峨野や大覚寺の風景を眺めることでき、
京料理おきなさんでは、豆腐料理を堪能することができました。
雨上がりの大覚寺も苔が綺麗で、晴れと雨、
それぞれを楽しめたのはラッキーでしたね。
今回はご参加頂きまして、ありがとうございました。

ご案内 / らくたび代表・若村 亮
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
初秋の嵯峨野を経て、大覚寺で京の夏の旅「霊宝館」の
源平ゆかりの寺宝展を鑑賞しました。
途中、京料理おきなにて、嵯峨豆腐を用いたおいしい京料理も頂きました。
出発は嵯峨嵐山駅。愛宕山が美しく見えています。
最初はゆっくり歩きながら、清凉寺へ。
嵯峨釈迦堂とも呼ばれる清凉寺では、釈迦37歳の像を写した
生身(しょうしん)の釈迦如来像を、間近で拝観させていただきました。
釈迦像の中からは五臓六腑の模型も見つかっており、
本当に生き写しであることが想像できますね。
若村先生に展示品を丁寧に説明して頂けました。
お堂をじっくりと回った後は、境内もゆっくりと散策します。
こちらは豊臣秀頼公の首塚。清凉寺は秀頼によって復興されており、
昭和55年に大阪城の三の丸跡の発掘で見つかった頭蓋骨が
秀頼のものではないかとして、こちらに首塚が作られました。
一切経蔵では、輪蔵(りんぞう)を回すことで、
一切経を読んだのと同じ功徳を授かれるとされます。
参加者の皆様もゆっくりと回されていましたよ!
さて、じっくりと清凉寺を散策した後は、お待ちかねの豆腐料理♪
「京料理おきな」さんは、嵯峨豆腐「森嘉」さんの向かいにあって、
ミシュランガイドでは☆も獲得されています。
次々と運ばれるお豆腐料理に舌鼓を打ちます♪
皆さんと歓談しながら和やかに頂きました。
とてもおいしかったです。
お腹を満たした後は、大覚寺へ向けて嵯峨野を散策!
稲の穂も実りだし、遠くには鳥居形も見えます。
9月も半ばを迎えながら残暑が厳しい一日でしたが、
初秋の雰囲気も感じることが出来ました。
大覚寺は、格式高い門跡寺院。
大玄関では後宇多法皇が使用した輿が置かれ、
雅な雰囲気で迎えてくれます。

こちらは宸殿(しんでん)の蔀(しとみ)戸に付けられた金具。
蝉の形をしていて面白いですね。一つ一つ蝉の種類も違うそうですよ。
蝉は逃げる時に鳴き声を出すので、
侵入者を検知する防犯の願いが込められています。
参加者の皆様も興味津々で見上げています。
さて、霊宝館では源平ゆかりの寺宝展が行われています。
ちょうど中で観賞している間に・・・
外は一時的に大雨になっていました!心経殿も雨にかすみます。
心経殿の中には歴代天皇直筆の写経が収められ、
天皇の命により封印がされて信仰の対象ともなっている建物。
60年に1回の開扉と開封で、次回は平成30年に開かれますよ。
雨上がりの大覚寺は苔の緑が生き生きとしていました。
今回は大覚寺前で解散です。
ちょうど雨に降られる前に嵯峨野や大覚寺の風景を眺めることでき、
京料理おきなさんでは、豆腐料理を堪能することができました。
雨上がりの大覚寺も苔が綺麗で、晴れと雨、
それぞれを楽しめたのはラッキーでしたね。
今回はご参加頂きまして、ありがとうございました。

ご案内 / らくたび代表・若村 亮
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
2012年05月27日
5月20日(日) 優雅な三船祭と悲恋が残る嵯峨野めぐり
5月20日(日)のらくたび京都さんぽは、新緑の美しい嵐山にて
平安貴族の船遊びを再現した三船祭を見学し、
平安時代に世をしのぶ女性が隠れ住んだ嵯峨野を歩き、
最後は嵯峨祭のお神輿が並ぶ清凉寺前のお旅所を目指して散策しました。
出発は阪急の嵐山駅。三船祭が行われるとあって
人も多めです。まずは法輪寺から。
法輪寺へは階段を上っていきますが、見事な新緑もみじが迎えてくれました!

法輪寺には電電宮というちょっと珍しいお社があり、
電気・電波の神である電電明神が祀られていますよ。

法輪寺からは抜群の眺望を楽しむことができます。
山村先生が、送り火や山々を丁寧に解説して下さいました。
ちょうど三船祭の一行が渡月橋へと向かってくる場面も目撃です!

法輪寺から櫟谷(いちだに)宗像神社を経て、渡月橋まで来ると、
三船祭の牛車が到着していました。

三船祭を見学する前に、小督(こごう)塚に立ち寄りました。
小督局は平安時代、その美貌と琴の音色で高倉天皇に愛された女性でしたが、
娘を高倉天皇の妃としていた平清盛の圧力によって嵯峨野に隠れ住むことになりました。
それでも彼女を探しに来た天皇の使いは、美しい琴の音色から見事に小督を見つけ出したという
ロマンチックな物語があります。

さて、いよいよ三船祭の船遊びが始まりました。車折神社の御祭神も御座船にお乗りになり、
龍頭船では雅な舞が披露されています。時代をタイプスリップしたかのような光景ですね!


私たちも平安時代の船遊びの世界をじっくりと堪能させていただきました。

名残を惜しみつつ三船祭を後にして、嵐山公園を散策します。
保津川を開削した角倉了以(すみのくら りょうい)の像を解説中です。
円山公園の坂本竜馬像・三条大橋の高山彦九郎像と並ぶ
京都三大銅像の一つだそうですよ~!

嵯峨野の美しい竹林も抜けて行きました~!

輝く緑に包まれた野宮神社に到着です。
皮を残したままのクヌギを使った黒木の鳥居が印象的です。

野宮神社は伊勢神宮に奉仕する女性・斎宮が身を清めた場所の一つで、
源氏物語では光源氏と六条御息所の別れの場面で登場します。

嵐山の景色を再現した苔のお庭もありますよ。
橋が渡月橋で奥の灯籠が愛宕山!緑がいっぱいの境内でした。

嵯峨野散策を続けていると、土佐四天王像が現れました!
凛々しい表情をされています。

俳人・向井去来ゆかりの落柿舎(らくししゃ)の前。柿の木も緑の葉を茂らせていました。
辺りは長閑な風景が広がっています。山村先生が落柿舎の名前の由来を面白く解説中です。

桜と紅葉の美しい二尊院の前を経て・・・

祇王寺に到着しました!境内は柔らかい一面の緑に包まれて
「これぞ京都」といった空間です。

祇王寺は、平安時代の白拍子・祇王や仏御前ゆかりのお寺です。
祇王は清盛に気に入られた歌や舞の名手でしたが、仏御前の登場によって捨てられ、
母や妹とともに嵯峨野に隠れ住みました。
やがては仏御前も世を儚んでやってきて、皆で念仏三昧の余生を過ごしました。
境内には祇王のお墓と清盛の供養塔が並んでいます。

最後は、清凉寺の境内を抜けて、野宮神社と愛宕神社のお神輿が置かれている御旅所へ。
別々の神社のお神輿が並んでいるのが面白いですね。

今回の散策は、美しい船遊びに平安の雅を感じ、新緑に包まれた社寺をじっくりと巡りながら
心癒された散策だったのではないでしょうか。山村先生の優しい口調で語られる悲恋の物語も、
柔らかい緑によく似合っていました。気持のよい5月のひと時。
皆様、ご参加頂き本当にありがとうございました。

ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
平安貴族の船遊びを再現した三船祭を見学し、
平安時代に世をしのぶ女性が隠れ住んだ嵯峨野を歩き、
最後は嵯峨祭のお神輿が並ぶ清凉寺前のお旅所を目指して散策しました。
出発は阪急の嵐山駅。三船祭が行われるとあって
人も多めです。まずは法輪寺から。
法輪寺へは階段を上っていきますが、見事な新緑もみじが迎えてくれました!
法輪寺には電電宮というちょっと珍しいお社があり、
電気・電波の神である電電明神が祀られていますよ。
法輪寺からは抜群の眺望を楽しむことができます。
山村先生が、送り火や山々を丁寧に解説して下さいました。
ちょうど三船祭の一行が渡月橋へと向かってくる場面も目撃です!
法輪寺から櫟谷(いちだに)宗像神社を経て、渡月橋まで来ると、
三船祭の牛車が到着していました。
三船祭を見学する前に、小督(こごう)塚に立ち寄りました。
小督局は平安時代、その美貌と琴の音色で高倉天皇に愛された女性でしたが、
娘を高倉天皇の妃としていた平清盛の圧力によって嵯峨野に隠れ住むことになりました。
それでも彼女を探しに来た天皇の使いは、美しい琴の音色から見事に小督を見つけ出したという
ロマンチックな物語があります。
さて、いよいよ三船祭の船遊びが始まりました。車折神社の御祭神も御座船にお乗りになり、
龍頭船では雅な舞が披露されています。時代をタイプスリップしたかのような光景ですね!
私たちも平安時代の船遊びの世界をじっくりと堪能させていただきました。
名残を惜しみつつ三船祭を後にして、嵐山公園を散策します。
保津川を開削した角倉了以(すみのくら りょうい)の像を解説中です。
円山公園の坂本竜馬像・三条大橋の高山彦九郎像と並ぶ
京都三大銅像の一つだそうですよ~!
嵯峨野の美しい竹林も抜けて行きました~!
輝く緑に包まれた野宮神社に到着です。
皮を残したままのクヌギを使った黒木の鳥居が印象的です。
野宮神社は伊勢神宮に奉仕する女性・斎宮が身を清めた場所の一つで、
源氏物語では光源氏と六条御息所の別れの場面で登場します。
嵐山の景色を再現した苔のお庭もありますよ。
橋が渡月橋で奥の灯籠が愛宕山!緑がいっぱいの境内でした。
嵯峨野散策を続けていると、土佐四天王像が現れました!
凛々しい表情をされています。
俳人・向井去来ゆかりの落柿舎(らくししゃ)の前。柿の木も緑の葉を茂らせていました。
辺りは長閑な風景が広がっています。山村先生が落柿舎の名前の由来を面白く解説中です。
桜と紅葉の美しい二尊院の前を経て・・・
祇王寺に到着しました!境内は柔らかい一面の緑に包まれて
「これぞ京都」といった空間です。
祇王寺は、平安時代の白拍子・祇王や仏御前ゆかりのお寺です。
祇王は清盛に気に入られた歌や舞の名手でしたが、仏御前の登場によって捨てられ、
母や妹とともに嵯峨野に隠れ住みました。
やがては仏御前も世を儚んでやってきて、皆で念仏三昧の余生を過ごしました。
境内には祇王のお墓と清盛の供養塔が並んでいます。
最後は、清凉寺の境内を抜けて、野宮神社と愛宕神社のお神輿が置かれている御旅所へ。
別々の神社のお神輿が並んでいるのが面白いですね。
今回の散策は、美しい船遊びに平安の雅を感じ、新緑に包まれた社寺をじっくりと巡りながら
心癒された散策だったのではないでしょうか。山村先生の優しい口調で語られる悲恋の物語も、
柔らかい緑によく似合っていました。気持のよい5月のひと時。
皆様、ご参加頂き本当にありがとうございました。
ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
2009年05月30日
本格的陶芸体験と新緑の奥嵯峨めぐり

今日の京都さんぽは、体験版です!
嵯峨野にある 大覚寺陶房 さんで、手ひねりによる陶芸制作です。
不器用な私にとっては、ハードルの高い挑戦になることでしょう~。
嵯峨野にある 大覚寺陶房 さんで、手ひねりによる陶芸制作です。
不器用な私にとっては、ハードルの高い挑戦になることでしょう~。

工房に到着すると、テーブルには土の固まりが用意されていました。
その土を前にして各自思い思いの器をイメージしながらこねていきす。
私は半年前から茶道を習い始めたので、
せっかくならと、「お抹茶碗」を作ることにしました。
「土をこねる」というのはなんとも気持ちの良いもので……
いつまでもこねこねしていたいくらいでした(笑)。
工房の先生の手ほどきに導かれながら、段々と形になってきます。
その土を前にして各自思い思いの器をイメージしながらこねていきす。
私は半年前から茶道を習い始めたので、
せっかくならと、「お抹茶碗」を作ることにしました。
「土をこねる」というのはなんとも気持ちの良いもので……
いつまでもこねこねしていたいくらいでした(笑)。
工房の先生の手ほどきに導かれながら、段々と形になってきます。

私たちのテーブルにはお抹茶碗を作る人が数人集まってましたが、
みんな形は様々。目標は同じなのに、こんなに個性がでるんですね。
なんて面白いんでしょう!
そうこうしながら、第一の目標であるお抹茶碗が完成して、
残った土で2個目の制作にとりかかります。
私は、お抹茶と一緒にお菓子をいただくお皿と、
小さなお香立てをつくりました。
全てが完成したら、次に「色」を決め、そして作品の底に
刻印代わりの1文字を入れてくださるということなので、
名前から1文字を決めて、作品と共に工房の方にお願いしました。
これで約1ヵ月ほど経てば焼き上がり、手元に届けていただけます。
どんな風に出来上がるのか、楽しみ~!!
陶芸は以前から興味がありましたが、なかなか個人で体験することが
できなかったので、今回はほんとにありがたい企画でした。
一度陶芸を経験すると、その魅力にはまる人が多いと聞きますが、
その気持ちがわかりました。
この大覚寺陶房さんは、個人で行っても陶芸体験できるので、
ぜひ興味のある方はお出かけください。工房のみなさんはとても親切で
優しくてアットホームな雰囲気で、初心者には良いと思います。
みんな形は様々。目標は同じなのに、こんなに個性がでるんですね。
なんて面白いんでしょう!
そうこうしながら、第一の目標であるお抹茶碗が完成して、
残った土で2個目の制作にとりかかります。
私は、お抹茶と一緒にお菓子をいただくお皿と、
小さなお香立てをつくりました。
全てが完成したら、次に「色」を決め、そして作品の底に
刻印代わりの1文字を入れてくださるということなので、
名前から1文字を決めて、作品と共に工房の方にお願いしました。
これで約1ヵ月ほど経てば焼き上がり、手元に届けていただけます。
どんな風に出来上がるのか、楽しみ~!!
陶芸は以前から興味がありましたが、なかなか個人で体験することが
できなかったので、今回はほんとにありがたい企画でした。
一度陶芸を経験すると、その魅力にはまる人が多いと聞きますが、
その気持ちがわかりました。
この大覚寺陶房さんは、個人で行っても陶芸体験できるので、
ぜひ興味のある方はお出かけください。工房のみなさんはとても親切で
優しくてアットホームな雰囲気で、初心者には良いと思います。

初めての陶芸を満喫し、ここからは京都散策でもかなりレアな所への
京都さんぽが始まります。
京都さんぽが始まります。

奥嵯峨にある 直指庵 ( じきしあん )へ。
こちらは嵯峨野巡りの中で最も北の奥にあり、なかなか来れない
穴場的名所です。秋には紅葉の名所でもあるように、
今は新緑が素晴らしく爽やかで穏やかなひとときを過ごさせていただきました。
正保3(1646)年、独照性円禅師が草庵を結んだことに始まり、その後、
明の高僧・隠元禅師に黄檗禅を学び、伽藍を建立するなどし、
直指庵は大寺院になりました。その後、次第に寺院は衰退して
荒廃しましたが、幕末の頃、近衛家の老女・津崎村岡局が再興し、
浄土宗の寺院となり、土地の子女の訓育につくし現在に至っています。
村岡局は、昨年の篤姫に登場していたのが記憶に新しいですね。
境内には村岡局のお墓もあります。そして堂内には「想い出草ノート」が
置かれていて、多くの人が思いを綴っておられます。
開け放たれた堂内で自然の香りに包まれながら、思いにひたり
ノートに綴る……ここでしか味わえない時間があります。
今度は一人で訪れてみたいです。
こちらは嵯峨野巡りの中で最も北の奥にあり、なかなか来れない
穴場的名所です。秋には紅葉の名所でもあるように、
今は新緑が素晴らしく爽やかで穏やかなひとときを過ごさせていただきました。
正保3(1646)年、独照性円禅師が草庵を結んだことに始まり、その後、
明の高僧・隠元禅師に黄檗禅を学び、伽藍を建立するなどし、
直指庵は大寺院になりました。その後、次第に寺院は衰退して
荒廃しましたが、幕末の頃、近衛家の老女・津崎村岡局が再興し、
浄土宗の寺院となり、土地の子女の訓育につくし現在に至っています。
村岡局は、昨年の篤姫に登場していたのが記憶に新しいですね。
境内には村岡局のお墓もあります。そして堂内には「想い出草ノート」が
置かれていて、多くの人が思いを綴っておられます。
開け放たれた堂内で自然の香りに包まれながら、思いにひたり
ノートに綴る……ここでしか味わえない時間があります。
今度は一人で訪れてみたいです。

最後に訪れたのは、石仏群が愛らしい 愛宕念仏寺 。
嵯峨の石仏というと、化野念仏寺が頭に浮かぶと思いますが、
こちらは「愛宕(おたぎ)念仏寺」です。
私は以前から気になっていたのですが、機会がなく初めての拝観です。
奥嵯峨の究極の隠れ寺。なんでも山村先生のお気に入りのひとつだそうですよ。
境内に入ると、多くのの石像がお出迎えしてくださいました。
奈良時代に創建された寺院ですが、大正時代にこの地に移築されました。
昭和56年にお寺の興隆を祈念して、境内を羅漢の石像で充満させたい
と発願し、10年がかりで1200体の石像が一般の参拝者の手によって彫られ、
今ここに並んでいるそうです。
羅漢さんはみんな穏やかなお顔で、厳粛な気持ちになるというより
心が和み癒されます。
手をつないだ羅漢さん、お酒を酌み交わされている羅漢さん、
赤ちゃんを抱いた羅漢さん……様々な表情の羅漢さんに
会いに行ってみてはいかがでしょう。
今回の京都さんぽは、私的には初めてのことばかりで魅力溢れる内容でした。
これからの夏の企画も魅力満載です!
らくたびスタッフさん、楽しみにしていま~す。
そうそう楽しみと言えば、焼き上がった陶芸作品が届くのも楽しみですね。
参加者のみなさん、山村先生、若村先生、お疲れさまでした~!
嵯峨の石仏というと、化野念仏寺が頭に浮かぶと思いますが、
こちらは「愛宕(おたぎ)念仏寺」です。
私は以前から気になっていたのですが、機会がなく初めての拝観です。
奥嵯峨の究極の隠れ寺。なんでも山村先生のお気に入りのひとつだそうですよ。
境内に入ると、多くのの石像がお出迎えしてくださいました。
奈良時代に創建された寺院ですが、大正時代にこの地に移築されました。
昭和56年にお寺の興隆を祈念して、境内を羅漢の石像で充満させたい
と発願し、10年がかりで1200体の石像が一般の参拝者の手によって彫られ、
今ここに並んでいるそうです。
羅漢さんはみんな穏やかなお顔で、厳粛な気持ちになるというより
心が和み癒されます。
手をつないだ羅漢さん、お酒を酌み交わされている羅漢さん、
赤ちゃんを抱いた羅漢さん……様々な表情の羅漢さんに
会いに行ってみてはいかがでしょう。
今回の京都さんぽは、私的には初めてのことばかりで魅力溢れる内容でした。
これからの夏の企画も魅力満載です!
らくたびスタッフさん、楽しみにしていま~す。
そうそう楽しみと言えば、焼き上がった陶芸作品が届くのも楽しみですね。
参加者のみなさん、山村先生、若村先生、お疲れさまでした~!
文/らくたび会員 奥村成美様 写真/らくたび会員 岩崎守男様
2009年03月15日
嵐山の伝説めぐりと嵯峨大念仏狂言+お松明
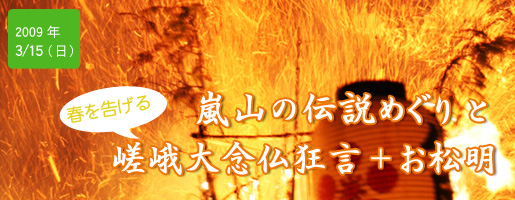
冬のひところと比べると日も随分と長くなり、スタートの17時でもまだまだ明るく、
こんなところからも春の訪れを感じながら嵐電・嵐山駅を出発しました。
こんなところからも春の訪れを感じながら嵐電・嵐山駅を出発しました。

最初に向かったのは 長慶天皇嵯峨東陵 。
初めて聞いたお名前ですが第98代の天皇で南北朝時代の南朝の天皇だそうです。
南北朝時代といいますから、さぞや激動の時代を生きられたことでしょう。
すぐ南隣には 安倍晴明のお墓 があります。そちらへ向かう途中で山村先生が
「今日は皆さんに安倍晴明からプレゼントが届いています」とおっしゃったので
「えっ?何かなぁ?」と期待を膨らませて行ってみると……
なんと桜の花が咲いていました。
もちろん桜の花を見るのはこの春初めて!う~ん、心憎い演出ですね。
安倍晴明は平安時代の陰陽師。当時、天道をつかさどっていた賀茂氏に
弟子入りしそこで才能を開花させた後、村上天皇・花山天皇・一条天皇・
藤原道長などの元で様々な事を予知した伝説を残しています。
墓碑の中央にはおなじみの「五芒星(ごぼうせい)」が刻まれていました。
初めて聞いたお名前ですが第98代の天皇で南北朝時代の南朝の天皇だそうです。
南北朝時代といいますから、さぞや激動の時代を生きられたことでしょう。
すぐ南隣には 安倍晴明のお墓 があります。そちらへ向かう途中で山村先生が
「今日は皆さんに安倍晴明からプレゼントが届いています」とおっしゃったので
「えっ?何かなぁ?」と期待を膨らませて行ってみると……
なんと桜の花が咲いていました。
もちろん桜の花を見るのはこの春初めて!う~ん、心憎い演出ですね。
安倍晴明は平安時代の陰陽師。当時、天道をつかさどっていた賀茂氏に
弟子入りしそこで才能を開花させた後、村上天皇・花山天皇・一条天皇・
藤原道長などの元で様々な事を予知した伝説を残しています。
墓碑の中央にはおなじみの「五芒星(ごぼうせい)」が刻まれていました。

次は渡月橋のたもとから少し歩いた所にある 小督塚 へ向かいました。
『平家物語』の中で悲恋の女性として描かれている小督局。
平清盛により高倉天皇との仲を裂かれ、この地に身を潜めていたところを
高倉天皇の側近であった源仲国により見つけ出された場面は
峯の嵐か松風か、訪ぬる人の琴の音か
駒引き止めて立ち寄れば、爪音高き想夫恋
という歌にもなっています。琴の名手・小督の演奏とそれを聞き分けた
笛の名手・源仲国。
昼間の賑やかな時間帯ではなく静かな夕暮れにあらためてこのお話を
聞くことで、小督の奏でた琴の音を普段よりも少し身近に
感じることができました。
『平家物語』の中で悲恋の女性として描かれている小督局。
平清盛により高倉天皇との仲を裂かれ、この地に身を潜めていたところを
高倉天皇の側近であった源仲国により見つけ出された場面は
峯の嵐か松風か、訪ぬる人の琴の音か
駒引き止めて立ち寄れば、爪音高き想夫恋
という歌にもなっています。琴の名手・小督の演奏とそれを聞き分けた
笛の名手・源仲国。
昼間の賑やかな時間帯ではなく静かな夕暮れにあらためてこのお話を
聞くことで、小督の奏でた琴の音を普段よりも少し身近に
感じることができました。

続いては竹林が美しい小道を通り抜けて 野宮神社 に到着しました。
こちらはかつて伊勢神宮に仕える皇女が伊勢に向かう前に
身を清めた場所です。境内を囲む小柴垣と黒木の鳥居の様子は
『源氏物語』の「賢木」の帖にも書かれています。
縁結びの神様として普段の境内は大盛況ですが、さすがにこの時は
私達だけ。光源氏が秘かに六条御息所を訪ねた心情を
思い浮かべてみるには、このくらいの静けさがいいですね。
こちらはかつて伊勢神宮に仕える皇女が伊勢に向かう前に
身を清めた場所です。境内を囲む小柴垣と黒木の鳥居の様子は
『源氏物語』の「賢木」の帖にも書かれています。
縁結びの神様として普段の境内は大盛況ですが、さすがにこの時は
私達だけ。光源氏が秘かに六条御息所を訪ねた心情を
思い浮かべてみるには、このくらいの静けさがいいですね。

落柿舎 (らくししゃ)は松尾芭蕉の高弟であった向井去来が晩年を過ごしたところです。
「庭の柿を売ろうとしたところ、その夜の大風ですべて実が落ちてしまった」
というのが落柿舎の名前の由来です。
“売ろうとした柿が落ちてしまった”なんていうちょっとマイナス的な出来事を、
あえて遊び心に変えてしまうところがいかにも俳人らしい!
辺りに広がる田園と茅葺屋根の草庵が嵯峨野のひなびた風情を
演出してくれているのですが……
あらら、なんと修復中でした。まぁ、残念がっても仕方がない。
「今しか見られない光景が見られてよかった」ということにしておきましょう……
「庭の柿を売ろうとしたところ、その夜の大風ですべて実が落ちてしまった」
というのが落柿舎の名前の由来です。
“売ろうとした柿が落ちてしまった”なんていうちょっとマイナス的な出来事を、
あえて遊び心に変えてしまうところがいかにも俳人らしい!
辺りに広がる田園と茅葺屋根の草庵が嵯峨野のひなびた風情を
演出してくれているのですが……
あらら、なんと修復中でした。まぁ、残念がっても仕方がない。
「今しか見られない光景が見られてよかった」ということにしておきましょう……

そしてこの後、 清凉寺(嵯峨釈迦堂) へ向かいました。
この日は 嵯峨大念仏狂言 と お松明式 が行われています。
到着したのが大念仏狂言の始まる5分前。すでに座席は満員で立ち見する人、
鐘楼の台に座る人などで溢れていました。
嵯峨大念仏狂言は京都の三大念仏狂言の一つで、
狂言面をつけて演じられる無言劇です。
円覚上人が鎌倉時代に仏教の教えをわかり易く広めるために
始めたそうです。
「釈迦如来」「愛宕詣」「羅城門」など20演目ほどあるらしいのですが、
この時間は「土蜘蛛」が上演されました。
源頼光に命ぜられて渡辺綱と平井保昌が土蜘蛛退治をする物語です。
昨年の秋、私が偶然通りかかった時に練習をしておられた演目でした。
地道な練習や保存活動の上でこうして伝統は守れているんですね。
境内には屋台も立ち並び、美味しそうな匂いもしています。
近所の子供達もとっても楽しそう!
この地で代々親しまれている行事だということを感じました。
この日は 嵯峨大念仏狂言 と お松明式 が行われています。
到着したのが大念仏狂言の始まる5分前。すでに座席は満員で立ち見する人、
鐘楼の台に座る人などで溢れていました。
嵯峨大念仏狂言は京都の三大念仏狂言の一つで、
狂言面をつけて演じられる無言劇です。
円覚上人が鎌倉時代に仏教の教えをわかり易く広めるために
始めたそうです。
「釈迦如来」「愛宕詣」「羅城門」など20演目ほどあるらしいのですが、
この時間は「土蜘蛛」が上演されました。
源頼光に命ぜられて渡辺綱と平井保昌が土蜘蛛退治をする物語です。
昨年の秋、私が偶然通りかかった時に練習をしておられた演目でした。
地道な練習や保存活動の上でこうして伝統は守れているんですね。
境内には屋台も立ち並び、美味しそうな匂いもしています。
近所の子供達もとっても楽しそう!
この地で代々親しまれている行事だということを感じました。

狂言を鑑賞した後は20時半からのお松明式を見学しました。
これは五山の送り火・鞍馬の火祭りに並ぶ京都三大火祭りの一つで
京都に春の到来を告げる行事です。お釈迦様が入滅し荼毘にふされた様子を
境内に立てられた高さ7メートルの大きな松明で表しているそうです。
本堂で法要が営まれた後、僧侶が松明の周りを練り歩き、
長い(ホントに長い)竹竿の様なもので松明に火が灯りました。
松明は3基あり、それぞれが早稲(わせ:稲の中で早く実を結ぶ品種)、
中稲(なかて:早稲と晩生の間で実を結ぶ品種)、
晩生(おくて:比較的遅く実を結ぶ品種)に見立てられ、
かつてはその燃え方で稲作の豊凶を占っていたといいますから、
民衆の暮らしに密着した行事であることがここからもわかります。
点火直前に周辺の屋台の方たちがテントの屋根に水をかけたり、
濡れタオルを被せたりしておられるのを見て
「まさか、ここまで火の粉は飛んでこないやろ~」と思っていたのですが、
点火されるや否や勢いよく燃え上がり、火の粉が舞い散ってきました。
私は初めは張り切って前で見ていたのですが、熱と火の粉が怖くなって
どんどん後ずさりしてしましました。
らくたびレポーター仲間の鴨田さんが火の粉に負けずに撮影された
写真がこちらです。
これは五山の送り火・鞍馬の火祭りに並ぶ京都三大火祭りの一つで
京都に春の到来を告げる行事です。お釈迦様が入滅し荼毘にふされた様子を
境内に立てられた高さ7メートルの大きな松明で表しているそうです。
本堂で法要が営まれた後、僧侶が松明の周りを練り歩き、
長い(ホントに長い)竹竿の様なもので松明に火が灯りました。
松明は3基あり、それぞれが早稲(わせ:稲の中で早く実を結ぶ品種)、
中稲(なかて:早稲と晩生の間で実を結ぶ品種)、
晩生(おくて:比較的遅く実を結ぶ品種)に見立てられ、
かつてはその燃え方で稲作の豊凶を占っていたといいますから、
民衆の暮らしに密着した行事であることがここからもわかります。
点火直前に周辺の屋台の方たちがテントの屋根に水をかけたり、
濡れタオルを被せたりしておられるのを見て
「まさか、ここまで火の粉は飛んでこないやろ~」と思っていたのですが、
点火されるや否や勢いよく燃え上がり、火の粉が舞い散ってきました。
私は初めは張り切って前で見ていたのですが、熱と火の粉が怖くなって
どんどん後ずさりしてしましました。
らくたびレポーター仲間の鴨田さんが火の粉に負けずに撮影された
写真がこちらです。

五山の送り火の印象からか、もっとじっくりと燃える様子を想像していましたが、
実際には7分程で燃え尽きました。何でも見てみないとわからないものですね。
これでこの日の見学はすべて終了です。
今まで夜にこの辺りを歩くことがなかったので気がつきませんでしたが、
清凉寺の境内から星がとてもきれいに見えたことが印象に残っています。
嵐山の山々や川の流れ、静かな竹林、田園風景、人々が集うお寺、
きれいな星空……そんな昔からの風景が守られている嵐山・嵯峨野だからこそ、
ここにまつわる伝説や伝統行事が今も生き生きとしているのだということを
五感で感じることができた京都さんぽとなりました。
ナイトツアーもいいもんですね。ぜひ今後も実施して下さい。
実際には7分程で燃え尽きました。何でも見てみないとわからないものですね。
これでこの日の見学はすべて終了です。
今まで夜にこの辺りを歩くことがなかったので気がつきませんでしたが、
清凉寺の境内から星がとてもきれいに見えたことが印象に残っています。
嵐山の山々や川の流れ、静かな竹林、田園風景、人々が集うお寺、
きれいな星空……そんな昔からの風景が守られている嵐山・嵯峨野だからこそ、
ここにまつわる伝説や伝統行事が今も生き生きとしているのだということを
五感で感じることができた京都さんぽとなりました。
ナイトツアーもいいもんですね。ぜひ今後も実施して下さい。
文/らくたび会員 森明子様 写真/らくたび会員 鴨田一美様
2008年08月23日
化野念仏寺の千灯供養と嵯峨野散策
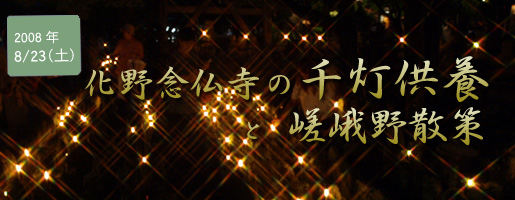
雨が降る夕刻の嵐電嵐山駅で集合です。これだけ降ると
普通ならと中止、なんでしようがそこはらくたびさん企画の京都さんぽ。
ツアーは、もちろん決行です! さすがに夕方で、この雨。
人通りも少なくて、嵯峨野めぐりの竹林道は貸切状態。
でも、雨の嵯峨野も風情がありなかなか良いものです。
普通ならと中止、なんでしようがそこはらくたびさん企画の京都さんぽ。
ツアーは、もちろん決行です! さすがに夕方で、この雨。
人通りも少なくて、嵯峨野めぐりの竹林道は貸切状態。
でも、雨の嵯峨野も風情がありなかなか良いものです。

まずは、最初の目的地、源氏物語「賢木の巻」の舞台となった 野宮神社
に到着。今は、縁結びや子宝安産の神として、毎日多くの人々が訪れる
嵯峨野でも人気のスポットです。特徴のある黒木鳥居は、樹皮がついたままの
クヌギの木をもちいたもので、古代の鳥居の形式と伝えられています。
境内の「野宮じゅうたん苔」が、雨に濡れて緑が濃く美しいです。
に到着。今は、縁結びや子宝安産の神として、毎日多くの人々が訪れる
嵯峨野でも人気のスポットです。特徴のある黒木鳥居は、樹皮がついたままの
クヌギの木をもちいたもので、古代の鳥居の形式と伝えられています。
境内の「野宮じゅうたん苔」が、雨に濡れて緑が濃く美しいです。

次に松尾芭蕉の門下の一人であった向井去来の別荘だった 落柿舎 へ。
いつもここに来るとふと時が止まったように感じます。
のんびりとした昔ながらの風景。前の畑をなんとかこのまま残して
いただきたいものです。 ここでは、山村先生と若村先生の
学生時代のおもしろ?エピソードを聞かせていただきました。
そして、落柿舎の裏手にある向井去来のお墓へ。お墓と言っても
こちらは遺髪塚とか。ほんとうのお墓は真如堂にあるそうです。
いつもここに来るとふと時が止まったように感じます。
のんびりとした昔ながらの風景。前の畑をなんとかこのまま残して
いただきたいものです。 ここでは、山村先生と若村先生の
学生時代のおもしろ?エピソードを聞かせていただきました。
そして、落柿舎の裏手にある向井去来のお墓へ。お墓と言っても
こちらは遺髪塚とか。ほんとうのお墓は真如堂にあるそうです。

雨は降ったり止んだりですが、足下が悪くて
予定のコースへは行けなくて予定変更。ほんとうなら嵯峨野のレアスポットを
案内していただけたようですが、残念。でもこの悪天候は仕方ありませんね。
それでも要所要所で山村先生が口頭でちゃーんと案内してくださいました。
常寂光寺、二尊院、祇王寺、滝口寺、瀬戸内寂聴さんの寂庵など。
そろそろ鳥居本辺りに来ると陽も暮れてきました。
鳥居本への道中には、様々な行灯や提灯が置かれており順々に
ロウソクの火が灯されていきます。今日はこの辺りの地蔵盆で、
結構賑やかな雰囲気です。愛宕神社一の鳥居では地蔵盆の行事が
行われており、たくさんの人が集まっておられました。
予定のコースへは行けなくて予定変更。ほんとうなら嵯峨野のレアスポットを
案内していただけたようですが、残念。でもこの悪天候は仕方ありませんね。
それでも要所要所で山村先生が口頭でちゃーんと案内してくださいました。
常寂光寺、二尊院、祇王寺、滝口寺、瀬戸内寂聴さんの寂庵など。
そろそろ鳥居本辺りに来ると陽も暮れてきました。
鳥居本への道中には、様々な行灯や提灯が置かれており順々に
ロウソクの火が灯されていきます。今日はこの辺りの地蔵盆で、
結構賑やかな雰囲気です。愛宕神社一の鳥居では地蔵盆の行事が
行われており、たくさんの人が集まっておられました。

ここ 化野念仏寺 は、弘仁2(811)年弘法大師・空海が
化野の風葬の惨めさを知り、五智如来寺を建て人々に土葬という
埋葬を教えたのがはじまりといわれています。のち法然上人が
ここに念仏道場を作った事から念仏寺というようになりました。
昔の京の三葬送地は「蓮台野」「鳥辺野」そしてここ「化野」です。
そして明治36年に嵯峨野周辺にあった無縁仏がここに集められて、
8000体もの無縁の石仏や石塔が並んでいるというわけです。
この無縁仏を供養したのが、千灯供養の始まりと言われています。
化野の風葬の惨めさを知り、五智如来寺を建て人々に土葬という
埋葬を教えたのがはじまりといわれています。のち法然上人が
ここに念仏道場を作った事から念仏寺というようになりました。
昔の京の三葬送地は「蓮台野」「鳥辺野」そしてここ「化野」です。
そして明治36年に嵯峨野周辺にあった無縁仏がここに集められて、
8000体もの無縁の石仏や石塔が並んでいるというわけです。
この無縁仏を供養したのが、千灯供養の始まりと言われています。

境内の「西院(さい)の河原」は、多くのロウソクの火が灯もり
幻想的な雰囲気です。参拝者は皆ロウソクを手にし境内に入り、思い思いの
石仏にロウソクを立て静かに手を合わせて祈ります。無縁の仏さんたちも、
多くの人々に祈られて今では寂しくないでしょうね。
今日は千灯供養や、地蔵盆で賑やかですが、普段は静かで人気も少なく
いかにも化野といった時が流れています。そんな普段の化野に
ゆっくりと訪れてみてはいかがですか。
秋の紅葉のころにも、風情があって良いと思います。
この化野念仏寺の千灯供養へは、一人で来るのはかなり勇気が
いるような気がしていました。
このようなツアーをらくたびさんが組んでくださり感謝しています。
ありがとうございました!
幻想的な雰囲気です。参拝者は皆ロウソクを手にし境内に入り、思い思いの
石仏にロウソクを立て静かに手を合わせて祈ります。無縁の仏さんたちも、
多くの人々に祈られて今では寂しくないでしょうね。
今日は千灯供養や、地蔵盆で賑やかですが、普段は静かで人気も少なく
いかにも化野といった時が流れています。そんな普段の化野に
ゆっくりと訪れてみてはいかがですか。
秋の紅葉のころにも、風情があって良いと思います。
この化野念仏寺の千灯供養へは、一人で来るのはかなり勇気が
いるような気がしていました。
このようなツアーをらくたびさんが組んでくださり感謝しています。
ありがとうございました!
文/らくたび会員 奥村成美 写真/らくたび会員 鴨田一美様
2008年05月18日
三船祭と絶景の大悲閣千光寺を訪ねて

絶好の京都さんぽ日和の中、参加者一行は嵐電嵐山駅を出発しました。
始めに天龍寺の南側に建つ平家物語ゆかりの史跡、
小督塚 (こごうづか)へ向かいました。
始めに天龍寺の南側に建つ平家物語ゆかりの史跡、
小督塚 (こごうづか)へ向かいました。

「平氏にあらずんば、人にあらず」
と言われた平家全盛の時代、一族の繁栄を邪魔するものは
徹底的に排除をした平清盛によって、高倉天皇との仲を裂かれた小督が
この場所にひっそりと隠れ住んでいたことが物語に記されています。
嵐山の中心部にありながら、周りの喧騒に染まることなく建つ石塔は、
彼女の悲恋そのものを今に伝えているように思えました。
と言われた平家全盛の時代、一族の繁栄を邪魔するものは
徹底的に排除をした平清盛によって、高倉天皇との仲を裂かれた小督が
この場所にひっそりと隠れ住んでいたことが物語に記されています。
嵐山の中心部にありながら、周りの喧騒に染まることなく建つ石塔は、
彼女の悲恋そのものを今に伝えているように思えました。

続いて渡月橋を渡り 法輪寺 の中に建つ 電電宮 (でんでんぐう)に
立ち寄りました。
この電電宮は電気や電波の安全を祈願する神社で、
主に電気関係者に信仰されている全国でも珍しい神社です。
一見、法輪寺とは何の関係もなさそうに思えますが、
法輪寺のご本尊である虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)にちなみ
こちらに建てられたとのこと。
少々難しい話になりますが……虚空蔵菩薩を感得する為に行う修行、
虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)は、
星の光を受けて得られることから、星、光、電気と繋がって
神社の創建に至ったそうです。
しかし、そういった難しい話はさておき、法輪寺が京都の人々にとって、
非常に親しみのあるお寺であることは間違いありません。
虚空蔵菩薩が「知恵の神様」であることから、昔から数えで13歳になると
「十三参り」としてこのお寺に参拝し、
「大人として生きて行く為に必要な智恵を授かれます様に」
と祈願する風習があるからです。
ですから京都では法輪寺という正式名称より「虚空蔵さん」
あるいは「十三参りのお寺」といった方が馴染みがあるかもしれません。
もちろん私も数十年前(?)に参拝しています。しかし、
当時はそんな深い意味があるとは知らず、帰りに桜餅を食べた記憶しか
残っていません。「もっとちゃんとお願いしておけば良かったなぁ」と
少々反省しつつ法輪寺を後にしました。
立ち寄りました。
この電電宮は電気や電波の安全を祈願する神社で、
主に電気関係者に信仰されている全国でも珍しい神社です。
一見、法輪寺とは何の関係もなさそうに思えますが、
法輪寺のご本尊である虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)にちなみ
こちらに建てられたとのこと。
少々難しい話になりますが……虚空蔵菩薩を感得する為に行う修行、
虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)は、
星の光を受けて得られることから、星、光、電気と繋がって
神社の創建に至ったそうです。
しかし、そういった難しい話はさておき、法輪寺が京都の人々にとって、
非常に親しみのあるお寺であることは間違いありません。
虚空蔵菩薩が「知恵の神様」であることから、昔から数えで13歳になると
「十三参り」としてこのお寺に参拝し、
「大人として生きて行く為に必要な智恵を授かれます様に」
と祈願する風習があるからです。
ですから京都では法輪寺という正式名称より「虚空蔵さん」
あるいは「十三参りのお寺」といった方が馴染みがあるかもしれません。
もちろん私も数十年前(?)に参拝しています。しかし、
当時はそんな深い意味があるとは知らず、帰りに桜餅を食べた記憶しか
残っていません。「もっとちゃんとお願いしておけば良かったなぁ」と
少々反省しつつ法輪寺を後にしました。

次はこの日のメインである 三船祭 の見学です。
三船祭は 車折神社 (くるまざきじんじゃ)の例祭の延長神事で、
毎年5月の第3日曜日に嵐山の大堰川(おおいがわ)において行われます。
車折神社の祭神:清原頼業が乗る御座船の前で、雅楽や日本舞踊、
筝などを披露したり、和歌などを書いた美しい扇を流したりする
風流なお祭で、平安時代の故事をもとに昭和になって再現されました。
千年の昔から一部の人間の私欲に侵されること無く、
変わらず美しい景観を保ってきた嵐山。
人々にとってこの地は現実世界から離れた特別な場所であり、
そんな嵐山であるからこそ再現ができたのでしょう。
ここで1時間の自由行動となり、各自で
平安貴族の優雅な船遊び見学を楽しみました。
三船祭は 車折神社 (くるまざきじんじゃ)の例祭の延長神事で、
毎年5月の第3日曜日に嵐山の大堰川(おおいがわ)において行われます。
車折神社の祭神:清原頼業が乗る御座船の前で、雅楽や日本舞踊、
筝などを披露したり、和歌などを書いた美しい扇を流したりする
風流なお祭で、平安時代の故事をもとに昭和になって再現されました。
千年の昔から一部の人間の私欲に侵されること無く、
変わらず美しい景観を保ってきた嵐山。
人々にとってこの地は現実世界から離れた特別な場所であり、
そんな嵐山であるからこそ再現ができたのでしょう。
ここで1時間の自由行動となり、各自で
平安貴族の優雅な船遊び見学を楽しみました。

再集合をした後は、 大悲閣千光寺 (だいひかくせんこうじ)へと
向いました。三船祭の行われていた一帯は見物客で混雑していましたが、
さすがにこちらへ向う人はありません。
保津川(大堰川)沿いに続く道を進んでいくと
次第に川面を眼下に見下ろすようになり、水の色は山峡の川らしく
深い緑色に変わっていきます。
参道の登り口には松尾芭蕉の句碑が建ち
花の山 二町のぼれば大悲閣
と刻まれていることから、かつてはこの辺りが「花の山」と
呼ばれていたことがわかります。
つづら折りの石段を登りつめた山の中腹に千光寺は
ひっそりと建っていました。
ご住職さんの明るい笑顔に迎えられ、ここでお寺の説明が始まりました。
お話によると、お寺はもともと清涼寺の近くにあったそうですが、
保津川・高瀬川の開削に力を尽くした角倉了以(すみのくらりょうい)が
「河川の開削工事で命を落とした方々の菩提を弔う為に」と
この地に移したそうです。
その了以の念持仏がご本尊の千手観音菩薩であり、
お祀りされている観音堂を「大悲閣」と呼ぶそうです。
「悲」といっても決して「悲しい」の意味ではなく、仏教の慈悲の「悲」を現し、
「全ての苦しみを抜きたい」という願いが込められているとのことです。
向いました。三船祭の行われていた一帯は見物客で混雑していましたが、
さすがにこちらへ向う人はありません。
保津川(大堰川)沿いに続く道を進んでいくと
次第に川面を眼下に見下ろすようになり、水の色は山峡の川らしく
深い緑色に変わっていきます。
参道の登り口には松尾芭蕉の句碑が建ち
花の山 二町のぼれば大悲閣
と刻まれていることから、かつてはこの辺りが「花の山」と
呼ばれていたことがわかります。
つづら折りの石段を登りつめた山の中腹に千光寺は
ひっそりと建っていました。
ご住職さんの明るい笑顔に迎えられ、ここでお寺の説明が始まりました。
お話によると、お寺はもともと清涼寺の近くにあったそうですが、
保津川・高瀬川の開削に力を尽くした角倉了以(すみのくらりょうい)が
「河川の開削工事で命を落とした方々の菩提を弔う為に」と
この地に移したそうです。
その了以の念持仏がご本尊の千手観音菩薩であり、
お祀りされている観音堂を「大悲閣」と呼ぶそうです。
「悲」といっても決して「悲しい」の意味ではなく、仏教の慈悲の「悲」を現し、
「全ての苦しみを抜きたい」という願いが込められているとのことです。

また、境内にある仏閣からの眺めは素晴らしく、遠くに
東山三十六峰を臨む、まさに絶景です。
秋には紅葉が赤く染まる光景を楽しめそうですので、
とっておきの名所としておきましょう。
美しい景色と爽やかな風のおかげで疲れも吹き飛び、
心が洗われたような気持ちで千光寺を後にし、
この日の京都さんぽは終了となりました。
参加者の方々に感想を聞いてみると、「三船祭を初めて見られた。
来年は船から見たい」、「8月16日の送り火を千光寺から眺めたい」、
「嵐山と言えば“混雑”というイメージだったが、違った面が見られた」
とそれぞれに楽しまれたご様子です。
私自身も通い慣れた嵐山ですが、その魅力を再発見できた一日となりました。
これからも皆様とご一緒にいろいろな京都を楽しんでいきたいと思います。
参加者の皆様、スタッフの皆様、ありがとうございました。
東山三十六峰を臨む、まさに絶景です。
秋には紅葉が赤く染まる光景を楽しめそうですので、
とっておきの名所としておきましょう。
美しい景色と爽やかな風のおかげで疲れも吹き飛び、
心が洗われたような気持ちで千光寺を後にし、
この日の京都さんぽは終了となりました。
参加者の方々に感想を聞いてみると、「三船祭を初めて見られた。
来年は船から見たい」、「8月16日の送り火を千光寺から眺めたい」、
「嵐山と言えば“混雑”というイメージだったが、違った面が見られた」
とそれぞれに楽しまれたご様子です。
私自身も通い慣れた嵐山ですが、その魅力を再発見できた一日となりました。
これからも皆様とご一緒にいろいろな京都を楽しんでいきたいと思います。
参加者の皆様、スタッフの皆様、ありがとうございました。
文/らくたび会員 森明子様 写真/らくたび会員 坂田肇様
2007年09月23日
千代の古道散策と大覚寺・中秋の名月鑑賞

嵐電の 鳴滝駅 という今までで最も小さな駅にて集合しました。

今にも雨が降り出しそうな空模様の中、出発です。
あたりは閑静な住宅街。少しくだっていくと、宮内庁管轄の
お墓の入口に到着。参拝者以外立ち入り禁止の看板の横を抜けて入っていくと、
鬱蒼とした木々が生い茂り、大きな池に囲まれた 文徳天皇陵 がありました。
あまり聞かない名前ですが、清和天皇の父といいますから
平安時代中頃の天皇です。悲運で知られる惟喬親王が
第一皇子ということで藤原氏の勃興してきた時代の天皇ですね。
しかしこんな閑静な住宅街に巨大な天皇陵があろうとは。
知られざる京都をまたひとつ発見しました。
あたりは閑静な住宅街。少しくだっていくと、宮内庁管轄の
お墓の入口に到着。参拝者以外立ち入り禁止の看板の横を抜けて入っていくと、
鬱蒼とした木々が生い茂り、大きな池に囲まれた 文徳天皇陵 がありました。
あまり聞かない名前ですが、清和天皇の父といいますから
平安時代中頃の天皇です。悲運で知られる惟喬親王が
第一皇子ということで藤原氏の勃興してきた時代の天皇ですね。
しかしこんな閑静な住宅街に巨大な天皇陵があろうとは。
知られざる京都をまたひとつ発見しました。

さらに西へ進むと造園をされている庭師さんたちの家々が続きます。
そして交差点に出たところで本日のお目当ての 千代の古道 の石碑が登場。
ここには
嵯峨の山 御幸(みゆき)絶えにし芹川の
千代の古道あとはありけり
と在原行平(在原業平の兄)が詠んだと記されています。
もはや平安中期には古道となっていたということでしょうか。
ここから千代の古道に沿って大覚寺へと向かいます。
歩き始めるとすぐに雨が強く降って来ましたが、
幸運にもバス停と車庫があり、雨宿りができました。
そして交差点に出たところで本日のお目当ての 千代の古道 の石碑が登場。
ここには
嵯峨の山 御幸(みゆき)絶えにし芹川の
千代の古道あとはありけり
と在原行平(在原業平の兄)が詠んだと記されています。
もはや平安中期には古道となっていたということでしょうか。
ここから千代の古道に沿って大覚寺へと向かいます。
歩き始めるとすぐに雨が強く降って来ましたが、
幸運にもバス停と車庫があり、雨宿りができました。

やがて雨は止み、「さざれ石山」の横を通って、
桜守として知られる佐野藤右衛門さんが育てる桜を見ながら、
観月の名所 広沢の池 へ到着。
このころは西日がうっすらとさし、なんとも神々しい風景が目前に広がりました。
桜守として知られる佐野藤右衛門さんが育てる桜を見ながら、
観月の名所 広沢の池 へ到着。
このころは西日がうっすらとさし、なんとも神々しい風景が目前に広がりました。

広沢の池の向こうに美しくそびえる山は遍照寺山といって
神南備(かんなび)山と呼ばれています。
「なび」というのは隠れるという意味があるそうで、神が隠れる、
つまり神様がいる山ということです。たしかに神々しいまでの美しさ。
ちなみに山の名前ともなった遍照寺はちゃんと広沢の池から南に
200mほど下がったところに今もあります。
さてここからが千代の古道がますます往時の雰囲気を偲ばせます。
今は田んぼのあぜ道のようになっていますが、あきらかに嵯峨御所であった
大覚寺に向かって伸びています。
途中、下馬野(げばの)を通過。なるほど、ここで都からやってきた貴族達が
馬を下りたというわけですね。リアルに地名に残っているのがまたすごい。
あたりは夕闇につつまれて、ほんとうにタイムスリップした雰囲気です。
ここで月がでていれば完璧なのでしょうが・・・
残念ながら分厚い雲に覆われているようです。
大覚寺からはいっそう雰囲気をかきたてるかのように
管弦楽の音色が流れてきます。
神南備(かんなび)山と呼ばれています。
「なび」というのは隠れるという意味があるそうで、神が隠れる、
つまり神様がいる山ということです。たしかに神々しいまでの美しさ。
ちなみに山の名前ともなった遍照寺はちゃんと広沢の池から南に
200mほど下がったところに今もあります。
さてここからが千代の古道がますます往時の雰囲気を偲ばせます。
今は田んぼのあぜ道のようになっていますが、あきらかに嵯峨御所であった
大覚寺に向かって伸びています。
途中、下馬野(げばの)を通過。なるほど、ここで都からやってきた貴族達が
馬を下りたというわけですね。リアルに地名に残っているのがまたすごい。
あたりは夕闇につつまれて、ほんとうにタイムスリップした雰囲気です。
ここで月がでていれば完璧なのでしょうが・・・
残念ながら分厚い雲に覆われているようです。
大覚寺からはいっそう雰囲気をかきたてるかのように
管弦楽の音色が流れてきます。

そうしてついに 大覚寺 に到着。夜間拝観時は
大沢の池のところから入ることができます。
ライトアップされた建物の美しさは寺院というよりまさに離宮。
大沢の池に浮かぶ船のチケットは夕方発売するや、早々に売り切れたとか。
大覚寺の宸殿の手前で説明を聞いて、解散となりました。
大沢の池の周囲を散策すると多宝塔がある手前では夜店がでていて
お祭りムードとなっており、みなさん思い思いに、
ゆっくりとくつろいで夜の嵯峨野を満喫されていました。
月は最後まで残念ながら出ませんでしたが、天気も回復し、
いい雰囲気の中で雅な時間を過ごすことができました。
大沢の池のところから入ることができます。
ライトアップされた建物の美しさは寺院というよりまさに離宮。
大沢の池に浮かぶ船のチケットは夕方発売するや、早々に売り切れたとか。
大覚寺の宸殿の手前で説明を聞いて、解散となりました。
大沢の池の周囲を散策すると多宝塔がある手前では夜店がでていて
お祭りムードとなっており、みなさん思い思いに、
ゆっくりとくつろいで夜の嵯峨野を満喫されていました。
月は最後まで残念ながら出ませんでしたが、天気も回復し、
いい雰囲気の中で雅な時間を過ごすことができました。
文/山村純也

