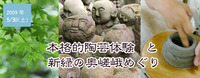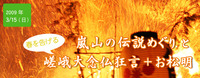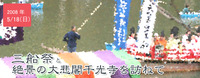2012年05月27日
5月20日(日) 優雅な三船祭と悲恋が残る嵯峨野めぐり
5月20日(日)のらくたび京都さんぽは、新緑の美しい嵐山にて
平安貴族の船遊びを再現した三船祭を見学し、
平安時代に世をしのぶ女性が隠れ住んだ嵯峨野を歩き、
最後は嵯峨祭のお神輿が並ぶ清凉寺前のお旅所を目指して散策しました。
出発は阪急の嵐山駅。三船祭が行われるとあって
人も多めです。まずは法輪寺から。
法輪寺へは階段を上っていきますが、見事な新緑もみじが迎えてくれました!

法輪寺には電電宮というちょっと珍しいお社があり、
電気・電波の神である電電明神が祀られていますよ。

法輪寺からは抜群の眺望を楽しむことができます。
山村先生が、送り火や山々を丁寧に解説して下さいました。
ちょうど三船祭の一行が渡月橋へと向かってくる場面も目撃です!

法輪寺から櫟谷(いちだに)宗像神社を経て、渡月橋まで来ると、
三船祭の牛車が到着していました。

三船祭を見学する前に、小督(こごう)塚に立ち寄りました。
小督局は平安時代、その美貌と琴の音色で高倉天皇に愛された女性でしたが、
娘を高倉天皇の妃としていた平清盛の圧力によって嵯峨野に隠れ住むことになりました。
それでも彼女を探しに来た天皇の使いは、美しい琴の音色から見事に小督を見つけ出したという
ロマンチックな物語があります。

さて、いよいよ三船祭の船遊びが始まりました。車折神社の御祭神も御座船にお乗りになり、
龍頭船では雅な舞が披露されています。時代をタイプスリップしたかのような光景ですね!


私たちも平安時代の船遊びの世界をじっくりと堪能させていただきました。

名残を惜しみつつ三船祭を後にして、嵐山公園を散策します。
保津川を開削した角倉了以(すみのくら りょうい)の像を解説中です。
円山公園の坂本竜馬像・三条大橋の高山彦九郎像と並ぶ
京都三大銅像の一つだそうですよ~!

嵯峨野の美しい竹林も抜けて行きました~!

輝く緑に包まれた野宮神社に到着です。
皮を残したままのクヌギを使った黒木の鳥居が印象的です。

野宮神社は伊勢神宮に奉仕する女性・斎宮が身を清めた場所の一つで、
源氏物語では光源氏と六条御息所の別れの場面で登場します。

嵐山の景色を再現した苔のお庭もありますよ。
橋が渡月橋で奥の灯籠が愛宕山!緑がいっぱいの境内でした。

嵯峨野散策を続けていると、土佐四天王像が現れました!
凛々しい表情をされています。

俳人・向井去来ゆかりの落柿舎(らくししゃ)の前。柿の木も緑の葉を茂らせていました。
辺りは長閑な風景が広がっています。山村先生が落柿舎の名前の由来を面白く解説中です。

桜と紅葉の美しい二尊院の前を経て・・・

祇王寺に到着しました!境内は柔らかい一面の緑に包まれて
「これぞ京都」といった空間です。

祇王寺は、平安時代の白拍子・祇王や仏御前ゆかりのお寺です。
祇王は清盛に気に入られた歌や舞の名手でしたが、仏御前の登場によって捨てられ、
母や妹とともに嵯峨野に隠れ住みました。
やがては仏御前も世を儚んでやってきて、皆で念仏三昧の余生を過ごしました。
境内には祇王のお墓と清盛の供養塔が並んでいます。

最後は、清凉寺の境内を抜けて、野宮神社と愛宕神社のお神輿が置かれている御旅所へ。
別々の神社のお神輿が並んでいるのが面白いですね。

今回の散策は、美しい船遊びに平安の雅を感じ、新緑に包まれた社寺をじっくりと巡りながら
心癒された散策だったのではないでしょうか。山村先生の優しい口調で語られる悲恋の物語も、
柔らかい緑によく似合っていました。気持のよい5月のひと時。
皆様、ご参加頂き本当にありがとうございました。

ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
平安貴族の船遊びを再現した三船祭を見学し、
平安時代に世をしのぶ女性が隠れ住んだ嵯峨野を歩き、
最後は嵯峨祭のお神輿が並ぶ清凉寺前のお旅所を目指して散策しました。
出発は阪急の嵐山駅。三船祭が行われるとあって
人も多めです。まずは法輪寺から。
法輪寺へは階段を上っていきますが、見事な新緑もみじが迎えてくれました!
法輪寺には電電宮というちょっと珍しいお社があり、
電気・電波の神である電電明神が祀られていますよ。
法輪寺からは抜群の眺望を楽しむことができます。
山村先生が、送り火や山々を丁寧に解説して下さいました。
ちょうど三船祭の一行が渡月橋へと向かってくる場面も目撃です!
法輪寺から櫟谷(いちだに)宗像神社を経て、渡月橋まで来ると、
三船祭の牛車が到着していました。
三船祭を見学する前に、小督(こごう)塚に立ち寄りました。
小督局は平安時代、その美貌と琴の音色で高倉天皇に愛された女性でしたが、
娘を高倉天皇の妃としていた平清盛の圧力によって嵯峨野に隠れ住むことになりました。
それでも彼女を探しに来た天皇の使いは、美しい琴の音色から見事に小督を見つけ出したという
ロマンチックな物語があります。
さて、いよいよ三船祭の船遊びが始まりました。車折神社の御祭神も御座船にお乗りになり、
龍頭船では雅な舞が披露されています。時代をタイプスリップしたかのような光景ですね!
私たちも平安時代の船遊びの世界をじっくりと堪能させていただきました。
名残を惜しみつつ三船祭を後にして、嵐山公園を散策します。
保津川を開削した角倉了以(すみのくら りょうい)の像を解説中です。
円山公園の坂本竜馬像・三条大橋の高山彦九郎像と並ぶ
京都三大銅像の一つだそうですよ~!
嵯峨野の美しい竹林も抜けて行きました~!
輝く緑に包まれた野宮神社に到着です。
皮を残したままのクヌギを使った黒木の鳥居が印象的です。
野宮神社は伊勢神宮に奉仕する女性・斎宮が身を清めた場所の一つで、
源氏物語では光源氏と六条御息所の別れの場面で登場します。
嵐山の景色を再現した苔のお庭もありますよ。
橋が渡月橋で奥の灯籠が愛宕山!緑がいっぱいの境内でした。
嵯峨野散策を続けていると、土佐四天王像が現れました!
凛々しい表情をされています。
俳人・向井去来ゆかりの落柿舎(らくししゃ)の前。柿の木も緑の葉を茂らせていました。
辺りは長閑な風景が広がっています。山村先生が落柿舎の名前の由来を面白く解説中です。
桜と紅葉の美しい二尊院の前を経て・・・
祇王寺に到着しました!境内は柔らかい一面の緑に包まれて
「これぞ京都」といった空間です。
祇王寺は、平安時代の白拍子・祇王や仏御前ゆかりのお寺です。
祇王は清盛に気に入られた歌や舞の名手でしたが、仏御前の登場によって捨てられ、
母や妹とともに嵯峨野に隠れ住みました。
やがては仏御前も世を儚んでやってきて、皆で念仏三昧の余生を過ごしました。
境内には祇王のお墓と清盛の供養塔が並んでいます。
最後は、清凉寺の境内を抜けて、野宮神社と愛宕神社のお神輿が置かれている御旅所へ。
別々の神社のお神輿が並んでいるのが面白いですね。
今回の散策は、美しい船遊びに平安の雅を感じ、新緑に包まれた社寺をじっくりと巡りながら
心癒された散策だったのではないでしょうか。山村先生の優しい口調で語られる悲恋の物語も、
柔らかい緑によく似合っていました。気持のよい5月のひと時。
皆様、ご参加頂き本当にありがとうございました。
ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
4/7 王朝の古式ゆかしい嵯峨野めぐり
9月15日 大覚寺「源平ゆかりの寺宝」観賞と京料理
本格的陶芸体験と新緑の奥嵯峨めぐり
嵐山の伝説めぐりと嵯峨大念仏狂言+お松明
化野念仏寺の千灯供養と嵯峨野散策
三船祭と絶景の大悲閣千光寺を訪ねて
9月15日 大覚寺「源平ゆかりの寺宝」観賞と京料理
本格的陶芸体験と新緑の奥嵯峨めぐり
嵐山の伝説めぐりと嵯峨大念仏狂言+お松明
化野念仏寺の千灯供養と嵯峨野散策
三船祭と絶景の大悲閣千光寺を訪ねて