2012年11月26日
11月17日 法性寺・寶樹寺の特別拝観と九条界隈の社寺
11月17日のらくたび京都さんぽは、
特別公開の法性寺・寶樹寺を巡り、
藤原氏ゆかりの社寺が残る九条通界隈を散策しました。

出発は、東福寺駅。紅葉シーズンということもあって
雨の降る空模様ながらも大勢の人で賑わっていました。
まずは、東福寺とは反対側の滝尾神社へ。
今年は辰年ですが、拝殿の天井見事な龍の彫刻があります。
夜な夜な水を飲みに出かけたと伝わるほどの
躍動感のある龍ですよ。

滝尾神社からすぐ近くの寶樹寺へ。非公開文化財特別公開で、
源義経の母・常盤御前ゆかりの薬師如来像と、
雪除松図を見ることが出来ました。

雪除松は、幼い子を抱いて清盛のもとへと向かう常盤御前が、
雪を除けようと身をひそめた松。その根が境内に残されています。

続いては、法性寺へ。
藤原忠平が建立した藤原氏の氏寺の流れをくみ、
数々の兵火をくぐりぬけた国宝の千手観音像が伝わります。
見事な仏像と、迫力ある不動明王像・薬師如来像を鑑賞しました。

お手洗いもかねて東福寺の境内へ。
紅葉シーズンということもあって、境内は大混雑。
でも、若村先生の「青」の服装が目立っているので迷いません!


臥雲橋からは紅葉の雲海が広がっていました。

東福寺を抜けて、九条大橋を越えて藤原氏や
九条家ゆかりの社寺が残る界隈へと向かいます。

新宮神社は、九条家が創建に関わった神社。
今では足止めのご利益があるとして信仰を集めているそうですよ。

九品寺(くほんじ)の辺りは、法然上人の別名・円光大師ゆかりの地。
法然に深く帰依した九条兼実は、自らの九条邸に法然を招き、
帰りに法然を見送ると、法然の背が
円光を放っているのを見たといわれています。

最後は、城興寺と薬院社へ。
平家追討の令旨で知られる以仁王は、城興寺の寺領を有していましたが、
それが平家によって取り上げられてしまったために
追討を決意したとされます。意外なつながりがあるのですね。

今回の散策は非公開文化財を巡り、
東福寺でも少し紅葉を眺めることが出来ました。
街中の小さな社寺にも深い歴史が隠されていて、
らくたびならではの散策だったのではないでしょうか。
終始雨が降る中でしたが、多くの皆様にご参加いただきました。
本当にありがとうございました。
おまけ:薬院社の狛犬が珍しい姿をしていました。

ご案内 / らくたび代表・若村 亮
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
特別公開の法性寺・寶樹寺を巡り、
藤原氏ゆかりの社寺が残る九条通界隈を散策しました。
出発は、東福寺駅。紅葉シーズンということもあって
雨の降る空模様ながらも大勢の人で賑わっていました。
まずは、東福寺とは反対側の滝尾神社へ。
今年は辰年ですが、拝殿の天井見事な龍の彫刻があります。
夜な夜な水を飲みに出かけたと伝わるほどの
躍動感のある龍ですよ。
滝尾神社からすぐ近くの寶樹寺へ。非公開文化財特別公開で、
源義経の母・常盤御前ゆかりの薬師如来像と、
雪除松図を見ることが出来ました。
雪除松は、幼い子を抱いて清盛のもとへと向かう常盤御前が、
雪を除けようと身をひそめた松。その根が境内に残されています。
続いては、法性寺へ。
藤原忠平が建立した藤原氏の氏寺の流れをくみ、
数々の兵火をくぐりぬけた国宝の千手観音像が伝わります。
見事な仏像と、迫力ある不動明王像・薬師如来像を鑑賞しました。
お手洗いもかねて東福寺の境内へ。
紅葉シーズンということもあって、境内は大混雑。
でも、若村先生の「青」の服装が目立っているので迷いません!
臥雲橋からは紅葉の雲海が広がっていました。
東福寺を抜けて、九条大橋を越えて藤原氏や
九条家ゆかりの社寺が残る界隈へと向かいます。
新宮神社は、九条家が創建に関わった神社。
今では足止めのご利益があるとして信仰を集めているそうですよ。
九品寺(くほんじ)の辺りは、法然上人の別名・円光大師ゆかりの地。
法然に深く帰依した九条兼実は、自らの九条邸に法然を招き、
帰りに法然を見送ると、法然の背が
円光を放っているのを見たといわれています。
最後は、城興寺と薬院社へ。
平家追討の令旨で知られる以仁王は、城興寺の寺領を有していましたが、
それが平家によって取り上げられてしまったために
追討を決意したとされます。意外なつながりがあるのですね。
今回の散策は非公開文化財を巡り、
東福寺でも少し紅葉を眺めることが出来ました。
街中の小さな社寺にも深い歴史が隠されていて、
らくたびならではの散策だったのではないでしょうか。
終始雨が降る中でしたが、多くの皆様にご参加いただきました。
本当にありがとうございました。
おまけ:薬院社の狛犬が珍しい姿をしていました。
ご案内 / らくたび代表・若村 亮
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
2012年07月21日
7月8日 天得院・桔梗の庭と特別公開・荷田春満旧宅へ
7月8日(日)のらくたび京都さんぽは、
桔梗咲く東福寺の塔頭・天得院と、東福寺の大伽藍を散策し、
苔の美しい塔頭・光明院を経て、伏見稲荷大社では
特別公開中のお茶屋と荷田春満旧宅を見学しました。
今回は初の試みで、平日の12日にも森先生で同じ散策を実施しました。

出発は京阪の東福寺駅。この日の講師は若村先生

まずは東福寺の境内へと向かいます。こちら万寿寺は、
かつては京都五山にも数えられた名刹でしたが、
現在は東福寺の塔頭の一つとなっています。

境内を歩きながらも若村先生が解説をしてくれます。
今回ならではの光景です!

紅葉で知られる東福寺の通天橋。青い季節も綺麗です。

東福寺の塔頭・天得院に到着しました。桔梗の時期の特別公開です。
境内はまさに桔梗が見ごろを迎え、青や白の涼しげな花を咲かせていました。

参加者も思い思いにお庭を楽しみます。
実は花の中には八重の桔梗もあるそうです!
四葉のクローバーのように、皆さん探しておられました。

天得院の見どころの一つは華頭窓からのお庭。
窓の奥に立つ灯篭も趣を添えてくれます。

今回は少人数ということで、東福寺の大伽藍の一つ一つも
じっくりと若村先生から解説して頂けました。

本堂では堂本印象の天井龍の絵を覗き・・・

禅宗寺院最古の三門を見上げます。

こちらは東司(とうす)。現在の言葉でいうと、お手洗いです。
禅寺ではお手洗いに至るまで細かい作法があり、
自らを律する修行の一部だったそうです。

境内を満喫して、塔頭の光明院へと入ります。
「虹の苔寺」とも呼ばれるほど、ウズマキゴケの緑が見事なお庭です。

そして光明院の特徴はこうして額縁のように
風景を切り取って眺められること。
重森三玲による斬新な立石も絵になりますね。

さらに光明院では丸窓からのお庭を楽しむことが出来ます!
京都らしい風景と癒しに満ちた空間は、時間が経つのを忘れさせてくれます。

光明院を後にして、住宅街を縫うように通り抜けると
そこは伏見稲荷大社のお産婆稲荷でした。
お山巡りをすると最後に訪れるお社で、願いが産まれる場所といわれます。

伏見稲荷では、しめ縄や鳥居の由来について詳しく解説して頂けました。
明快な解説に、参加者の皆さまからも納得の声が聞こえてきます。

伏見稲荷大社の本殿にも参拝します。ちょうど綺麗な青空が広がりました。

そして「京の夏の旅」で特別公開されている、
荷田春満(かだのあずままろ)旧宅へ。
美しい室内からは、伏見稲荷の楼門も綺麗に見えます!
普段は出逢うことのできない光景に感激しました。

本日最後は、伏見稲荷大社のお茶屋です。
江戸時代に後水尾上皇から下賜された貴重な建物。
内部は撮影できないのですが、格式と優雅さを感じさせてくれる
見事な意匠が散りばめられていました。

さて今回は、同じ企画を休日と平日とそれぞれで実施するという初の試みで、
若村先生にはいつも以上にたっぷりと解説して頂けました。
天得院の桔梗は見事に咲き誇り、光明院の苔のお庭も
抜群の美しさで迎えてくれ、最後の伏見稲荷では青空も広がって、
普段は見られない場所を気持ちよく歩くことができましたね!
素敵な散策にご参加頂きまして、ありがとうございました!

ご案内 / らくたび代表・若村 亮
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
桔梗咲く東福寺の塔頭・天得院と、東福寺の大伽藍を散策し、
苔の美しい塔頭・光明院を経て、伏見稲荷大社では
特別公開中のお茶屋と荷田春満旧宅を見学しました。
今回は初の試みで、平日の12日にも森先生で同じ散策を実施しました。
出発は京阪の東福寺駅。この日の講師は若村先生
まずは東福寺の境内へと向かいます。こちら万寿寺は、
かつては京都五山にも数えられた名刹でしたが、
現在は東福寺の塔頭の一つとなっています。
境内を歩きながらも若村先生が解説をしてくれます。
今回ならではの光景です!
紅葉で知られる東福寺の通天橋。青い季節も綺麗です。
東福寺の塔頭・天得院に到着しました。桔梗の時期の特別公開です。
境内はまさに桔梗が見ごろを迎え、青や白の涼しげな花を咲かせていました。
参加者も思い思いにお庭を楽しみます。
実は花の中には八重の桔梗もあるそうです!
四葉のクローバーのように、皆さん探しておられました。
天得院の見どころの一つは華頭窓からのお庭。
窓の奥に立つ灯篭も趣を添えてくれます。
今回は少人数ということで、東福寺の大伽藍の一つ一つも
じっくりと若村先生から解説して頂けました。
本堂では堂本印象の天井龍の絵を覗き・・・
禅宗寺院最古の三門を見上げます。
こちらは東司(とうす)。現在の言葉でいうと、お手洗いです。
禅寺ではお手洗いに至るまで細かい作法があり、
自らを律する修行の一部だったそうです。
境内を満喫して、塔頭の光明院へと入ります。
「虹の苔寺」とも呼ばれるほど、ウズマキゴケの緑が見事なお庭です。
そして光明院の特徴はこうして額縁のように
風景を切り取って眺められること。
重森三玲による斬新な立石も絵になりますね。
さらに光明院では丸窓からのお庭を楽しむことが出来ます!
京都らしい風景と癒しに満ちた空間は、時間が経つのを忘れさせてくれます。
光明院を後にして、住宅街を縫うように通り抜けると
そこは伏見稲荷大社のお産婆稲荷でした。
お山巡りをすると最後に訪れるお社で、願いが産まれる場所といわれます。
伏見稲荷では、しめ縄や鳥居の由来について詳しく解説して頂けました。
明快な解説に、参加者の皆さまからも納得の声が聞こえてきます。
伏見稲荷大社の本殿にも参拝します。ちょうど綺麗な青空が広がりました。
そして「京の夏の旅」で特別公開されている、
荷田春満(かだのあずままろ)旧宅へ。
美しい室内からは、伏見稲荷の楼門も綺麗に見えます!
普段は出逢うことのできない光景に感激しました。
本日最後は、伏見稲荷大社のお茶屋です。
江戸時代に後水尾上皇から下賜された貴重な建物。
内部は撮影できないのですが、格式と優雅さを感じさせてくれる
見事な意匠が散りばめられていました。
さて今回は、同じ企画を休日と平日とそれぞれで実施するという初の試みで、
若村先生にはいつも以上にたっぷりと解説して頂けました。
天得院の桔梗は見事に咲き誇り、光明院の苔のお庭も
抜群の美しさで迎えてくれ、最後の伏見稲荷では青空も広がって、
普段は見られない場所を気持ちよく歩くことができましたね!
素敵な散策にご参加頂きまして、ありがとうございました!
ご案内 / らくたび代表・若村 亮
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
2009年11月08日
伏見稲荷お火焚祭見学と伏見の隠れ寺めぐり

本日の散歩集合は、JR伏見稲荷駅、午後1時。
天候は晴れ、11月というのに「暑い」という言葉の似合う一日でした。
私にとって始めてお目にかかる参加者が多かったことに驚きました。
天候は晴れ、11月というのに「暑い」という言葉の似合う一日でした。
私にとって始めてお目にかかる参加者が多かったことに驚きました。

まずは 大橋家庭園 苔涼庭(たいりょうてい) に向かいます。
ここは、個人のお宅ですが、昭和63年に京都市の名勝に
登録されています。現当主の曾お爺さんの大橋仁兵衛氏が
隠居のために作った家(庭)だそうです。明治の終わりから
作り初めて、大正2年に完成したお庭で、もうすぐ100年になります。
このお庭には、大きな特徴が二つあります。その一つは
京都一古い水琴窟です。昭和50年ごろは、全国で7つ8つ
残っていただけなのですが、テレビに取り上げられるようになり、
その後増えたようです。
最近とみに有名になった妙心寺の退蔵院の水琴窟より
古いものだそうです。
ここは、個人のお宅ですが、昭和63年に京都市の名勝に
登録されています。現当主の曾お爺さんの大橋仁兵衛氏が
隠居のために作った家(庭)だそうです。明治の終わりから
作り初めて、大正2年に完成したお庭で、もうすぐ100年になります。
このお庭には、大きな特徴が二つあります。その一つは
京都一古い水琴窟です。昭和50年ごろは、全国で7つ8つ
残っていただけなのですが、テレビに取り上げられるようになり、
その後増えたようです。
最近とみに有名になった妙心寺の退蔵院の水琴窟より
古いものだそうです。

もう一つは、燈籠の多さです。 この庭は、仁兵衛氏と親戚筋にあった
七代目・小川治兵衛(植治)の設計で作られた庭です。
ただ、仁兵衛氏は石燈籠集めが趣味で、このお庭に12基もの
燈籠が配されています。 「苔涼庭」という名称は、
鮮魚元請をしていた仁兵衛が、親交のあった各地網元の
『大漁』を祈念して名付けたと伝えられています。
七代目・小川治兵衛(植治)の設計で作られた庭です。
ただ、仁兵衛氏は石燈籠集めが趣味で、このお庭に12基もの
燈籠が配されています。 「苔涼庭」という名称は、
鮮魚元請をしていた仁兵衛が、親交のあった各地網元の
『大漁』を祈念して名付けたと伝えられています。

伏見稲荷大社 は、秦氏の一族により和銅4(711)年に創建され、
平成22年に鎮座1300年を迎えます。また全国4万におよぶ
稲荷神社の総本宮です。五条通から南側が伏見稲荷大社の氏神で、
北側が八坂神社の氏神になります。
キツネとお稲荷さんは同一視されたりしますが、
あくまでキツネは「神の使い」だそうです。
キツネは米を食い荒らすネズミを捕ることから、
五穀豊穣と関係しているとか諸説があるそうです。
伏見稲荷と言えば すずめの丸焼き が有名です。
すずめはお米を食べる害鳥なので、それを食ってやろう
というのが、発端らしいのですが、みやげ物店に「すずめ」
の姿がありません。すべてウズラのようです。
「最近は屋根瓦の家が減って、すずめが巣を作りにくくなって
その数が減った」というテレビ報道を見たことがあります。
またすずめは、中国からの輸入に頼っていましたが、
昨今の農薬問題のあおりを食って、入らなくなった
とか聞いたことがあります。それでウズラになったのでしょうか。
私には、いくら美味しくても、あの身近にいる
可愛いすずめを食べるのは忍び難いです。
平成22年に鎮座1300年を迎えます。また全国4万におよぶ
稲荷神社の総本宮です。五条通から南側が伏見稲荷大社の氏神で、
北側が八坂神社の氏神になります。
キツネとお稲荷さんは同一視されたりしますが、
あくまでキツネは「神の使い」だそうです。
キツネは米を食い荒らすネズミを捕ることから、
五穀豊穣と関係しているとか諸説があるそうです。
伏見稲荷と言えば すずめの丸焼き が有名です。
すずめはお米を食べる害鳥なので、それを食ってやろう
というのが、発端らしいのですが、みやげ物店に「すずめ」
の姿がありません。すべてウズラのようです。
「最近は屋根瓦の家が減って、すずめが巣を作りにくくなって
その数が減った」というテレビ報道を見たことがあります。
またすずめは、中国からの輸入に頼っていましたが、
昨今の農薬問題のあおりを食って、入らなくなった
とか聞いたことがあります。それでウズラになったのでしょうか。
私には、いくら美味しくても、あの身近にいる
可愛いすずめを食べるのは忍び難いです。

お火焚祭 (おひたきさい)は、今年一年間の収穫に感謝する行事で、
伏見稲荷大社のものは全国一のスケールということで、
立ち上る炎に圧倒されます。
本殿裏手の斎場に3基の火床を設け、神田でとれた稲のわらを燃やし、
恵みをもたらしてくれた神を山に送ります。
その際、全国から寄せられた約10万本の願い事が書かれた
「火焚き串」を焚き、神楽女の神楽舞が行われます。
伏見稲荷大社のものは全国一のスケールということで、
立ち上る炎に圧倒されます。
本殿裏手の斎場に3基の火床を設け、神田でとれた稲のわらを燃やし、
恵みをもたらしてくれた神を山に送ります。
その際、全国から寄せられた約10万本の願い事が書かれた
「火焚き串」を焚き、神楽女の神楽舞が行われます。

稲荷大社から住宅地の狭い道を南に向かって歩いていくと、
右手に ぬりこべ地蔵 があります。
病気を「塗り込める」ことから「ぬりこべ地蔵」といわれるように
なったそうです。傷口をふさぐ、特に歯痛平癒にご利益があるといわれ、
歯痛が治った人はお堂の格子にお礼の塗り箸を結びつける
という慣わしがあります。6月4日の「虫歯の日」には法要が行われます。
釘抜き地蔵(石像寺)とセットでお参りすると更にご利益があるそうです。
右手に ぬりこべ地蔵 があります。
病気を「塗り込める」ことから「ぬりこべ地蔵」といわれるように
なったそうです。傷口をふさぐ、特に歯痛平癒にご利益があるといわれ、
歯痛が治った人はお堂の格子にお礼の塗り箸を結びつける
という慣わしがあります。6月4日の「虫歯の日」には法要が行われます。
釘抜き地蔵(石像寺)とセットでお参りすると更にご利益があるそうです。

更に南に進むと、左手階段の奥に 石峰寺 の中国風(竜宮造り)の
赤い総門が見えます。
黄檗宗の寺院で、山号は百丈山(ひゅくじょうざん)。
本尊は薬師如来で開山は黄檗六世 千呆性案禅師
(せんがいしょうあんぜんじ)によって創建された寺です。
黄檗宗の禅寺らしく、全体に質素で本堂へ続く龍の背の鱗を表す
平石の参道が印象的です。
また本堂では、「卍くずし」を見ることが出来ます。
ここでは、門前に住んでいた伊藤若冲が奉納した五百羅漢が有名です。
伊藤若冲(1716~1800)は、錦の青物屋の生まれで、
23歳で家督を継いだのですが、絵を描くこと意外に趣味がなく、
39歳で家督を弟に譲りました。
五百羅漢は、釈迦誕生より涅槃に至るまでの一代を物語る
石仏群になっています。 「天上天下唯我独尊」と姿を示す
釈迦誕生仏から始まり、出山釈迦、二十五菩薩来迎石仏や
十八羅漢石仏、釈迦説法の群像、托鉢修行の羅漢の群像、
釈迦涅槃の場面、賽の河原と続いていきます。
毎年9月10日には、若冲忌が開催されています。
没後200年の2000年ごろから、若冲ブームが続いています。
私が伊藤若冲を知ったのは、テレビ番組の「なんでも鑑定団」
だったと記憶しています。若冲と言えば鶏の絵という先入観があります。
赤い総門が見えます。
黄檗宗の寺院で、山号は百丈山(ひゅくじょうざん)。
本尊は薬師如来で開山は黄檗六世 千呆性案禅師
(せんがいしょうあんぜんじ)によって創建された寺です。
黄檗宗の禅寺らしく、全体に質素で本堂へ続く龍の背の鱗を表す
平石の参道が印象的です。
また本堂では、「卍くずし」を見ることが出来ます。
ここでは、門前に住んでいた伊藤若冲が奉納した五百羅漢が有名です。
伊藤若冲(1716~1800)は、錦の青物屋の生まれで、
23歳で家督を継いだのですが、絵を描くこと意外に趣味がなく、
39歳で家督を弟に譲りました。
五百羅漢は、釈迦誕生より涅槃に至るまでの一代を物語る
石仏群になっています。 「天上天下唯我独尊」と姿を示す
釈迦誕生仏から始まり、出山釈迦、二十五菩薩来迎石仏や
十八羅漢石仏、釈迦説法の群像、托鉢修行の羅漢の群像、
釈迦涅槃の場面、賽の河原と続いていきます。
毎年9月10日には、若冲忌が開催されています。
没後200年の2000年ごろから、若冲ブームが続いています。
私が伊藤若冲を知ったのは、テレビ番組の「なんでも鑑定団」
だったと記憶しています。若冲と言えば鶏の絵という先入観があります。

日蓮宗妙顕寺派 深草山(じんそうざん) 宝塔寺 。
平安時代に藤原基経(もとつね)により創建された真言宗極楽寺が前身です。
京都で布教活動を行っていた日蓮宗日像(にちぞう)上人が、
極楽寺住職の良桂(りょうけい)と出会い、数日に渡り論争をしました。
良桂は日像に感服し、宗派を日蓮宗に改めるとともに、
寺名を宝塔寺としました。多宝塔(重要文化財)は市内最古の多宝塔で、
一層目は行基(ぎょうき)葺き、二層目は本瓦葺きで、
永享10(1438)年以前に建立されたものです。
日蓮宗寺院本堂の特徴として、一般観光客は本堂に上ることが
出来なくて、檀家だけが上って使えるとのことです。そういえば、
日蓮宗の寺院の本堂は普段すべて障子が閉められていますね。
京都における日蓮宗の布教活動が凄かったため、
天台宗などからの迫害を受け、応仁の乱に匹敵する被害が出ました。
このことが原因となって、日蓮宗の檀家が多かった
西陣の技術者などは堺へ逃れ、ここで南蛮文化に触れ
多くの文化を吸収し、その後京都に戻ったそうです。
京都といえば碁盤目の街づくりがイメージされますが、
このあたりは、他宗派から攻められる恐れがあるため、
道路が迷路になっていたそうです。今もその面影が残っています。
平安時代に藤原基経(もとつね)により創建された真言宗極楽寺が前身です。
京都で布教活動を行っていた日蓮宗日像(にちぞう)上人が、
極楽寺住職の良桂(りょうけい)と出会い、数日に渡り論争をしました。
良桂は日像に感服し、宗派を日蓮宗に改めるとともに、
寺名を宝塔寺としました。多宝塔(重要文化財)は市内最古の多宝塔で、
一層目は行基(ぎょうき)葺き、二層目は本瓦葺きで、
永享10(1438)年以前に建立されたものです。
日蓮宗寺院本堂の特徴として、一般観光客は本堂に上ることが
出来なくて、檀家だけが上って使えるとのことです。そういえば、
日蓮宗の寺院の本堂は普段すべて障子が閉められていますね。
京都における日蓮宗の布教活動が凄かったため、
天台宗などからの迫害を受け、応仁の乱に匹敵する被害が出ました。
このことが原因となって、日蓮宗の檀家が多かった
西陣の技術者などは堺へ逃れ、ここで南蛮文化に触れ
多くの文化を吸収し、その後京都に戻ったそうです。
京都といえば碁盤目の街づくりがイメージされますが、
このあたりは、他宗派から攻められる恐れがあるため、
道路が迷路になっていたそうです。今もその面影が残っています。

こちらが 茶椀子(ちゃわんこ)の水 の碑です。
都に住む茶人が宇治川の水をくませて茶の湯に用いていました。
ある時、いつものように宇治橋まで水をくみに行った使いの者が、
この近くで水をこぼしてしまいました。仕方なく使いの者は、
このわき水を持ち帰り知らぬ顔をしていました。
主人はいつもの水と違うことに気付き、問いつめました。
使いの者は恐る恐る一部始終を話したところ、
しかられるどころか「宇治川の水に勝る」とほめられ、
その後は宇治までの遠出の労が省けたという伝え話が残っています。
きっと若冲さんも、このわき水で喉を潤していたのでしょうね。
都に住む茶人が宇治川の水をくませて茶の湯に用いていました。
ある時、いつものように宇治橋まで水をくみに行った使いの者が、
この近くで水をこぼしてしまいました。仕方なく使いの者は、
このわき水を持ち帰り知らぬ顔をしていました。
主人はいつもの水と違うことに気付き、問いつめました。
使いの者は恐る恐る一部始終を話したところ、
しかられるどころか「宇治川の水に勝る」とほめられ、
その後は宇治までの遠出の労が省けたという伝え話が残っています。
きっと若冲さんも、このわき水で喉を潤していたのでしょうね。
文・写真/らくたび会員 鴨田一美様
2009年05月04日
稲荷山 千本鳥居登山と新緑の東福寺を歩く

晴天の中、今日は 伏見稲荷登山 です!
私自身、伏見稲荷の奥の院までは来たことがあるのですが、
稲荷山登山は初めてなので、ちょっと不安な状態でスタートしました。
私自身、伏見稲荷の奥の院までは来たことがあるのですが、
稲荷山登山は初めてなので、ちょっと不安な状態でスタートしました。

まずは全員で本殿にて今日の安全を祈願しました。
そして奥の院まで進むとまずは、 おもかる石 ですね!2つの石灯篭があります。
この灯篭の前で願い事を念じて石灯篭の一番上にある丸い石をを持ち上げます。
そのときに感じる重さが、自分が予想していたよりも軽ければ願い事が叶い、
重ければ残念ながら願いは叶い難いということです。
皆さん童心に返ったようにはしゃぎながら、
次々に石を持ち上げておられました(笑)
そして奥の院まで進むとまずは、 おもかる石 ですね!2つの石灯篭があります。
この灯篭の前で願い事を念じて石灯篭の一番上にある丸い石をを持ち上げます。
そのときに感じる重さが、自分が予想していたよりも軽ければ願い事が叶い、
重ければ残念ながら願いは叶い難いということです。
皆さん童心に返ったようにはしゃぎながら、
次々に石を持ち上げておられました(笑)

さあ、いよいよこの後、山頂の一ノ峯の社を目指して登山開始です。
稲荷山の登山入口の鳥居からどんどん進んで行きます。
奥の院までの参道は、整然と鳥居が並んでいますが、ここからの登山道は
鳥居だけでなく、多くの社殿が無数に並んでいます。
歴史が物語るように、昔からここに佇んでいる社殿にはお社を祀ってある他に
石に注連縄を張り祀ってある社殿がたくさんあり驚きました。
登山道は急な傾斜もありますが比較的ゆるやかで、
階段もありますが普通の登山道もあり、思ったより行けそうです(笑)
稲荷山の登山入口の鳥居からどんどん進んで行きます。
奥の院までの参道は、整然と鳥居が並んでいますが、ここからの登山道は
鳥居だけでなく、多くの社殿が無数に並んでいます。
歴史が物語るように、昔からここに佇んでいる社殿にはお社を祀ってある他に
石に注連縄を張り祀ってある社殿がたくさんあり驚きました。
登山道は急な傾斜もありますが比較的ゆるやかで、
階段もありますが普通の登山道もあり、思ったより行けそうです(笑)

景色の良い四ツ辻に到着です。
すでに一汗かいて、市内を一望できる休憩所で一服~。
そよぐ風が心地よかったです。
すでに一汗かいて、市内を一望できる休憩所で一服~。
そよぐ風が心地よかったです。

さあここからが本番。さらに三ノ峯、ニノ峯と登って行き、
山頂が一ノ峯です。一ノ峯に続く参道には、今まで以上に小さな社殿が
次々に現れます。
その社殿の前には、このエリアまで月参りされる方のためにでしょうか、
それぞれ茶店があります。
そこには神様にお供えするためのお供え物がたくさん並んでいます。
ここまでは手ぶらでこられて、茶店でお供え物を購入し、
供えられるのでしょう。この光景は、稲荷山ならではのような気がしました。
どんどん進みます。この辺りは階段がずーっと、ずーっと続きます。
ひたすら登って行き、いよいよ山頂に到着!
さぞかし素晴らしい景色がお出迎え~、と思いきや、
なんと一ノ峯のお社が鎮座する神妙なる聖地でした。
そうか、眺望を楽しむための登山ではないんですよね。
皆さん無事に頂上まで到達しそれぞれ参拝して、いざ下山です。
階段をどんどん下ると、さきほどの四ツ辻に戻ってきて、
ここでまた休憩~。あとは、稲荷大社の社殿には戻らず、
行きとは異なる道を下り次の目的地に向います。
景色のよい箇所をいくつか楽しみながら、
東福寺の辺りまで降りてきました。
山頂が一ノ峯です。一ノ峯に続く参道には、今まで以上に小さな社殿が
次々に現れます。
その社殿の前には、このエリアまで月参りされる方のためにでしょうか、
それぞれ茶店があります。
そこには神様にお供えするためのお供え物がたくさん並んでいます。
ここまでは手ぶらでこられて、茶店でお供え物を購入し、
供えられるのでしょう。この光景は、稲荷山ならではのような気がしました。
どんどん進みます。この辺りは階段がずーっと、ずーっと続きます。
ひたすら登って行き、いよいよ山頂に到着!
さぞかし素晴らしい景色がお出迎え~、と思いきや、
なんと一ノ峯のお社が鎮座する神妙なる聖地でした。
そうか、眺望を楽しむための登山ではないんですよね。
皆さん無事に頂上まで到達しそれぞれ参拝して、いざ下山です。
階段をどんどん下ると、さきほどの四ツ辻に戻ってきて、
ここでまた休憩~。あとは、稲荷大社の社殿には戻らず、
行きとは異なる道を下り次の目的地に向います。
景色のよい箇所をいくつか楽しみながら、
東福寺の辺りまで降りてきました。

登山の後は、東福寺の塔頭・ 光明院 を参拝し、重森三玲氏の作庭
「波心の庭」で至福のひとときです。
ちょうどツツジが見頃を迎えており、素晴らしい美しさです。
観光寺院ではないこの光明院さんでは、季節折々表情の異なるお庭を
ゆっくりと座し拝見できます。秋の紅葉もステキですよ。
「波心の庭」で至福のひとときです。
ちょうどツツジが見頃を迎えており、素晴らしい美しさです。
観光寺院ではないこの光明院さんでは、季節折々表情の異なるお庭を
ゆっくりと座し拝見できます。秋の紅葉もステキですよ。

この後、 東福寺 を参拝し、通天橋を通り青紅葉を楽しんでから、
解散となりました。
今回も老若男女が多数参加しましたが、皆さん無事に
伏見稲荷大社・一ノ峯の社まで到達することができて良かってですね。
これも らくたびさんならではのツアーです。
京都に住んでいながらも、なかなか機会がないと稲荷登山はできないので
良い経験をさせていただきました。ありがとうございました!
そして、皆さんおつかれさまでした!!
解散となりました。
今回も老若男女が多数参加しましたが、皆さん無事に
伏見稲荷大社・一ノ峯の社まで到達することができて良かってですね。
これも らくたびさんならではのツアーです。
京都に住んでいながらも、なかなか機会がないと稲荷登山はできないので
良い経験をさせていただきました。ありがとうございました!
そして、皆さんおつかれさまでした!!
文/奥村成美様 写真/鴨田一美様
2008年10月19日
即成院 二十五菩薩お練供養と東福寺塔頭めぐり
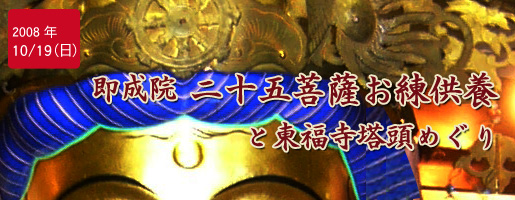
晴天の中、今日はとても有り難い仏教行事を見学させていただきます。
泉涌寺の塔頭・ 即成院 で行なわれる 二十五菩薩お練供養 です。
若村先生の京都講座でも詳しく説明していただいた行事なので、
実際に見学できるこの日を楽しみにしてました!
京阪・東福寺駅に集合し、約15分後に即成院に到着。13:30から始まる
ということでしたが、すでにかなりの人がお越しになってます。
泉涌寺の塔頭・ 即成院 で行なわれる 二十五菩薩お練供養 です。
若村先生の京都講座でも詳しく説明していただいた行事なので、
実際に見学できるこの日を楽しみにしてました!
京阪・東福寺駅に集合し、約15分後に即成院に到着。13:30から始まる
ということでしたが、すでにかなりの人がお越しになってます。

この仏教行事は、本尊の阿弥陀如来が極楽浄土から現世に来迎し、
人々を浄土に導いてくださる姿をあらわしています。
金色の菩薩面を被り、金襴衣装を身につけた25人の信徒が、本堂から
地蔵堂へ架かる高さ2mほど、距離にして約50mほどの橋の上を
練り歩く姿が見どころです。
「二十五菩薩」の登場までに、山伏さん、可愛らしいお稚児さん、
お偉い僧侶、各役員さんなど、かなり多くの人々が、この橋の上を
列になって歩いて行かれました。
その中でもなんと言っても、小さなお稚児さんが可愛かったです!
付き添っておられたお母様、おばあちゃまも綺麗なおべべを
着られていたので、それを見てるのも目の保養になりました(笑)
人々を浄土に導いてくださる姿をあらわしています。
金色の菩薩面を被り、金襴衣装を身につけた25人の信徒が、本堂から
地蔵堂へ架かる高さ2mほど、距離にして約50mほどの橋の上を
練り歩く姿が見どころです。
「二十五菩薩」の登場までに、山伏さん、可愛らしいお稚児さん、
お偉い僧侶、各役員さんなど、かなり多くの人々が、この橋の上を
列になって歩いて行かれました。
その中でもなんと言っても、小さなお稚児さんが可愛かったです!
付き添っておられたお母様、おばあちゃまも綺麗なおべべを
着られていたので、それを見てるのも目の保養になりました(笑)

いよいよ二十五菩薩の登場です。さすがに観音菩薩さんは、貫禄が
あります。お面も衣装も豪華です。その後に、普賢菩薩、文殊菩薩が続き、
次々といろんな楽器や道具を持った菩薩が登場します。
踊りを舞いながら進む菩薩さんもおられます。
100年ほど前の衣装もあるのでしょう、結構小柄な方なので、
中学生くらいがお面を被っているようです。
お面の「目」は、かなり小さい穴らしく前も見にくいのか、
しっかりと付き添いの方が手を取っておられます。
このお練り(=行列)は、本堂から地蔵堂へと3往復されます。
見学している私たちは、ただ行列を見ているだけなのかもしれませんが、
阿弥陀如来さんはここにいる人々を皆、極楽浄土に導いてくださるに
違いありません。今回は、本堂には入れませんでしたが、お堂の中の
「阿弥陀如来と二十五菩薩の極楽浄土の空間」をまだご覧になってない方は、
ぜひお越しになってご覧ください。
お寺の方が、詳しく説明してくださいますよ。
あります。お面も衣装も豪華です。その後に、普賢菩薩、文殊菩薩が続き、
次々といろんな楽器や道具を持った菩薩が登場します。
踊りを舞いながら進む菩薩さんもおられます。
100年ほど前の衣装もあるのでしょう、結構小柄な方なので、
中学生くらいがお面を被っているようです。
お面の「目」は、かなり小さい穴らしく前も見にくいのか、
しっかりと付き添いの方が手を取っておられます。
このお練り(=行列)は、本堂から地蔵堂へと3往復されます。
見学している私たちは、ただ行列を見ているだけなのかもしれませんが、
阿弥陀如来さんはここにいる人々を皆、極楽浄土に導いてくださるに
違いありません。今回は、本堂には入れませんでしたが、お堂の中の
「阿弥陀如来と二十五菩薩の極楽浄土の空間」をまだご覧になってない方は、
ぜひお越しになってご覧ください。
お寺の方が、詳しく説明してくださいますよ。

じっくりと行事を堪能した後、東福寺方面へ。そして、ここでひとつめのサプライズ!
東福寺の塔頭・ 明暗寺 。傘をかぶって尺八を吹きながら
修行される虚無僧さんの「尺八根本道場」で有名だそうです。
こちらは拝観寺院ではありませんが、山門を一歩入ったところにある
「苔庭」が素晴らしい、と山村先生からのディープな案内です!
自然に生え育ってできた苔庭はそんなに広くはないですが、ほんとに
美しかったです。これはほとんどの人が「知らなかった~」と感動!
東福寺に行くお楽しみが、またひとつ増えました。
(※明暗寺の場所は、東福寺北駐車場の東側です。東福寺の境内案内には、
院号の「喜慧院」と掲載されています。)
そして、次は 霊雲院 へ。
こちらには、「九山八海(くせんはっかい)の庭」と「臥雲の庭」の
素敵なお庭があります。「九山八海の庭」は、仏の住む世界は中央に
須弥山(しゅみせん)があって、九つの山と八つの海が取り囲むと
考えられていて、庭中央の遺愛石(=庭の中央にある珍しい形の石塔)
が須弥山、それを取り囲む白砂が九山八海をあらわしているそうです。
そして、「臥雲の庭」は、雲と水の美しさを砂であらわしている
モダンなお庭です。いずれのお庭も、近年になって重森三玲氏により
修復されたそうです。
東福寺の塔頭・ 明暗寺 。傘をかぶって尺八を吹きながら
修行される虚無僧さんの「尺八根本道場」で有名だそうです。
こちらは拝観寺院ではありませんが、山門を一歩入ったところにある
「苔庭」が素晴らしい、と山村先生からのディープな案内です!
自然に生え育ってできた苔庭はそんなに広くはないですが、ほんとに
美しかったです。これはほとんどの人が「知らなかった~」と感動!
東福寺に行くお楽しみが、またひとつ増えました。
(※明暗寺の場所は、東福寺北駐車場の東側です。東福寺の境内案内には、
院号の「喜慧院」と掲載されています。)
そして、次は 霊雲院 へ。
こちらには、「九山八海(くせんはっかい)の庭」と「臥雲の庭」の
素敵なお庭があります。「九山八海の庭」は、仏の住む世界は中央に
須弥山(しゅみせん)があって、九つの山と八つの海が取り囲むと
考えられていて、庭中央の遺愛石(=庭の中央にある珍しい形の石塔)
が須弥山、それを取り囲む白砂が九山八海をあらわしているそうです。
そして、「臥雲の庭」は、雲と水の美しさを砂であらわしている
モダンなお庭です。いずれのお庭も、近年になって重森三玲氏により
修復されたそうです。

続いて、 東福寺 の境内を順次「伽藍」「山門」「東司」と説明を伺ってから、
最後の目的地・ 芬陀院 に到着です。こちらの南庭園は雪舟が作庭したと
伝えられ、通称・雪舟寺と言われています。
この鶴亀庭園の出来映えがあまりにも素晴らしく、亀島が夜になると
動き出した!寺の住職が雪舟にこの様を伝えたところ、
亀島が動かないように真ん中に大きな石を立てると、
動かなくなったとか。なんとも不思議なエピソードですね。
確かに亀島には、大きな石がどんっ!と、刺さっていました(笑)。
茶室「図南亭(となんてい)」に続く廊下の横は、重森三玲作庭の東庭
「鶴亀の庭」。ここでも重森三玲氏のお庭が拝見できました。
そして、ここでふたつめのサプライズ!お寺の奥様(?)のご好意から、
お茶とお菓子を頂きました。前日にお寺の法要があり、そのお下がり
ですが・・・・・・と、京都の有名なお菓子をたくさん振舞ってくださいました。
みんなで、ほっこりとするひとときを楽しませていただきました。
ありがとうございました!
今回のツアーで訪れた寺院は、ほぼらくたび文庫に掲載されています。
即成院は、『京の仏像NAVI 』に。東福寺・霊雲院・芬陀院は、
『京の庭NAVI 枯山水庭園編 』に。この寺院に訪れる際には、
ぜひらくたび文庫片手にお越しくださいね。
らくたび文庫を見ながらじっくりお庭を拝見すると、勉強になるし、
楽しさ倍増です!・・・・・・私、経験者です(笑)
年に一度の仏教行事に、個人で来るのもいいけれど、みんなで
ワイワイと言いながら見学するのって、ほんとうに楽しいですね。
またお祭りや、神事を見学するツアーを楽しみにしています。
最後の目的地・ 芬陀院 に到着です。こちらの南庭園は雪舟が作庭したと
伝えられ、通称・雪舟寺と言われています。
この鶴亀庭園の出来映えがあまりにも素晴らしく、亀島が夜になると
動き出した!寺の住職が雪舟にこの様を伝えたところ、
亀島が動かないように真ん中に大きな石を立てると、
動かなくなったとか。なんとも不思議なエピソードですね。
確かに亀島には、大きな石がどんっ!と、刺さっていました(笑)。
茶室「図南亭(となんてい)」に続く廊下の横は、重森三玲作庭の東庭
「鶴亀の庭」。ここでも重森三玲氏のお庭が拝見できました。
そして、ここでふたつめのサプライズ!お寺の奥様(?)のご好意から、
お茶とお菓子を頂きました。前日にお寺の法要があり、そのお下がり
ですが・・・・・・と、京都の有名なお菓子をたくさん振舞ってくださいました。
みんなで、ほっこりとするひとときを楽しませていただきました。
ありがとうございました!
今回のツアーで訪れた寺院は、ほぼらくたび文庫に掲載されています。
即成院は、『京の仏像NAVI 』に。東福寺・霊雲院・芬陀院は、
『京の庭NAVI 枯山水庭園編 』に。この寺院に訪れる際には、
ぜひらくたび文庫片手にお越しくださいね。
らくたび文庫を見ながらじっくりお庭を拝見すると、勉強になるし、
楽しさ倍増です!・・・・・・私、経験者です(笑)
年に一度の仏教行事に、個人で来るのもいいけれど、みんなで
ワイワイと言いながら見学するのって、ほんとうに楽しいですね。
またお祭りや、神事を見学するツアーを楽しみにしています。
文/らくたび会員 奥村成美様 写真/らくたび会員 坂田肇様
2008年03月16日
釈迦涅槃会めぐりの旅

好天に恵まれた3月16日、参加者50人以上というご一行さんでの
ツアーの始まりです。
ツアーの始まりです。

まずは、東福寺駅前の本町通りを北上し、瀧尾神社へ。
創建・由来は不詳ですが、豊臣秀吉の方広寺の大仏殿建立に伴い、
東山七条付近からこの地に移されたとか。
江戸時代中期の貴重な建物で京都市指定有形文化財に指定されています。
一見普通の神社だと思っていましたが、実際は見所いっぱいの神社です。
見所その1、拝殿天井に、なんと!、龍の彫刻が・・・。
立体感のある迫力満点の龍は一見の価値あり!
見所その2、大丸神社。大丸創業者の下村家初代が欠かさずこの瀧尾神社へ
参拝に訪れ、厚い信仰をされていたそうです。
現在も大丸百貨店ゆかりの神社ということから、
境内に大丸百貨店の繁栄を祈る大丸神社があります。
見所その3、安産加護の神様・三嶋神社。
後白河天皇は深く三島神を崇敬され、以来、
皇室の方々も崇拝されているそうで・・・。
秋篠宮様も二度お越しになったそうです。ご利益があって、
紀子様は3人の元気な宮様をご出産なさったのでしょうね。
創建・由来は不詳ですが、豊臣秀吉の方広寺の大仏殿建立に伴い、
東山七条付近からこの地に移されたとか。
江戸時代中期の貴重な建物で京都市指定有形文化財に指定されています。
一見普通の神社だと思っていましたが、実際は見所いっぱいの神社です。
見所その1、拝殿天井に、なんと!、龍の彫刻が・・・。
立体感のある迫力満点の龍は一見の価値あり!
見所その2、大丸神社。大丸創業者の下村家初代が欠かさずこの瀧尾神社へ
参拝に訪れ、厚い信仰をされていたそうです。
現在も大丸百貨店ゆかりの神社ということから、
境内に大丸百貨店の繁栄を祈る大丸神社があります。
見所その3、安産加護の神様・三嶋神社。
後白河天皇は深く三島神を崇敬され、以来、
皇室の方々も崇拝されているそうで・・・。
秋篠宮様も二度お越しになったそうです。ご利益があって、
紀子様は3人の元気な宮様をご出産なさったのでしょうね。

瀧尾神社を後に、泉涌寺に向かう道中、夢の浮橋跡に立ち寄ります。
その名の通り、ここには昔、川が流れていて、
「夢の浮橋」が架かっていたそうです。
この橋は、歴代の天皇、皇后の墓所が多い泉涌寺に詣でる本道に架けられた橋で、
源氏物語の宇治十帖に因み、この名前がつけられたとか。
風情のある命名です。
その名の通り、ここには昔、川が流れていて、
「夢の浮橋」が架かっていたそうです。
この橋は、歴代の天皇、皇后の墓所が多い泉涌寺に詣でる本道に架けられた橋で、
源氏物語の宇治十帖に因み、この名前がつけられたとか。
風情のある命名です。

さあ、泉涌寺道のゆるやかな坂を上り、即成院へと思ったら・・・
その前に、何やら墓地へ。
そこは、戒光寺の墓地。ここには新選組・伊東甲子太郎・藤堂平助の
お墓があると、柵の前で山村先生の説明です。
今までは、いつでも参拝できたのだけれど、最近は訪れる方が多くなり、
立ち入り禁止だそうです。なんて、マニアックな情報なんでしょう。
隣りの即成院では、本堂で何やら勤行が行われていますので、
中には入れません。阿弥陀如来像と二十五菩薩像を拝見することができず、
ちょっと残念。
即成院のもうひとつの見所は、「那須与一のお墓」です。
お墓は本堂を通らないと行けませんので、今回はお参りできないですが、
代わりに、弓の名手「那須与一」のエピソードを
山村先生が熱く語ってくださいます。
源氏の歴史を左右するターニングポイントの人物でもあったという、
とっても興味深いお話です。
そのまま即成院境内の横道を上ると、戒光寺です。
堂内いっぱいに鎮座されている身代わりのお釈迦様。
「丈六釈迦如来像・丈六さん」運慶・湛慶親子の合作です。
後水尾天皇の身代わりに首を切られて、その時の血の跡が今も残っている・・・
ほんとに、血の跡がはっきりと見えます!
とっても大きなお釈迦様は、とても優しいお顔で、
拝見しているだけで心が安らかに。
ここでは、若村先生が丈六さんの詳しい説明をしてくださいます。
こちらでは多くの参拝者が数珠をご購入なさるそうです!
この数珠、親玉の中に「丈六釈迦如来」が描かれており、
いつの間にかこの如来像が消えることがあるそうです。
その時は、自らに何か災いが起こっていて、その災いを
「丈六釈迦如来」が身代りになって受けて下さったということなんですよ!
これは不思議! もちろん私も丈六さんに守っていただいてます。
その前に、何やら墓地へ。
そこは、戒光寺の墓地。ここには新選組・伊東甲子太郎・藤堂平助の
お墓があると、柵の前で山村先生の説明です。
今までは、いつでも参拝できたのだけれど、最近は訪れる方が多くなり、
立ち入り禁止だそうです。なんて、マニアックな情報なんでしょう。
隣りの即成院では、本堂で何やら勤行が行われていますので、
中には入れません。阿弥陀如来像と二十五菩薩像を拝見することができず、
ちょっと残念。
即成院のもうひとつの見所は、「那須与一のお墓」です。
お墓は本堂を通らないと行けませんので、今回はお参りできないですが、
代わりに、弓の名手「那須与一」のエピソードを
山村先生が熱く語ってくださいます。
源氏の歴史を左右するターニングポイントの人物でもあったという、
とっても興味深いお話です。
そのまま即成院境内の横道を上ると、戒光寺です。
堂内いっぱいに鎮座されている身代わりのお釈迦様。
「丈六釈迦如来像・丈六さん」運慶・湛慶親子の合作です。
後水尾天皇の身代わりに首を切られて、その時の血の跡が今も残っている・・・
ほんとに、血の跡がはっきりと見えます!
とっても大きなお釈迦様は、とても優しいお顔で、
拝見しているだけで心が安らかに。
ここでは、若村先生が丈六さんの詳しい説明をしてくださいます。
こちらでは多くの参拝者が数珠をご購入なさるそうです!
この数珠、親玉の中に「丈六釈迦如来」が描かれており、
いつの間にかこの如来像が消えることがあるそうです。
その時は、自らに何か災いが起こっていて、その災いを
「丈六釈迦如来」が身代りになって受けて下さったということなんですよ!
これは不思議! もちろん私も丈六さんに守っていただいてます。

次は、今熊野観音寺へ。西国三十三ヶ所の第十五番。
そして、後白河法皇の頭痛をこの頭痛封じの観音さまが
癒してくださったことから、今では「頭の観音さま」だそうです。
昔は、頭痛を治すために、自分の枕を持ってきて
ご祈祷を受けておりましたが、では「枕宝布」ならぬ
枕カバーを販売されています。
そうっ!枕カバーを買って帰って、自分の枕にかければ、頭痛が治る!
なんて合理的なんでしょう~。
そして、後白河法皇の頭痛をこの頭痛封じの観音さまが
癒してくださったことから、今では「頭の観音さま」だそうです。
昔は、頭痛を治すために、自分の枕を持ってきて
ご祈祷を受けておりましたが、では「枕宝布」ならぬ
枕カバーを販売されています。
そうっ!枕カバーを買って帰って、自分の枕にかければ、頭痛が治る!
なんて合理的なんでしょう~。

そして、すぐ側の、来迎院へ。こちらには大石内蔵助良雄が浪人中に
建立した茶室「含翠軒」があります。
今日は、時間の関係で拝観せずに、弘法大師が水脈を見つけられたという
「独鈷水」へと。祠の奥にある窪みにたまった湧き水の水面に、
長い柄杓を差し出してお水を掬います。
2m近くもありそうな、長~い柄杓に皆さん大騒ぎ!
面白い体験ができましたね。
建立した茶室「含翠軒」があります。
今日は、時間の関係で拝観せずに、弘法大師が水脈を見つけられたという
「独鈷水」へと。祠の奥にある窪みにたまった湧き水の水面に、
長い柄杓を差し出してお水を掬います。
2m近くもありそうな、長~い柄杓に皆さん大騒ぎ!
面白い体験ができましたね。

さあっ!これからが今日のメインイベントです!
泉涌寺の日本最大・涅槃図を拝見しましょう~。
本堂に入り、涅槃図を見た瞬間、あまりの大きさに圧倒されます。
お話には伺っていましたけれど、実際にこの目で見たら、
ほんとに大きいこと!
涅槃図には、釈尊入滅の場面が描かれています。
沙羅双樹の下、お釈迦様が右脇を下にして、頭を北に、お顔は西を向き、
両足を軽く重ねて手枕で休まれるお姿。
そのお姿を囲みながら、人や鳥やけだものなど、あらゆる生き物が
嘆き悲しみ泣き伏している光景です。
泉涌寺の涅槃図は、奈良の東大寺に奉納する予定だった程の大きさで、
縦16m、横8mと大きく日本最大。
あまりに大き過ぎて、そのまま掛けることができず、
天井から垂らした掛け軸を、一旦大木で柱に引っ掛けて、
下へ垂らすという工夫が成されています。
それでもまだ高さが足らず、下の方は丸めて土間に置いてあります。
これでいかにこの涅槃図が大きいかがはっきりとわかります。
泉涌寺の日本最大・涅槃図を拝見しましょう~。
本堂に入り、涅槃図を見た瞬間、あまりの大きさに圧倒されます。
お話には伺っていましたけれど、実際にこの目で見たら、
ほんとに大きいこと!
涅槃図には、釈尊入滅の場面が描かれています。
沙羅双樹の下、お釈迦様が右脇を下にして、頭を北に、お顔は西を向き、
両足を軽く重ねて手枕で休まれるお姿。
そのお姿を囲みながら、人や鳥やけだものなど、あらゆる生き物が
嘆き悲しみ泣き伏している光景です。
泉涌寺の涅槃図は、奈良の東大寺に奉納する予定だった程の大きさで、
縦16m、横8mと大きく日本最大。
あまりに大き過ぎて、そのまま掛けることができず、
天井から垂らした掛け軸を、一旦大木で柱に引っ掛けて、
下へ垂らすという工夫が成されています。
それでもまだ高さが足らず、下の方は丸めて土間に置いてあります。
これでいかにこの涅槃図が大きいかがはっきりとわかります。

そして、最後にもうひとつの涅槃図・東福寺へ。
泉涌寺から東福寺への道中は、普通の住宅地を通り抜けて行くので、
迷子になりそう(笑)
今回の涅槃図公開は午後4時までで、無事の到着は4時少し前。
すでに僧侶の方々の手で、涅槃図が降ろされようとしています。
こちらの涅槃図は、珍しい「猫入り涅槃図」。
なんとかその猫だけでも見ないとと、いうことから、
山村先生の大きな声が聞こえてきます!
「あそこの左下の方に猫が居ますよ~」と・・・。
確かに居ます、猫が!と、喜んでいるうちに
涅槃図は降ろされてしまいました。
でもなんとか間に合って良かったですね。
本堂天井の、堂本印象作・雲竜図もしっかりと拝見できて、満足!
(※写真は昨年撮影したものです)
泉涌寺から東福寺への道中は、普通の住宅地を通り抜けて行くので、
迷子になりそう(笑)
今回の涅槃図公開は午後4時までで、無事の到着は4時少し前。
すでに僧侶の方々の手で、涅槃図が降ろされようとしています。
こちらの涅槃図は、珍しい「猫入り涅槃図」。
なんとかその猫だけでも見ないとと、いうことから、
山村先生の大きな声が聞こえてきます!
「あそこの左下の方に猫が居ますよ~」と・・・。
確かに居ます、猫が!と、喜んでいるうちに
涅槃図は降ろされてしまいました。
でもなんとか間に合って良かったですね。
本堂天井の、堂本印象作・雲竜図もしっかりと拝見できて、満足!
(※写真は昨年撮影したものです)
泉涌寺の涅槃図の説明の際に、印象に残った逸話。
お釈迦様が床に伏されたとき、あの世におられるお母様・摩耶夫人が、
元気になって欲しいとお薬を投げられたと。
しかし、願いは叶わず、薬の入った布包みは沙羅双樹の枝にひっかかり
お釈迦様の元へは届かなかったそうです。
お釈迦様の入滅に悲しみ沙羅双樹まで枯れ果てていたのに、
その薬の入った布包みが引っかかった樹だけが、
青々と茂っているのを見て、あの世におられるお母様は
さぞ悲しまれたのでしょうね。
ちょっと切なく悲しい逸話を聞いて、
より興味深く涅槃図を拝見することができました。
今日は立ち寄った社寺も多く、ほんとうに中身の濃い一日となりました。
遠方からお越しの方も多かったですが、きっと満足しておられたと思います。
ありがとうございました!
お釈迦様が床に伏されたとき、あの世におられるお母様・摩耶夫人が、
元気になって欲しいとお薬を投げられたと。
しかし、願いは叶わず、薬の入った布包みは沙羅双樹の枝にひっかかり
お釈迦様の元へは届かなかったそうです。
お釈迦様の入滅に悲しみ沙羅双樹まで枯れ果てていたのに、
その薬の入った布包みが引っかかった樹だけが、
青々と茂っているのを見て、あの世におられるお母様は
さぞ悲しまれたのでしょうね。
ちょっと切なく悲しい逸話を聞いて、
より興味深く涅槃図を拝見することができました。
今日は立ち寄った社寺も多く、ほんとうに中身の濃い一日となりました。
遠方からお越しの方も多かったですが、きっと満足しておられたと思います。
ありがとうございました!
文/らくたび会員 奥村成美様

