2009年02月23日
醍醐寺「五大力さん」と勧修寺「臥龍の老梅」

今年の「京都さんぽ」の特徴は、京都の有名な行事と
寺社の散策の組み合わせにある様で、
今日2月23日は醍醐寺の五大力尊仁王会の見学と、隨心院、勧修寺を巡る企画です。
地下鉄東西線「醍醐」駅を出て、新興住宅街の雰囲気の中を、
東に10分ほど歩いて南北の道(奈良街道)にぶつかった所が 醍醐寺 です。
理源大師聖宝(しょうぼう)が開いた真言宗の寺で、京都府下最古の
国宝の五重塔や、春の桜の美しさで有名な古刹です。
寺社の散策の組み合わせにある様で、
今日2月23日は醍醐寺の五大力尊仁王会の見学と、隨心院、勧修寺を巡る企画です。
地下鉄東西線「醍醐」駅を出て、新興住宅街の雰囲気の中を、
東に10分ほど歩いて南北の道(奈良街道)にぶつかった所が 醍醐寺 です。
理源大師聖宝(しょうぼう)が開いた真言宗の寺で、京都府下最古の
国宝の五重塔や、春の桜の美しさで有名な古刹です。

途中、未だ「餅上げ力奉納」は終わっていないのに、
醍醐寺から駅の方へ帰って行かれる大勢の方々とすれ違いましたが、
山村さんの説明で理由が解りました。
五大力尊仁王会は平安時代より続く厳粛な法要で、僧侶の方が
七日間の前行の後の23日に、国家安泰と国民の幸福を祈願し、
五大力尊を刷った「御影(みえい)」のお札が本日のみ参拝者に
授与されます。これを家の玄関などに貼ると、災難、盗難を
免れる事が出来ると言われています。
この「御影」のお札を頂くのが参拝の本来の目的で、途中すれ違った方々は、
お札を買って目的を果たした方々だったのでした。
醍醐寺から駅の方へ帰って行かれる大勢の方々とすれ違いましたが、
山村さんの説明で理由が解りました。
五大力尊仁王会は平安時代より続く厳粛な法要で、僧侶の方が
七日間の前行の後の23日に、国家安泰と国民の幸福を祈願し、
五大力尊を刷った「御影(みえい)」のお札が本日のみ参拝者に
授与されます。これを家の玄関などに貼ると、災難、盗難を
免れる事が出来ると言われています。
この「御影」のお札を頂くのが参拝の本来の目的で、途中すれ違った方々は、
お札を買って目的を果たした方々だったのでした。

しかし私達(私かな?)の目的は法要のハイライトの「餅上げ力奉納」
の見学です。五大力尊(不動明王など五人の明王の総称)に力を奉納し、
身体堅固などのご利益を授かるというものです。
女性は90kg、男性は150kgの巨大な鏡餅を持ち上げ、
その継続時間を競う競技です。
総門から真っ直ぐ仁王門をくぐり、金堂の前まで来ました。
通常は仁王門で拝観料を払うのですが、本日は無料です。
金堂前の特設舞台上で山伏姿の僧侶が審判として見守る中、
丁度、男性の部が始まったところでした。
ここで30分ほどの自由時間となり、皆さん好きな場所から
楽しく見学されてました。持ち上げの状態に持っていくのが
中々難しい様です。腕の力で持ち上げるのではなく、
体を使って持ち上げるという感じです。
持ち上がってからは、途中1分、2分と経過時間がアナウンスされ、
観客から盛んな拍手が起こります。持ち上げまで行かずに
ギブアップされた方も何人かいました。私達が見ていた中で、
5分少々持ち上げた男性の方がいましたが、後でその方が
男性の部で優勝されたそうです。
何かほのぼのとした気分になった所で醍醐寺を後にしました。
の見学です。五大力尊(不動明王など五人の明王の総称)に力を奉納し、
身体堅固などのご利益を授かるというものです。
女性は90kg、男性は150kgの巨大な鏡餅を持ち上げ、
その継続時間を競う競技です。
総門から真っ直ぐ仁王門をくぐり、金堂の前まで来ました。
通常は仁王門で拝観料を払うのですが、本日は無料です。
金堂前の特設舞台上で山伏姿の僧侶が審判として見守る中、
丁度、男性の部が始まったところでした。
ここで30分ほどの自由時間となり、皆さん好きな場所から
楽しく見学されてました。持ち上げの状態に持っていくのが
中々難しい様です。腕の力で持ち上げるのではなく、
体を使って持ち上げるという感じです。
持ち上がってからは、途中1分、2分と経過時間がアナウンスされ、
観客から盛んな拍手が起こります。持ち上げまで行かずに
ギブアップされた方も何人かいました。私達が見ていた中で、
5分少々持ち上げた男性の方がいましたが、後でその方が
男性の部で優勝されたそうです。
何かほのぼのとした気分になった所で醍醐寺を後にしました。

奈良街道を北に20分ほど歩いて 隨心院 に到着です。
隨心院も真言宗のお寺で仁海僧正が建立した曼荼羅寺に始まる門跡寺院です。
南側の門から入ると、すぐ左手に梅園が広がっていました。
ここの梅は遅咲きで有名なので、未だ殆どが蕾状態でした。ここ隨心院は
小野小町が晩年を過ごした屋敷跡とも言われ、小町ゆかりの史跡として
小町に寄せられたラブレターを埋めた「文塚」や
化粧の水を汲んだとされる「化粧の井戸」などを見学しました。
この地に伝わる有名な伝説に、深草少将の「百夜通い」があります。
小町に恋をした深草少将は毎夜自宅から山を越えて、
ここ小野の地の小町の屋敷に通ったのですが、九十九日目に
とうとう力尽きて亡くなってしまいます。哀しいお話ですね。
3月の第4日曜日には小野小町と深草少将に扮した少女らによる
「はねず踊り」が行われます。
その時は、梅園の梅も満開になっている事でしょう。
隨心院も真言宗のお寺で仁海僧正が建立した曼荼羅寺に始まる門跡寺院です。
南側の門から入ると、すぐ左手に梅園が広がっていました。
ここの梅は遅咲きで有名なので、未だ殆どが蕾状態でした。ここ隨心院は
小野小町が晩年を過ごした屋敷跡とも言われ、小町ゆかりの史跡として
小町に寄せられたラブレターを埋めた「文塚」や
化粧の水を汲んだとされる「化粧の井戸」などを見学しました。
この地に伝わる有名な伝説に、深草少将の「百夜通い」があります。
小町に恋をした深草少将は毎夜自宅から山を越えて、
ここ小野の地の小町の屋敷に通ったのですが、九十九日目に
とうとう力尽きて亡くなってしまいます。哀しいお話ですね。
3月の第4日曜日には小野小町と深草少将に扮した少女らによる
「はねず踊り」が行われます。
その時は、梅園の梅も満開になっている事でしょう。

また、仏像に関しても必見のお寺だそうです。理由は、京都では、
何体もの仏像を一堂に見る事の出来るお寺は少ないですが、
隨心院では本尊の如意輪観音の他、快慶や定朝作の
阿弥陀如来坐像、薬師如来坐像などが横一列に並んで配置されており、
すぐ近くでこれらの仏像を見る事が出来るからです。
梅のシーズンには早すぎる為か、境内はほぼ私達の独占状態で、
仏像もゆっくり拝観できました。如意輪観音像には惹かれました。
何体もの仏像を一堂に見る事の出来るお寺は少ないですが、
隨心院では本尊の如意輪観音の他、快慶や定朝作の
阿弥陀如来坐像、薬師如来坐像などが横一列に並んで配置されており、
すぐ近くでこれらの仏像を見る事が出来るからです。
梅のシーズンには早すぎる為か、境内はほぼ私達の独占状態で、
仏像もゆっくり拝観できました。如意輪観音像には惹かれました。

最後の目的地の勧修寺に向かう途中、大きな 榧の木 が有りました。
小野小町が深草少将が通った日数を数える為に使った榧の実が、
こんな立派な木に成長したという事です。
山村さんの説明を聞いて、皆さん「ウアァー」と感嘆の声をあげていました。
小野小町が深草少将が通った日数を数える為に使った榧の実が、
こんな立派な木に成長したという事です。
山村さんの説明を聞いて、皆さん「ウアァー」と感嘆の声をあげていました。

勧修寺 (かじゅうじ)は、醍醐天皇が母である藤原胤子(いんし)の菩提を
弔うために建立したお寺で、ここも真言宗の門跡寺院です。
今回の目的は「臥龍の老梅」の見学です。臥龍の老梅は、
書院前にある親子孫の3代から成る珍しい白梅です。
親は根の部分、子は枯れ木でつながり、そこから孫の木が
今花をつけています。ちょっと時期が遅かった様ですが、
健気に頑張って咲いていました。すぐ近くに水戸光圀寄贈の
変わった形をした「勧修寺型燈籠」も有り、その周りを
樹齢750年と伝わる「這柏槙(はいびゃくしん)」が覆ってます。
境内の大半を占めるのは、平安時代の作庭と伝えられている
「氷室の池」を中心とする庭園です。
平安時代には、ここに張った氷を宮中に献上してその厚さによって
五穀豊穣を占ったそうです。
又、初夏から夏にかけて、カキツバタ、睡蓮、蓮などが咲き、
花の寺としても有名です。
が、今日はオフシーズン。何も咲いてない真冬の池を、
参加者一同で楽しく周遊しました。
今回は、ちょっと歩きましたが、皆さん全然疲れた様子もなく
地下鉄小野駅で解散となりました。
参加者の皆さん、らくたびさん、お疲れ様でした。
弔うために建立したお寺で、ここも真言宗の門跡寺院です。
今回の目的は「臥龍の老梅」の見学です。臥龍の老梅は、
書院前にある親子孫の3代から成る珍しい白梅です。
親は根の部分、子は枯れ木でつながり、そこから孫の木が
今花をつけています。ちょっと時期が遅かった様ですが、
健気に頑張って咲いていました。すぐ近くに水戸光圀寄贈の
変わった形をした「勧修寺型燈籠」も有り、その周りを
樹齢750年と伝わる「這柏槙(はいびゃくしん)」が覆ってます。
境内の大半を占めるのは、平安時代の作庭と伝えられている
「氷室の池」を中心とする庭園です。
平安時代には、ここに張った氷を宮中に献上してその厚さによって
五穀豊穣を占ったそうです。
又、初夏から夏にかけて、カキツバタ、睡蓮、蓮などが咲き、
花の寺としても有名です。
が、今日はオフシーズン。何も咲いてない真冬の池を、
参加者一同で楽しく周遊しました。
今回は、ちょっと歩きましたが、皆さん全然疲れた様子もなく
地下鉄小野駅で解散となりました。
参加者の皆さん、らくたびさん、お疲れ様でした。
文・写真/らくたび会員 坂田肇様
2009年02月11日
城南宮七草粥と安楽寿院特別
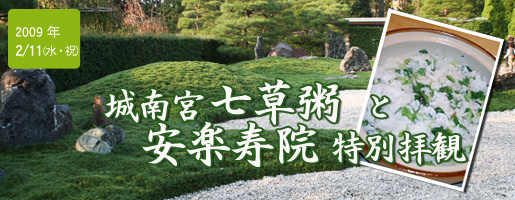
集合場所の近鉄竹田駅には30人を超える参加者が集まり、
久々に大所帯となりました。
12世紀から14世紀頃にかけてこの辺りには「鳥羽離宮」と呼ばれる
代々の上皇に使用された院御所があり、白河・鳥羽・後白河の3代の
院政の舞台となりました。
鳥羽離宮は、南殿・泉殿・北殿・馬場殿・東殿・田中殿などからなり、
近鉄竹田駅付近から国道1号線を越える広大な敷地を有していたそうです。
久々に大所帯となりました。
12世紀から14世紀頃にかけてこの辺りには「鳥羽離宮」と呼ばれる
代々の上皇に使用された院御所があり、白河・鳥羽・後白河の3代の
院政の舞台となりました。
鳥羽離宮は、南殿・泉殿・北殿・馬場殿・東殿・田中殿などからなり、
近鉄竹田駅付近から国道1号線を越える広大な敷地を有していたそうです。

鳥羽離宮の造営を始めたのは白河上皇です。
白河上皇は拡張工事を行い最終的には邸内に三重塔を中心とした
安楽寿院を創建します。
12世紀の鳥羽上皇の時代にも造営は繰り返されます。
しかし、鳥羽離宮内の史跡は全く残っておらず
安楽寿院のみが今日まで法灯を守っています。
城南宮へ向かう途中 白河天皇陵 を訪れます。こんな所に
天皇陵があるとは驚きでした。
白河上皇は拡張工事を行い最終的には邸内に三重塔を中心とした
安楽寿院を創建します。
12世紀の鳥羽上皇の時代にも造営は繰り返されます。
しかし、鳥羽離宮内の史跡は全く残っておらず
安楽寿院のみが今日まで法灯を守っています。
城南宮へ向かう途中 白河天皇陵 を訪れます。こんな所に
天皇陵があるとは驚きでした。

城南宮 に到着です。城南宮は古くから方除けの神として信仰集めましたが、
現在は交通安全の神としても有名です。4月と10月には
王朝風俗を再現した曲水の宴が催され多くの観光客で賑わいます。
本殿をお参りの後いよいよ本日のメインである七草粥をいただきます。
現在は交通安全の神としても有名です。4月と10月には
王朝風俗を再現した曲水の宴が催され多くの観光客で賑わいます。
本殿をお参りの後いよいよ本日のメインである七草粥をいただきます。

旧暦の正月7日の伝統行事で1年間の無病息災と延命長寿を
祈願しつついただきます。意外にお茶碗が大きく食べ応えがありましたね。
七草の他にも一口サイズのお餅も入っており非常に美味しくいただきました。
その後、城南宮のそばにある おせき餅本舗 でおせき餅を購入です。
餅の上につぶ餡をのせたもので、白い餅と草餅の2種類があります。
甘いものに目がないワタシですが、つい先ほど七草粥を食べたばかり。
散々迷った挙句購入するのを辞めました。次回訪れる時は必ず・・・・・・
祈願しつついただきます。意外にお茶碗が大きく食べ応えがありましたね。
七草の他にも一口サイズのお餅も入っており非常に美味しくいただきました。
その後、城南宮のそばにある おせき餅本舗 でおせき餅を購入です。
餅の上につぶ餡をのせたもので、白い餅と草餅の2種類があります。
甘いものに目がないワタシですが、つい先ほど七草粥を食べたばかり。
散々迷った挙句購入するのを辞めました。次回訪れる時は必ず・・・・・・

次の目的地は 鳥羽離宮跡公園 です。今は鳥羽離宮の石碑があるだけで
寂しい感じがします。さらに公園内には鳥羽伏見の戦いの石碑もあります。
実はこの付近、幕末に鳥羽伏見の戦いが勃発した場所としても
知られています。鳥羽方面の戦いは鴨川の小枝橋付近。
伏見方面の戦いは御香宮神社付近で始まります。
石碑の前で鳥羽伏見の戦いの経緯を説明する山村さんの口調も
段々と熱を帯びていくのがわかります。
戦場に立っているかのような臨場感たっぷりの説明は圧巻でした!!
寂しい感じがします。さらに公園内には鳥羽伏見の戦いの石碑もあります。
実はこの付近、幕末に鳥羽伏見の戦いが勃発した場所としても
知られています。鳥羽方面の戦いは鴨川の小枝橋付近。
伏見方面の戦いは御香宮神社付近で始まります。
石碑の前で鳥羽伏見の戦いの経緯を説明する山村さんの口調も
段々と熱を帯びていくのがわかります。
戦場に立っているかのような臨場感たっぷりの説明は圧巻でした!!

次は本日のもうひとつのメインであります 安楽寿院 を目指します。
途中、北向山不動院へ立ち寄ります。こちらも鳥羽上皇の勅願により
鳥羽離宮内に創建された寺院です。
そして、安楽寿院へ到着です。京の冬の旅で特別公開をしており、
さらに冬の旅初公開とのこと。特別公開・初公開と聞くと
ワクワクするのはワタシだけでしょうか。
最大の見所は鳥羽上皇の念持仏と伝わる本尊・阿弥陀如来坐像でしょう。
この阿弥陀様はなんと胸に卍が刻まれています。
そのことから「卍の阿弥陀」と呼ばれています。
その他にも、鳥羽法皇像、美福門院像などの寺宝が
特別展示をされております。
最後は雨に降られてしまいましたが、今回も充実した京都さんぽでした。
参加者の皆様、山村さんお疲れ様でした。
途中、北向山不動院へ立ち寄ります。こちらも鳥羽上皇の勅願により
鳥羽離宮内に創建された寺院です。
そして、安楽寿院へ到着です。京の冬の旅で特別公開をしており、
さらに冬の旅初公開とのこと。特別公開・初公開と聞くと
ワクワクするのはワタシだけでしょうか。
最大の見所は鳥羽上皇の念持仏と伝わる本尊・阿弥陀如来坐像でしょう。
この阿弥陀様はなんと胸に卍が刻まれています。
そのことから「卍の阿弥陀」と呼ばれています。
その他にも、鳥羽法皇像、美福門院像などの寺宝が
特別展示をされております。
最後は雨に降られてしまいましたが、今回も充実した京都さんぽでした。
参加者の皆様、山村さんお疲れ様でした。
文/らくたび会員 森田和宏様 写真/らくたび会員 鴨田一美様

