2012年07月29日
7月22日 伏見の名水巡りと伏見稲荷大社・本宮祭
7月22日(土)のらくたび京都さんぽは、
伏見を歩いて史跡や名水を巡り、伏見稲荷大社では
本宮祭で明かりの灯り始めた境内を散策しました。

出発は京阪の中書島駅。今回の講師は山村先生です。

まず向ったのは竜宮造の赤い門が印象的な長建寺。

こちらには閼伽水(あかすい)というお水が。
伏見はかつて「伏水」とも書かれ、
今でも至る所で名水を頂けるポイントがあります!

伏見の特徴的な風景は酒蔵です。
月桂冠の酒蔵が続く美しい街並みを通り抜けていきます。

鳥せい本店さんにも名水の白菊水が湧き、この日も地元の方が並ばれていました。

油掛地蔵へとやってきました。かつて大山崎の油売りが門前で油をこぼし、
残りをお地蔵さんに掛けたところ、商売繁盛したという伝説を
身振り手振りで分かりやすく解説して頂けました。

キザクラカッパカントリーへとやってきました。
お酒に関する資料やお土産も買うことが出来ます。

こちらでは「伏水(ふしみず)」という名水が湧きます。
伏見でおいしいお酒が造られるのもこうした水の力があるからですね!

続いて、月桂冠の旧本店社屋を活用した伏見夢百衆さんにて
皆さんで一服です。伏見の水で入れたコーヒーなどを頂きました。

再び伏見の街を散策へ。こちらはかつてあった遊郭の建物です。
知る人ぞ知るスポットですね。

電車で移動をして伏見稲荷大社へとやってきました。
本宮祭の提灯や燈籠の点灯まで境内を散策します。

商売繁盛のご利益を求めて参拝です!

本殿の横から建築様式を詳しく解説して頂きました。
講師からの説明がないとわからないことばかりです。

千本鳥居には一足先に幻想的な明かりが灯っていました。

こちらは奥社の「おもかる石」。燈籠の上の石を持ち上げて、
予想より重ければ願いは叶いにくく、軽ければ叶うといわれている石です。
皆さんで持ち上げてみました~!

ふたたび千本鳥居を抜けて・・・

お産場稲荷を経て、楼門に戻る頃には明かりが灯り始めていました。

本日はこちらで解散!
明かりが灯り、盆踊りも始まった伏見稲荷は大いに賑わっていました。
今日は伏見をたっぷり楽しんだ一日。冷たくておいしい名水に、
本宮祭の幻想的な明かりが灯る光景は、京都の夏の風物詩です。
ご参加いただきまして、ありがとうございました!
ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
伏見を歩いて史跡や名水を巡り、伏見稲荷大社では
本宮祭で明かりの灯り始めた境内を散策しました。
出発は京阪の中書島駅。今回の講師は山村先生です。
まず向ったのは竜宮造の赤い門が印象的な長建寺。
こちらには閼伽水(あかすい)というお水が。
伏見はかつて「伏水」とも書かれ、
今でも至る所で名水を頂けるポイントがあります!
伏見の特徴的な風景は酒蔵です。
月桂冠の酒蔵が続く美しい街並みを通り抜けていきます。
鳥せい本店さんにも名水の白菊水が湧き、この日も地元の方が並ばれていました。
油掛地蔵へとやってきました。かつて大山崎の油売りが門前で油をこぼし、
残りをお地蔵さんに掛けたところ、商売繁盛したという伝説を
身振り手振りで分かりやすく解説して頂けました。
キザクラカッパカントリーへとやってきました。
お酒に関する資料やお土産も買うことが出来ます。
こちらでは「伏水(ふしみず)」という名水が湧きます。
伏見でおいしいお酒が造られるのもこうした水の力があるからですね!
続いて、月桂冠の旧本店社屋を活用した伏見夢百衆さんにて
皆さんで一服です。伏見の水で入れたコーヒーなどを頂きました。
再び伏見の街を散策へ。こちらはかつてあった遊郭の建物です。
知る人ぞ知るスポットですね。
電車で移動をして伏見稲荷大社へとやってきました。
本宮祭の提灯や燈籠の点灯まで境内を散策します。
商売繁盛のご利益を求めて参拝です!
本殿の横から建築様式を詳しく解説して頂きました。
講師からの説明がないとわからないことばかりです。
千本鳥居には一足先に幻想的な明かりが灯っていました。
こちらは奥社の「おもかる石」。燈籠の上の石を持ち上げて、
予想より重ければ願いは叶いにくく、軽ければ叶うといわれている石です。
皆さんで持ち上げてみました~!
ふたたび千本鳥居を抜けて・・・
お産場稲荷を経て、楼門に戻る頃には明かりが灯り始めていました。
本日はこちらで解散!
明かりが灯り、盆踊りも始まった伏見稲荷は大いに賑わっていました。
今日は伏見をたっぷり楽しんだ一日。冷たくておいしい名水に、
本宮祭の幻想的な明かりが灯る光景は、京都の夏の風物詩です。
ご参加いただきまして、ありがとうございました!
ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
2011年10月07日
9月23日 千姫神輿・特別拝観 と 伏見桃山御陵を訪ねて
御香宮神社拝殿 屋根の下に施されている絢爛豪華な彫刻は必見!

「 千姫の金の神輿特別拝観と伏見桃山御陵を訪ねて 」 が開催されました。
まずは、日本第一安産守護之大神として広く崇められている御香宮神社を参拝。
豊臣秀吉が建てた伏見城の守護神とし、徳川将軍家からも厚い信仰を集め、幕末には、薩摩藩を中心とする官軍の陣地となり、鳥羽・伏見の戦いの最前線となったここ御香宮神社。

御香宮神社 小堀遠州ゆかりの名庭

その歴史深い神社に残る宝物を今回は特別に拝見させていただきました!

見よ! この荘厳豪華な金のお神輿を!
通称「 千姫神輿 」と呼ばれているこのお神輿は、徳川二代将軍・秀忠が長女・千姫の誕生を祝い、御香宮に寄進したものです。

日本一の重さでなんと 2.3t !!
しかし担ぎ手が足らず、昭和36年(1961年)以降担がれていないそうです。

あまりの豪華さに「 おお〜っ!」と参加者の皆さんから驚愕の声が聞こえてきました。たっぷりと拝見させていただき私たちがその場を立ち去ろると・・・すぐに扉が閉じられました。それを見て「ほんとに特別に見せていただいたんやね〜っ!」と今度は喜びの声が聞こえてきました。

さあ、特別拝観を堪能したあとは、天皇陵のご参拝です。
まずは、乃木将軍( 乃木希典 )を祀る乃木神社へ。
明治天皇が崩御され、それに付き従うように夫人と共に殉死されたとは・・・昔の方はすごいなと感心することしかできません。

乃木神社から足を進めて数分、長〜い階段が見えてきました!
この上にある壮大な桃山御陵( 明治天皇陵 )へと向かいます。
このときは皆さんまだまだ余裕たっぷり!

明治天皇陵 階段を登り詰めると、神々しい空気に包まれます。

遥か先には京都市の南端が見えま〜す。

次ぎの天皇陵を目指し、天皇陵の森を進みます。

と、その道中にお城が・・・なんと伏見城です!
もちろん秀吉のお城でも、家康のお城でもありませんが、立派な伏見城です。

2003年までは「 伏見桃山城キャッスルランド 」として京都人にとっては数少ないプレイランドだったんですよ。私もお年頃だったころよく遊びに来ました
現在はこの模擬天守を中心に運動公園や市民の憩いの場となっています。
桜の季節に来たらきっと綺麗でしょうね。
そして平安京を造営された桓武天皇陵の参拝です。
「京に都を遷してくださりありがとうございました」と心に刻みながらいにしえの栄華をしのびました。

天皇陵の参拝を終え、伏見の城下町を歩きました。当時はこのあたりは賑やかだったんでしょうね。そんな城下町にもたくさんのお寺が点在してます。
こちらは伊達政宗の伏見屋敷跡に建つ海寶寺( かいほうじ )。
普茶料理や画家の伊藤若冲ゆかりのお寺としてもよく知られています。

境内には樹齢約400年とも言われている伊達政宗お手植えのモッコクが今でも健在です。

散策も終盤、あとは駅に向かうだけだと思っていたら、ここでサプライズ!
曹洞宗の栄春寺。なんとこちらでは貴重な伏見城の遺構を見ることができるんです!

本堂裏手の墓地には伏見城の土塁が一部残っているんです。

皆さん、 らくたびの ” 京都さんぽ ” だからこそのサプライズに興味津々♪
案内なしでは知ることもなく、もちろん見ることも出来なかったですよね〜。

この小高い墓地から遠くに伏見城が見えました。
お城の位置が少しは変わっていると言えど、伏見城ってこんなに広い敷地だったんですね。
今回の京都さんぽはよく歩きましたが、金の御輿に魅せられ、神妙な気持ちで天皇陵を参拝し、サプライズ的なこともあり満足感溢れる散策となりました。
ご参加いただいたみなさん、お疲れさまでした!
そして、秋本番!
散策が気持ち良い季節です。
次回はお会いすることを楽しみにしてま〜す。
写真/らくたび会員 岩崎 真紀枝様
文・写真/らくたび会員 奥村なるみ

「 千姫の金の神輿特別拝観と伏見桃山御陵を訪ねて 」 が開催されました。
まずは、日本第一安産守護之大神として広く崇められている御香宮神社を参拝。
豊臣秀吉が建てた伏見城の守護神とし、徳川将軍家からも厚い信仰を集め、幕末には、薩摩藩を中心とする官軍の陣地となり、鳥羽・伏見の戦いの最前線となったここ御香宮神社。

御香宮神社 小堀遠州ゆかりの名庭

その歴史深い神社に残る宝物を今回は特別に拝見させていただきました!

見よ! この荘厳豪華な金のお神輿を!
通称「 千姫神輿 」と呼ばれているこのお神輿は、徳川二代将軍・秀忠が長女・千姫の誕生を祝い、御香宮に寄進したものです。

日本一の重さでなんと 2.3t !!
しかし担ぎ手が足らず、昭和36年(1961年)以降担がれていないそうです。

あまりの豪華さに「 おお〜っ!」と参加者の皆さんから驚愕の声が聞こえてきました。たっぷりと拝見させていただき私たちがその場を立ち去ろると・・・すぐに扉が閉じられました。それを見て「ほんとに特別に見せていただいたんやね〜っ!」と今度は喜びの声が聞こえてきました。

さあ、特別拝観を堪能したあとは、天皇陵のご参拝です。
まずは、乃木将軍( 乃木希典 )を祀る乃木神社へ。
明治天皇が崩御され、それに付き従うように夫人と共に殉死されたとは・・・昔の方はすごいなと感心することしかできません。

乃木神社から足を進めて数分、長〜い階段が見えてきました!
この上にある壮大な桃山御陵( 明治天皇陵 )へと向かいます。
このときは皆さんまだまだ余裕たっぷり!

明治天皇陵 階段を登り詰めると、神々しい空気に包まれます。

遥か先には京都市の南端が見えま〜す。

次ぎの天皇陵を目指し、天皇陵の森を進みます。

と、その道中にお城が・・・なんと伏見城です!
もちろん秀吉のお城でも、家康のお城でもありませんが、立派な伏見城です。

2003年までは「 伏見桃山城キャッスルランド 」として京都人にとっては数少ないプレイランドだったんですよ。私もお年頃だったころよく遊びに来ました

現在はこの模擬天守を中心に運動公園や市民の憩いの場となっています。
桜の季節に来たらきっと綺麗でしょうね。
そして平安京を造営された桓武天皇陵の参拝です。
「京に都を遷してくださりありがとうございました」と心に刻みながらいにしえの栄華をしのびました。

天皇陵の参拝を終え、伏見の城下町を歩きました。当時はこのあたりは賑やかだったんでしょうね。そんな城下町にもたくさんのお寺が点在してます。
こちらは伊達政宗の伏見屋敷跡に建つ海寶寺( かいほうじ )。
普茶料理や画家の伊藤若冲ゆかりのお寺としてもよく知られています。

境内には樹齢約400年とも言われている伊達政宗お手植えのモッコクが今でも健在です。

散策も終盤、あとは駅に向かうだけだと思っていたら、ここでサプライズ!
曹洞宗の栄春寺。なんとこちらでは貴重な伏見城の遺構を見ることができるんです!

本堂裏手の墓地には伏見城の土塁が一部残っているんです。

皆さん、 らくたびの ” 京都さんぽ ” だからこそのサプライズに興味津々♪
案内なしでは知ることもなく、もちろん見ることも出来なかったですよね〜。

この小高い墓地から遠くに伏見城が見えました。
お城の位置が少しは変わっていると言えど、伏見城ってこんなに広い敷地だったんですね。
今回の京都さんぽはよく歩きましたが、金の御輿に魅せられ、神妙な気持ちで天皇陵を参拝し、サプライズ的なこともあり満足感溢れる散策となりました。
ご参加いただいたみなさん、お疲れさまでした!
そして、秋本番!
散策が気持ち良い季節です。
次回はお会いすることを楽しみにしてま〜す。
写真/らくたび会員 岩崎 真紀枝様
文・写真/らくたび会員 奥村なるみ
2009年06月14日
藤森神社アジサイ苑と知られざる深草の里めぐり

6月は紫陽花の花が綺麗に色づく季節。
更に日ごとに暑さが増し夏の訪れを感じる季節でもあります。
そんな中京都さんぽが開催されました。
今回は京都・伏見の深草界隈を散策です。JR藤森駅に集合した一行は
初めの目的地である藤森神社を目指します
藤森神社 は創建が平安遷都以前という歴史ある神社です。
菖蒲の節句発祥の地とても知られており、菖蒲が勝負と転じて
勝運と馬の神社として信仰を集めています。
その為、全国から競馬関係者や競馬ファンが訪れています。
その他にも1500坪もの紫陽花苑があり3500株もの紫陽花が植えられています。
更に日ごとに暑さが増し夏の訪れを感じる季節でもあります。
そんな中京都さんぽが開催されました。
今回は京都・伏見の深草界隈を散策です。JR藤森駅に集合した一行は
初めの目的地である藤森神社を目指します
藤森神社 は創建が平安遷都以前という歴史ある神社です。
菖蒲の節句発祥の地とても知られており、菖蒲が勝負と転じて
勝運と馬の神社として信仰を集めています。
その為、全国から競馬関係者や競馬ファンが訪れています。
その他にも1500坪もの紫陽花苑があり3500株もの紫陽花が植えられています。

訪れたこの日は色鮮やかな紫陽花が咲き誇っており、
多くの参拝者で賑わっていました。
しかし、藤森神社の見所はこれだけはありません。まず、
神社南参道前にある鳥居には額がありません。
江戸時代には後水尾天皇御宸筆の額が掲げてあったのですが、
前の道が西国大名の参勤交代の道筋だったので、
各大名は神社前を通る時駕籠から降り拝礼をして、槍などは
穂先を下げて通行していました。
しかし、幕末に悠長なことをしていたのでは時代に即さないとして
新選組の近藤勇が外してしまったと言われています。
後水尾天皇御宸筆の額を外すとはさすがは近藤勇!!
因みに西側の鳥居にはちゃんと額が掲げられています。
多くの参拝者で賑わっていました。
しかし、藤森神社の見所はこれだけはありません。まず、
神社南参道前にある鳥居には額がありません。
江戸時代には後水尾天皇御宸筆の額が掲げてあったのですが、
前の道が西国大名の参勤交代の道筋だったので、
各大名は神社前を通る時駕籠から降り拝礼をして、槍などは
穂先を下げて通行していました。
しかし、幕末に悠長なことをしていたのでは時代に即さないとして
新選組の近藤勇が外してしまったと言われています。
後水尾天皇御宸筆の額を外すとはさすがは近藤勇!!
因みに西側の鳥居にはちゃんと額が掲げられています。

次は手水鉢。この手水鉢の台石があの石川五右衛門の寄進!?
だと言われているのです。それも宇治浮島の十三重塔の五番目を持ってきた
と言われており、その部分だけ色が違っているのがわかるそうです。
本当に色が違うかどうかはご自分の眼でお確かめ下さい。
因みにワタシはさんぽ終了後気になる方と確認に行きました。色は……
だと言われているのです。それも宇治浮島の十三重塔の五番目を持ってきた
と言われており、その部分だけ色が違っているのがわかるそうです。
本当に色が違うかどうかはご自分の眼でお確かめ下さい。
因みにワタシはさんぽ終了後気になる方と確認に行きました。色は……

一行は京阪電車を超えて 墨染寺と 欣浄寺 を目指します。
墨染寺の通称は「桜寺」。読み方は「ぼくせんじ」です。
名前の由来は平安時代に藤原基経の死を悲しんだ歌人上野峯雄が
深草の野辺の桜も心あらば今年ばかりは墨染に咲け
と詠んだところ、桜が薄墨色になったとの伝説により墨染寺と
名付けられました。現在は三代目の墨染桜が境内に植えられています。
実際には初めは真っ白に咲き、その後次第に墨色を帯びてきます。
墨染寺の通称は「桜寺」。読み方は「ぼくせんじ」です。
名前の由来は平安時代に藤原基経の死を悲しんだ歌人上野峯雄が
深草の野辺の桜も心あらば今年ばかりは墨染に咲け
と詠んだところ、桜が薄墨色になったとの伝説により墨染寺と
名付けられました。現在は三代目の墨染桜が境内に植えられています。
実際には初めは真っ白に咲き、その後次第に墨色を帯びてきます。

墨染寺の真裏に位置する欣浄寺は道元禅師が創建した曹洞宗のお寺です。
この欣浄寺は百夜通いで知られている深草少将の屋敷があった場所
とされています。その為、境内には深草少将と小野小町の塚や、
涙の水とも呼ばれる「墨染の井戸」があります。
御本尊は伏見の大仏として親しまれている昆盧舎那仏です。高さが5.3mもあり
近くで見るとその迫力に圧倒されます。本堂は中二階になっており
お参りすると丁度目が合う造りとなっています。
さらに小野小町の恋文の灰を固めて作られたと言われる
深草少将張文像が安置されています。
欣浄寺を後にした一行は撞木町から墨染インクラインを歩きます。
撞木町は江戸時代に栄えた遊郭で当時を偲ぶものは石碑しか残っていません。
ここは忠臣蔵の大石内蔵助が通っていた所でもあります。
史実では祇園一力亭ではなくこちらに通っていたとされています。
墨染インクラインは昭和35年に完全撤去され今は発電所しか残っていません。
実はこの疏水沿いは桜が非常に綺麗で、墨染寺と共に隠れた桜の名所でもあります。
京阪墨染駅に戻り本日の京都さんぽは終了です。
夏を思わせる日差しの中思った以上に日焼けをしてしまいました(笑)
この欣浄寺は百夜通いで知られている深草少将の屋敷があった場所
とされています。その為、境内には深草少将と小野小町の塚や、
涙の水とも呼ばれる「墨染の井戸」があります。
御本尊は伏見の大仏として親しまれている昆盧舎那仏です。高さが5.3mもあり
近くで見るとその迫力に圧倒されます。本堂は中二階になっており
お参りすると丁度目が合う造りとなっています。
さらに小野小町の恋文の灰を固めて作られたと言われる
深草少将張文像が安置されています。
欣浄寺を後にした一行は撞木町から墨染インクラインを歩きます。
撞木町は江戸時代に栄えた遊郭で当時を偲ぶものは石碑しか残っていません。
ここは忠臣蔵の大石内蔵助が通っていた所でもあります。
史実では祇園一力亭ではなくこちらに通っていたとされています。
墨染インクラインは昭和35年に完全撤去され今は発電所しか残っていません。
実はこの疏水沿いは桜が非常に綺麗で、墨染寺と共に隠れた桜の名所でもあります。
京阪墨染駅に戻り本日の京都さんぽは終了です。
夏を思わせる日差しの中思った以上に日焼けをしてしまいました(笑)
文/らくたび会員 森田和宏様
2009年02月11日
城南宮七草粥と安楽寿院特別
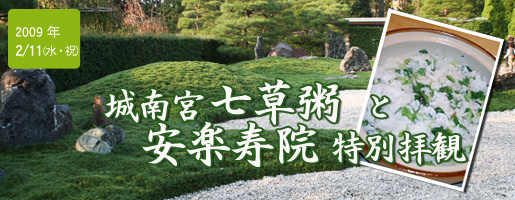
集合場所の近鉄竹田駅には30人を超える参加者が集まり、
久々に大所帯となりました。
12世紀から14世紀頃にかけてこの辺りには「鳥羽離宮」と呼ばれる
代々の上皇に使用された院御所があり、白河・鳥羽・後白河の3代の
院政の舞台となりました。
鳥羽離宮は、南殿・泉殿・北殿・馬場殿・東殿・田中殿などからなり、
近鉄竹田駅付近から国道1号線を越える広大な敷地を有していたそうです。
久々に大所帯となりました。
12世紀から14世紀頃にかけてこの辺りには「鳥羽離宮」と呼ばれる
代々の上皇に使用された院御所があり、白河・鳥羽・後白河の3代の
院政の舞台となりました。
鳥羽離宮は、南殿・泉殿・北殿・馬場殿・東殿・田中殿などからなり、
近鉄竹田駅付近から国道1号線を越える広大な敷地を有していたそうです。

鳥羽離宮の造営を始めたのは白河上皇です。
白河上皇は拡張工事を行い最終的には邸内に三重塔を中心とした
安楽寿院を創建します。
12世紀の鳥羽上皇の時代にも造営は繰り返されます。
しかし、鳥羽離宮内の史跡は全く残っておらず
安楽寿院のみが今日まで法灯を守っています。
城南宮へ向かう途中 白河天皇陵 を訪れます。こんな所に
天皇陵があるとは驚きでした。
白河上皇は拡張工事を行い最終的には邸内に三重塔を中心とした
安楽寿院を創建します。
12世紀の鳥羽上皇の時代にも造営は繰り返されます。
しかし、鳥羽離宮内の史跡は全く残っておらず
安楽寿院のみが今日まで法灯を守っています。
城南宮へ向かう途中 白河天皇陵 を訪れます。こんな所に
天皇陵があるとは驚きでした。

城南宮 に到着です。城南宮は古くから方除けの神として信仰集めましたが、
現在は交通安全の神としても有名です。4月と10月には
王朝風俗を再現した曲水の宴が催され多くの観光客で賑わいます。
本殿をお参りの後いよいよ本日のメインである七草粥をいただきます。
現在は交通安全の神としても有名です。4月と10月には
王朝風俗を再現した曲水の宴が催され多くの観光客で賑わいます。
本殿をお参りの後いよいよ本日のメインである七草粥をいただきます。

旧暦の正月7日の伝統行事で1年間の無病息災と延命長寿を
祈願しつついただきます。意外にお茶碗が大きく食べ応えがありましたね。
七草の他にも一口サイズのお餅も入っており非常に美味しくいただきました。
その後、城南宮のそばにある おせき餅本舗 でおせき餅を購入です。
餅の上につぶ餡をのせたもので、白い餅と草餅の2種類があります。
甘いものに目がないワタシですが、つい先ほど七草粥を食べたばかり。
散々迷った挙句購入するのを辞めました。次回訪れる時は必ず・・・・・・
祈願しつついただきます。意外にお茶碗が大きく食べ応えがありましたね。
七草の他にも一口サイズのお餅も入っており非常に美味しくいただきました。
その後、城南宮のそばにある おせき餅本舗 でおせき餅を購入です。
餅の上につぶ餡をのせたもので、白い餅と草餅の2種類があります。
甘いものに目がないワタシですが、つい先ほど七草粥を食べたばかり。
散々迷った挙句購入するのを辞めました。次回訪れる時は必ず・・・・・・

次の目的地は 鳥羽離宮跡公園 です。今は鳥羽離宮の石碑があるだけで
寂しい感じがします。さらに公園内には鳥羽伏見の戦いの石碑もあります。
実はこの付近、幕末に鳥羽伏見の戦いが勃発した場所としても
知られています。鳥羽方面の戦いは鴨川の小枝橋付近。
伏見方面の戦いは御香宮神社付近で始まります。
石碑の前で鳥羽伏見の戦いの経緯を説明する山村さんの口調も
段々と熱を帯びていくのがわかります。
戦場に立っているかのような臨場感たっぷりの説明は圧巻でした!!
寂しい感じがします。さらに公園内には鳥羽伏見の戦いの石碑もあります。
実はこの付近、幕末に鳥羽伏見の戦いが勃発した場所としても
知られています。鳥羽方面の戦いは鴨川の小枝橋付近。
伏見方面の戦いは御香宮神社付近で始まります。
石碑の前で鳥羽伏見の戦いの経緯を説明する山村さんの口調も
段々と熱を帯びていくのがわかります。
戦場に立っているかのような臨場感たっぷりの説明は圧巻でした!!

次は本日のもうひとつのメインであります 安楽寿院 を目指します。
途中、北向山不動院へ立ち寄ります。こちらも鳥羽上皇の勅願により
鳥羽離宮内に創建された寺院です。
そして、安楽寿院へ到着です。京の冬の旅で特別公開をしており、
さらに冬の旅初公開とのこと。特別公開・初公開と聞くと
ワクワクするのはワタシだけでしょうか。
最大の見所は鳥羽上皇の念持仏と伝わる本尊・阿弥陀如来坐像でしょう。
この阿弥陀様はなんと胸に卍が刻まれています。
そのことから「卍の阿弥陀」と呼ばれています。
その他にも、鳥羽法皇像、美福門院像などの寺宝が
特別展示をされております。
最後は雨に降られてしまいましたが、今回も充実した京都さんぽでした。
参加者の皆様、山村さんお疲れ様でした。
途中、北向山不動院へ立ち寄ります。こちらも鳥羽上皇の勅願により
鳥羽離宮内に創建された寺院です。
そして、安楽寿院へ到着です。京の冬の旅で特別公開をしており、
さらに冬の旅初公開とのこと。特別公開・初公開と聞くと
ワクワクするのはワタシだけでしょうか。
最大の見所は鳥羽上皇の念持仏と伝わる本尊・阿弥陀如来坐像でしょう。
この阿弥陀様はなんと胸に卍が刻まれています。
そのことから「卍の阿弥陀」と呼ばれています。
その他にも、鳥羽法皇像、美福門院像などの寺宝が
特別展示をされております。
最後は雨に降られてしまいましたが、今回も充実した京都さんぽでした。
参加者の皆様、山村さんお疲れ様でした。
文/らくたび会員 森田和宏様 写真/らくたび会員 鴨田一美様
2007年02月10日
「松本酒造」清酒づくり特別見学と伏見散策
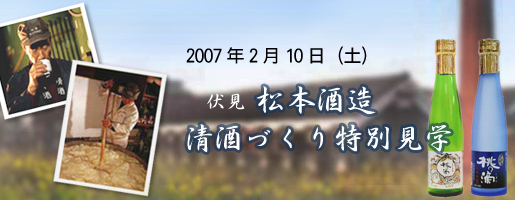
伏見は豊臣秀吉が建てた伏見城を中心に城下町として栄えた町。
今回は近鉄桃山御陵前駅から出発です。
大手筋商店街へ入ってすぐには銀座址の石碑があり、
付近にあった銀座の名残が銀座町という町名に見られます。
ちなみに東京の銀座はその後、つくられたそうです。
今回は近鉄桃山御陵前駅から出発です。
大手筋商店街へ入ってすぐには銀座址の石碑があり、
付近にあった銀座の名残が銀座町という町名に見られます。
ちなみに東京の銀座はその後、つくられたそうです。



しばらく進んで少し北にそれると、風変わりな二層の山門が。
ここは法然上人の25霊場の一つ、源空寺です。
伏見城から移築されたとされる山門の中には、
秀吉の念持仏で出世を導いたという大黒さんを祀っていました。
ここは法然上人の25霊場の一つ、源空寺です。
伏見城から移築されたとされる山門の中には、
秀吉の念持仏で出世を導いたという大黒さんを祀っていました。

商店街を抜け、5分ほど歩くと、時を経て深い黒味を帯びた
木目調の建物が見えてきました。
松本酒造さんです。
門を入って右側、まるで寺院のような重厚な玄関が迎えてくれます。
これは建仁寺にあった織田有楽斎(織田信長の弟で茶人)が使っていた
建物の玄関を移築したものだそうです。
木目調の建物が見えてきました。
松本酒造さんです。
門を入って右側、まるで寺院のような重厚な玄関が迎えてくれます。
これは建仁寺にあった織田有楽斎(織田信長の弟で茶人)が使っていた
建物の玄関を移築したものだそうです。

松本酒造の松本保博さんに迎えられ、
庭園の見える部屋へ通されました。
そこでは松本酒造さんの歴史、建物や庭のこと、お酒づくりのこと
などのお話をおいしいお抹茶とお菓子とともにいただきました。
庭園の見える部屋へ通されました。
そこでは松本酒造さんの歴史、建物や庭のこと、お酒づくりのこと
などのお話をおいしいお抹茶とお菓子とともにいただきました。

特に印象に残ったのは、酒づくりへのこだわり。
酒米選びやつくり方はもちろんですが、
何よりもつくる時の「心構え」を大事にされていることが
伝わってきました。最新の技術と伝統をうまく融合させながらも、
酒文化に誇りをもって取り組んでいける文化的環境を守っていくことが、
その心構えを支える大切な要素だそうです。
それが今日迎えていただいた、「万暁院」
(大正時代から変わらぬ有名な酒造場で、構想から完成まで1万日、
約30年の意)というお客様をもてなす迎賓館として形となって
あらわわれていると実感しました。
酒米選びやつくり方はもちろんですが、
何よりもつくる時の「心構え」を大事にされていることが
伝わってきました。最新の技術と伝統をうまく融合させながらも、
酒文化に誇りをもって取り組んでいける文化的環境を守っていくことが、
その心構えを支える大切な要素だそうです。
それが今日迎えていただいた、「万暁院」
(大正時代から変わらぬ有名な酒造場で、構想から完成まで1万日、
約30年の意)というお客様をもてなす迎賓館として形となって
あらわわれていると実感しました。



その後、できあがった日本酒を絞っているところへ案内してもらいました。
そこでは、絞った直後の酒糟(さけかす)をその場で食べさせてもらい、
絞りたての「桃の滴」をいう銘柄のお酒を試飲させていただきました。
スーッとしたのどこし、すっきりとして心地よい味わい。
少し間を置いてカーッと熱くなり、身体がぽかぽかと温まってきます。
サイコーです!気分良くおかわりまでいただいてしまいました。
そこでは、絞った直後の酒糟(さけかす)をその場で食べさせてもらい、
絞りたての「桃の滴」をいう銘柄のお酒を試飲させていただきました。
スーッとしたのどこし、すっきりとして心地よい味わい。
少し間を置いてカーッと熱くなり、身体がぽかぽかと温まってきます。
サイコーです!気分良くおかわりまでいただいてしまいました。

帰り際、お土産にと酒糟と銘酒「桃の滴」までいただきました!

松本酒造を後にし、門を出てすぐ西側の川べりに立ち寄ります。
ここからの松本酒造の全景は、伏見を代表する風景として知られています。
ここからの松本酒造の全景は、伏見を代表する風景として知られています。

竹田街道まで戻り、日本電車発祥の地の石碑を過ぎると、
油懸け地蔵という旗が見えてきます。
昔大山崎の油商人が、ここにあったお地蔵さんに油を懸けて祈願したところ
商売が大成功したことから信仰が続いているそうです。
お堂の中には油で黒光りしたお地蔵さんがいらっしゃいました。
その横には松尾芭蕉がこのお寺の住職を訪ねた時に残した句がありました。
油懸け地蔵という旗が見えてきます。
昔大山崎の油商人が、ここにあったお地蔵さんに油を懸けて祈願したところ
商売が大成功したことから信仰が続いているそうです。
お堂の中には油で黒光りしたお地蔵さんがいらっしゃいました。
その横には松尾芭蕉がこのお寺の住職を訪ねた時に残した句がありました。
「我衣に伏見の桃の雫せよ」
気付かれましたか?先ほどいただいた松本酒造さんの「桃の滴」の銘は
この句から取ったそうです。
その後は龍馬通商店街から寺田屋、伏見の運河の横を散策しながら
「島の弁天さん」で知られる長建寺、月桂冠大倉記念館の前を通り、
月桂冠の元本店である「伏見夢百衆」の前で解散しました。
松本酒造様、ご参加下さいました会員の皆様、ありがとうございました!
この句から取ったそうです。
その後は龍馬通商店街から寺田屋、伏見の運河の横を散策しながら
「島の弁天さん」で知られる長建寺、月桂冠大倉記念館の前を通り、
月桂冠の元本店である「伏見夢百衆」の前で解散しました。
松本酒造様、ご参加下さいました会員の皆様、ありがとうございました!

