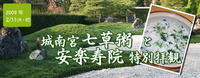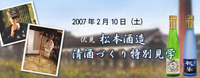2012年07月29日
7月22日 伏見の名水巡りと伏見稲荷大社・本宮祭
7月22日(土)のらくたび京都さんぽは、
伏見を歩いて史跡や名水を巡り、伏見稲荷大社では
本宮祭で明かりの灯り始めた境内を散策しました。

出発は京阪の中書島駅。今回の講師は山村先生です。

まず向ったのは竜宮造の赤い門が印象的な長建寺。

こちらには閼伽水(あかすい)というお水が。
伏見はかつて「伏水」とも書かれ、
今でも至る所で名水を頂けるポイントがあります!

伏見の特徴的な風景は酒蔵です。
月桂冠の酒蔵が続く美しい街並みを通り抜けていきます。

鳥せい本店さんにも名水の白菊水が湧き、この日も地元の方が並ばれていました。

油掛地蔵へとやってきました。かつて大山崎の油売りが門前で油をこぼし、
残りをお地蔵さんに掛けたところ、商売繁盛したという伝説を
身振り手振りで分かりやすく解説して頂けました。

キザクラカッパカントリーへとやってきました。
お酒に関する資料やお土産も買うことが出来ます。

こちらでは「伏水(ふしみず)」という名水が湧きます。
伏見でおいしいお酒が造られるのもこうした水の力があるからですね!

続いて、月桂冠の旧本店社屋を活用した伏見夢百衆さんにて
皆さんで一服です。伏見の水で入れたコーヒーなどを頂きました。

再び伏見の街を散策へ。こちらはかつてあった遊郭の建物です。
知る人ぞ知るスポットですね。

電車で移動をして伏見稲荷大社へとやってきました。
本宮祭の提灯や燈籠の点灯まで境内を散策します。

商売繁盛のご利益を求めて参拝です!

本殿の横から建築様式を詳しく解説して頂きました。
講師からの説明がないとわからないことばかりです。

千本鳥居には一足先に幻想的な明かりが灯っていました。

こちらは奥社の「おもかる石」。燈籠の上の石を持ち上げて、
予想より重ければ願いは叶いにくく、軽ければ叶うといわれている石です。
皆さんで持ち上げてみました~!

ふたたび千本鳥居を抜けて・・・

お産場稲荷を経て、楼門に戻る頃には明かりが灯り始めていました。

本日はこちらで解散!
明かりが灯り、盆踊りも始まった伏見稲荷は大いに賑わっていました。
今日は伏見をたっぷり楽しんだ一日。冷たくておいしい名水に、
本宮祭の幻想的な明かりが灯る光景は、京都の夏の風物詩です。
ご参加いただきまして、ありがとうございました!
ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥
伏見を歩いて史跡や名水を巡り、伏見稲荷大社では
本宮祭で明かりの灯り始めた境内を散策しました。
出発は京阪の中書島駅。今回の講師は山村先生です。
まず向ったのは竜宮造の赤い門が印象的な長建寺。
こちらには閼伽水(あかすい)というお水が。
伏見はかつて「伏水」とも書かれ、
今でも至る所で名水を頂けるポイントがあります!
伏見の特徴的な風景は酒蔵です。
月桂冠の酒蔵が続く美しい街並みを通り抜けていきます。
鳥せい本店さんにも名水の白菊水が湧き、この日も地元の方が並ばれていました。
油掛地蔵へとやってきました。かつて大山崎の油売りが門前で油をこぼし、
残りをお地蔵さんに掛けたところ、商売繁盛したという伝説を
身振り手振りで分かりやすく解説して頂けました。
キザクラカッパカントリーへとやってきました。
お酒に関する資料やお土産も買うことが出来ます。
こちらでは「伏水(ふしみず)」という名水が湧きます。
伏見でおいしいお酒が造られるのもこうした水の力があるからですね!
続いて、月桂冠の旧本店社屋を活用した伏見夢百衆さんにて
皆さんで一服です。伏見の水で入れたコーヒーなどを頂きました。
再び伏見の街を散策へ。こちらはかつてあった遊郭の建物です。
知る人ぞ知るスポットですね。
電車で移動をして伏見稲荷大社へとやってきました。
本宮祭の提灯や燈籠の点灯まで境内を散策します。
商売繁盛のご利益を求めて参拝です!
本殿の横から建築様式を詳しく解説して頂きました。
講師からの説明がないとわからないことばかりです。
千本鳥居には一足先に幻想的な明かりが灯っていました。
こちらは奥社の「おもかる石」。燈籠の上の石を持ち上げて、
予想より重ければ願いは叶いにくく、軽ければ叶うといわれている石です。
皆さんで持ち上げてみました~!
ふたたび千本鳥居を抜けて・・・
お産場稲荷を経て、楼門に戻る頃には明かりが灯り始めていました。
本日はこちらで解散!
明かりが灯り、盆踊りも始まった伏見稲荷は大いに賑わっていました。
今日は伏見をたっぷり楽しんだ一日。冷たくておいしい名水に、
本宮祭の幻想的な明かりが灯る光景は、京都の夏の風物詩です。
ご参加いただきまして、ありがとうございました!
ご案内 / らくたび代表・山村 純也
受付・添乗・文・写真 / らくたびレポーター・吉村 晋弥