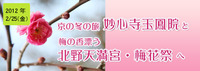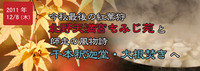2008年11月03日
源氏物語と秋の非公開文化財を訪ねて

今年は 『源氏物語』 の存在が『紫式部日記』で確認されてから1000年の
節目の年にあたることから、源氏物語にちなんだ様々な企画が
各地で開催されてきました。
そんな千年紀に沸く源氏物語ゆかりの場所を目指して出発です。
節目の年にあたることから、源氏物語にちなんだ様々な企画が
各地で開催されてきました。
そんな千年紀に沸く源氏物語ゆかりの場所を目指して出発です。

大聖寺、 三時知恩寺 はどちらも皇室ゆかりの女性が入寺された
門跡尼寺です。通常は非公開となっておりますので外からの見学となりました。
外観は大寺院とは異なりとても落ち着いた雰囲気を醸し出していました。
特別に公開される時期もあるとのことですので、チャンスがあれば
ぜひ訪れてみたいものです。
門跡尼寺です。通常は非公開となっておりますので外からの見学となりました。
外観は大寺院とは異なりとても落ち着いた雰囲気を醸し出していました。
特別に公開される時期もあるとのことですので、チャンスがあれば
ぜひ訪れてみたいものです。

報恩寺 の梵鐘は「撞かずの鐘」として京都検定テキストにも
紹介されています。西陣の織子さんと丁稚さんの揉め事から、
鐘を撞かなくなってしまった話です。
登場する人物や内容がとても具体的で、今でもその話がここに
生きている面白さがあります。
このように京都にはあちらこちらに伝説が伝わっていますが、
ハッピーエンドで終わるものだけでなく、ちょっと悲しかったり、
不気味だったりする伝説までもが大切に残されています。
物語好きの京都人の気質なのか、先人の教えを生活に取り入れる
智恵なのか・・・・・・?いずれにしても伝説が町歩きを
一層楽しくさせてくれることは間違いないでしょう。
紹介されています。西陣の織子さんと丁稚さんの揉め事から、
鐘を撞かなくなってしまった話です。
登場する人物や内容がとても具体的で、今でもその話がここに
生きている面白さがあります。
このように京都にはあちらこちらに伝説が伝わっていますが、
ハッピーエンドで終わるものだけでなく、ちょっと悲しかったり、
不気味だったりする伝説までもが大切に残されています。
物語好きの京都人の気質なのか、先人の教えを生活に取り入れる
智恵なのか・・・・・・?いずれにしても伝説が町歩きを
一層楽しくさせてくれることは間違いないでしょう。

小川通 は表千家の不審菴、裏千家の今日庵も並ぶ風情のある通りです。
もともとこの通りには小川が流れていたことから“小川通”となりました。
百々橋の礎石があったり、報恩寺や本法寺の門前には川がないのに
橋が架かっていたりすることから川の存在が確認できます。
私事ですが、以前母とこの道を歩いている時に、小川が流れていた話を
したのですが、「ホンマ?」と信用していない(?)様子でした。
ちゃんと橋を見せれば信用してもらえたのでしょうね。
今度試してみようと思いました。
もともとこの通りには小川が流れていたことから“小川通”となりました。
百々橋の礎石があったり、報恩寺や本法寺の門前には川がないのに
橋が架かっていたりすることから川の存在が確認できます。
私事ですが、以前母とこの道を歩いている時に、小川が流れていた話を
したのですが、「ホンマ?」と信用していない(?)様子でした。
ちゃんと橋を見せれば信用してもらえたのでしょうね。
今度試してみようと思いました。

宝鏡寺 は和宮が幼少期を過ごしたお寺であることから、
NHK大河ドラマ「篤姫」の篤姫紀行でも紹介されていたお寺です。
境内には門前にある和傘屋「日吉屋」さんの傘がきれいに並べられていました。
傘を作成する中で「屋外の広い場所で干す」ということが重要な工程である為、
傘屋さんはお寺の門前に店を構え、境内を借りて日干しをされるそうです。
観光用ではありませんので、いつもいつも出会える光景ではありませんが、
出会えたら“ラッキー”と思えるので、講座で教えていただいてからは
この辺りを歩く時は運試し(?)を兼ねて覗いています。
皆さんもぜひお試し下さい。
NHK大河ドラマ「篤姫」の篤姫紀行でも紹介されていたお寺です。
境内には門前にある和傘屋「日吉屋」さんの傘がきれいに並べられていました。
傘を作成する中で「屋外の広い場所で干す」ということが重要な工程である為、
傘屋さんはお寺の門前に店を構え、境内を借りて日干しをされるそうです。
観光用ではありませんので、いつもいつも出会える光景ではありませんが、
出会えたら“ラッキー”と思えるので、講座で教えていただいてからは
この辺りを歩く時は運試し(?)を兼ねて覗いています。
皆さんもぜひお試し下さい。

慈受院 は秋の特別公開中でしたので、中に入って拝観しました。
藤原鎌足の伝記であり日本最古の絵巻でもある「大織冠絵巻」、
足利義輝がお寺に宛てた手紙、後桜町天皇から下賜された屏風、
狩野探幽の掛け軸などなど、さりげなく置かれていましたが、
素晴らしい寺宝を間近で見ることができました。
藤原鎌足の伝記であり日本最古の絵巻でもある「大織冠絵巻」、
足利義輝がお寺に宛てた手紙、後桜町天皇から下賜された屏風、
狩野探幽の掛け軸などなど、さりげなく置かれていましたが、
素晴らしい寺宝を間近で見ることができました。

本法寺、 水火天満宮 を見た後は、いよいよ本日のテーマにちなんで
紫式部 のお墓参りです。紫式部のお墓は島津製作所さんの一角に
小野篁のお墓と並んで立っています。その並び方から一瞬「恋人同士?」
と思いますが、生きた時代が違いますのでそれはありません。
では、なぜ並んで立っているのかと言いますと、紫式部は
「源氏物語という架空のお話を書いた=嘘をついた=地獄行き」と
なっていたところ、閻魔様に仕えていた小野篁が源氏物語の人気振りを
伝え、地獄行きから逃れたという伝説があるからだそうです。
しかし、当の紫式部もフォローした小野篁も、まさか1000年後までブームが
続き、世界20カ国で翻訳がされるとは想像しなかったでしょうね。
また、このお墓の裏辺りから紫野小学校へ続く道は最近「紫式部通」と
名付けられたそうです。定着するのにもう少し時間がかかりそうですが、
京都の道は正面通や不明門通の様に定着さえすれば
その根拠が無くなっても名前は残ります。今後、紫式部通が
どのように発展していくのかを楽しみにしておきましょう。
紫式部 のお墓参りです。紫式部のお墓は島津製作所さんの一角に
小野篁のお墓と並んで立っています。その並び方から一瞬「恋人同士?」
と思いますが、生きた時代が違いますのでそれはありません。
では、なぜ並んで立っているのかと言いますと、紫式部は
「源氏物語という架空のお話を書いた=嘘をついた=地獄行き」と
なっていたところ、閻魔様に仕えていた小野篁が源氏物語の人気振りを
伝え、地獄行きから逃れたという伝説があるからだそうです。
しかし、当の紫式部もフォローした小野篁も、まさか1000年後までブームが
続き、世界20カ国で翻訳がされるとは想像しなかったでしょうね。
また、このお墓の裏辺りから紫野小学校へ続く道は最近「紫式部通」と
名付けられたそうです。定着するのにもう少し時間がかかりそうですが、
京都の道は正面通や不明門通の様に定着さえすれば
その根拠が無くなっても名前は残ります。今後、紫式部通が
どのように発展していくのかを楽しみにしておきましょう。

玄武神社 、 雲林院 を見学後、最後の目的地である 大徳寺 に到着しました。
大徳寺の住所は「紫野」であり、近くには「紫明通」も通っていることから、
ここら辺りと紫式部も何らかの関係があるのかもしれません。
しかし現在はその事実は明らかになっていません。でもそれはそれで
いいのではないかと私は思います。千年紀の今年、様々な行事が
各地で行われる中、新たな写本が確認されたり、違う解釈が
出てきたりしました。新発見を伝える新聞記事を読んでは、
1000年前と今が繋がることにワクワクしたものです。
(京都検定受験者としては非常に困るのですが)
そんなまだまだ秘められているであろう真実の解明は、50年後、
100年後の未来の人達に楽しんでいただけばいいと思うのです。
大徳寺でこの日の京都さんぽは終了し、
あとは希望者で特別公開をしている塔頭の拝観をしました。
この日のコースは西陣から紫野と狭い範囲ながらも見所いっぱいの
楽しいさんぽとなりました。
今年の源氏物語千年紀を記念して、11月1日は「古典の日」と
制定されたそうです。古典を楽しむことが1年限りの一過性のもの
として終わることなく、今後も少しずつその魅力を深めていければ
・・・・・・と思っています。
参加者の皆様、スタッフの皆様、お疲れ様でした!
大徳寺の住所は「紫野」であり、近くには「紫明通」も通っていることから、
ここら辺りと紫式部も何らかの関係があるのかもしれません。
しかし現在はその事実は明らかになっていません。でもそれはそれで
いいのではないかと私は思います。千年紀の今年、様々な行事が
各地で行われる中、新たな写本が確認されたり、違う解釈が
出てきたりしました。新発見を伝える新聞記事を読んでは、
1000年前と今が繋がることにワクワクしたものです。
(京都検定受験者としては非常に困るのですが)
そんなまだまだ秘められているであろう真実の解明は、50年後、
100年後の未来の人達に楽しんでいただけばいいと思うのです。
大徳寺でこの日の京都さんぽは終了し、
あとは希望者で特別公開をしている塔頭の拝観をしました。
この日のコースは西陣から紫野と狭い範囲ながらも見所いっぱいの
楽しいさんぽとなりました。
今年の源氏物語千年紀を記念して、11月1日は「古典の日」と
制定されたそうです。古典を楽しむことが1年限りの一過性のもの
として終わることなく、今後も少しずつその魅力を深めていければ
・・・・・・と思っています。
参加者の皆様、スタッフの皆様、お疲れ様でした!
文/らくたび会員 森明子様 写真/らくたび会員 鴨田一美様
4/14 白峯神宮の奉納蹴鞠見学と雨宝院の遅咲き桜を訪ねて
11月10日 報恩寺「鳴虎図」と聚楽第の足跡めぐり
8月12日 金閣寺と上七軒ビアガーデン
2月25日(土) 妙心寺玉鳳院と梅の香漂う北野天満宮へ
12月8日(木)北野天満宮・もみじ苑と千本釈迦堂・大根焚き
西陣の町家文化財 冨田屋で過ごす夏の茶話会
11月10日 報恩寺「鳴虎図」と聚楽第の足跡めぐり
8月12日 金閣寺と上七軒ビアガーデン
2月25日(土) 妙心寺玉鳳院と梅の香漂う北野天満宮へ
12月8日(木)北野天満宮・もみじ苑と千本釈迦堂・大根焚き
西陣の町家文化財 冨田屋で過ごす夏の茶話会